インタビュー/二川佳祐さん|学びを「習慣化」――継続した先に見える景色がある【注目の若手&中堅教師に聞く「わたしの教育ビジョン」Vol.05】
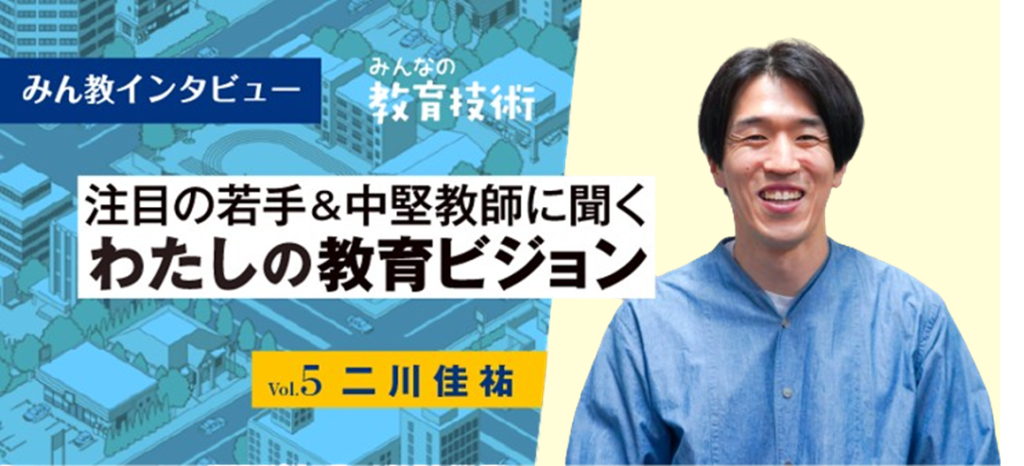
東京都の公立小学校で教鞭をとる傍ら、教員によるコミュニティー「BeYond Labo」や、Googleを学ぶ教員グループ「GEG Nerima」の運営、InstagramやVoicyといったSNSを活用した発信など、さまざまなフィールドで活躍する二川佳祐先生。学校を飛び出して活動する二川先生に、その背景や原点、教師の学びなどについて語っていただきました。

東京都練馬区石神井台小学校教諭
二川 佳祐(ふたかわ・けいすけ)
1986年東京都生まれ。教職の傍ら、「教育と社会の垣根をなくす」「今までの自分を超える」をビジョンとするコミュニティー「BeYond Labo」、Googleを学ぶ教員グループ「GEG Nerima」を運営。「大人が学びを楽しめば子どもも学びを楽しむ」をモットーに活動している。共著に『いちばんやさしい Google for Educationの教本』(インプレス)がある。
Instagram:https://www.instagram.com/futakawa.sensei/
Voicy:https://voicy.jp/channel/4074
目次
全ては「好奇心」から生まれる――学校という組織を超えて
なぜ二川先生が学校外部へと精力的に働きかけるようになったのか――コミュニティーやグループ創設のきっかけは、「好奇心」から始まったと二川先生は語ります。
「僕の性格上、誰もやっていないことをいちばんにやるのが好きなんです。なので、『教育に改革を起こそう!』とか『変えてやろう!』みたいな意識は全然なくて、自分がおもしろそうと感じた方向に進んできた結果、こうなりました(笑)。BeYond Laboの活動も、話を聞いてみたい人をお呼びして、地域の人たちといっしょに学びたいという思いから発足したんです」
現在、完全オンラインで実施しているというBeYond Laboは、教育と社会をつなぐコミュニティー。なかでも、派生企画である『マイチャレ』は、毎週日曜日の朝6時から30分間、実施しているとのこと。マイチャレは、1つの目標を掲げ、毎日できたかを日曜日にメンバー同士で発表し振り返り、「来週は、こんなことやります!」と習慣づけることを宣言する活動。半年間お互いに伴走することで、「習慣化」を身につけることをめざしているそうです。

また、教師同士でGoogleのツールを学び合う「GEG Nerima(Google教育者グループ練馬)」は、区内の小中学校の教師がICT教育についてともに学び、情報交換できる場。こちらも毎週水曜日の夕方から30分間、オンラインでお互いの実践について語り合っています。いずれの活動も毎週決まった時間に実施していることがポイントで、習慣化を意識して活動しています。
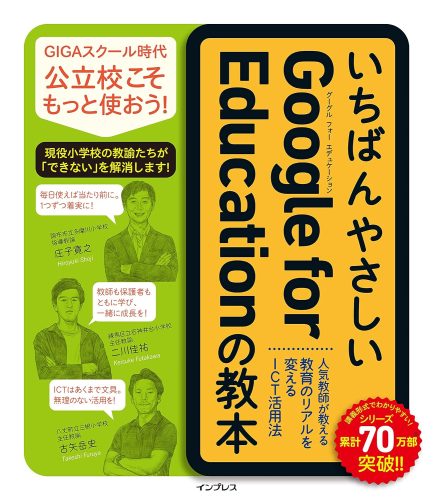
「私は、『教育は習慣』だと思っています。典型的な例でいえば、朝の会がまさにそう。もっと広く捉えれば、ランドセルで通うことも、ノートをとることも全部習慣です。
いかに子供たちにとってよい習慣をインストールできるかが重要で、そのためには環境を十分に整えなければならないですし、教師自身が常に新しいものを取り入れ、子どもたちに見せ続けなければなりません。まずは、教師が習慣化を実践することが大切なのです」
教師の学びも「習慣化」を――長期分散投資のような視点で
教員の学びについても、「習慣化」が大切であると語る二川先生。教員研修も一つのきっかけにしかすぎず、打ち上げ花火のように一時的な学びになっては意味がないと語ります。
「もちろん、研修を通して知識はつくでしょう。しかし、次の日から劇的に何かが変わるということは決してありません。何回も何回も学び続け、習慣化することで、初めて変化が訪れます。自らアクションを起こし、連続性をもたせ、常にPDCAサイクルを回していくことが重要です」
そのため、教員研修のあり方について、二川先生は「長期分散投資」のような考え方を提案します。
「数ヶ月に1回、1つの会場に集まって長時間の研修を実施するよりも、オンラインで短時間かつ定期的に行うほうが、多忙な教員には合っているのではないでしょうか。
正直な話、内容によっては『自分、これ受ける必要あったかな?』と思う研修があると思うんですよね。なので、長期分散投資のように、細かく分散して、あとは継続的に利益(知識や技術)を得ていくというスタイルに変えていくほうがいいのかもしれません。それに、もっと気軽で手軽に受けられるようデザインしたほうが、インプットしやすいでしょう」
学びの習慣化にあたっては、SNSを活用した学びがおすすめだと続けます。スマートフォンは日々の生活のなかで絶対に欠かせないからこそ、学びの連続性をもたせるのに最適なのだそう。
「自分の興味の赴くままでいいんです。まずは、検索してフォローして、情報を得るところから始めてみましょう。情報収集するなかで、『これ、ちょっとやってみよう』と入り口をつくることが大事。そこから、ちょっとしたスキマ時間に継続して触れていくことで、たとえパッチワークのような学びだとしても、積み重なっていけば、習慣化が生まれ、学びが蓄積されていきます」
自ら発信できることも、SNSの魅力のひとつ。主体的に動くことで、人とのつながりが生まれ、より情報の濃度が高くなっていくと言います。
「どんなことでもいいんです。とにかく『えいやっ!』と一歩を踏み出してみましょう。さまざまなことを発信していれば、どれか一つでも共鳴する部分を見つけてもらえて、人とのつながりが生まれます。人とのつながりが増えれば、さらに多くの情報が集まってくるようになります。SNSなら、そういった過程が距離に関係なく、スピーディーに実現できるんです」

