菊池省三の「コミュニケーション力が育つ教室づくり」 #47 菊池省三解説付き授業レポート⑪ ~千葉県鎌ケ谷市立初富小学校5年1組<中編>

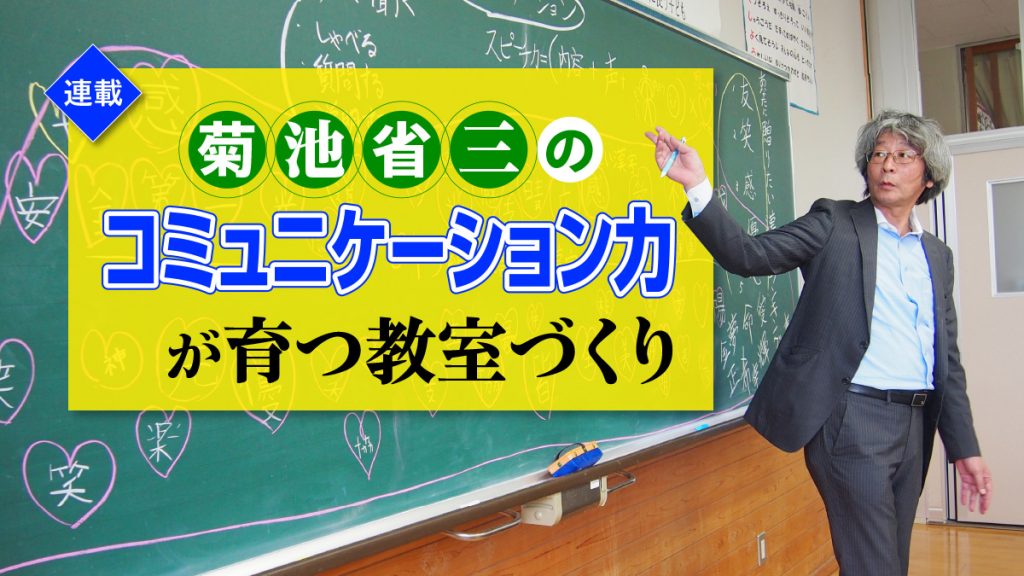
全国各地での飛び込み授業を、菊池先生ご自身の解説付きでレポートする好評シリーズ。初富小学校の5年生への授業の第2回をお届けします。菊池学級における「学びのレベルを上げる」アプローチの秘密が垣間見える必読回です。
目次
自由起立発表で、次々に意見を発表
「人間にしかできないこと、他の生き物にはできないことはどんなことか」
を菊池先生が尋ねた後、黒板の左端に次のように書いた。
<一人ひとり違っていい>
子供たちは素早く鉛筆を動かし、「3個できました」「5個書きました」と次々に声を上げた。
1分後、友達と意見交換タイム。
「今から自由に友達と写し合ったり、ひらめいたことを書き加えてもらおうと思います。多くの教室では、話し合いのとき、1人ぼっちを作ったり、『こっちにおいでよ』と誘えなかったり、男女別々に集まって話したり、決まった友達だけで集まったりしがちです。よくて、そういうことを克服しようというレベルで止まってしまっています。みなさんは全部克服しているようだから、一歩上の、『自分と同じ意見の人は誰かな』『自分と違う考えの友達に聞きたいな』と、意見交換の相手を探していく学級だと先生は考えていますが、先生の予想は当たりそうかな?」
菊池先生が尋ねると、みんながうなずいた。2分間の意見交換では、菊池先生の“予想通り”、いろいろな友達と話し合う姿が見られた。
「せっかくなので、自由起立発表を見せてもらいたいな」
菊池先生が声をかけるやいなや、何人かがすっと席を立ち、次々に発表した。
●人工雪を作れる
●何かを書く
●車を運転する
●心の成長
●しゃべる
●おしゃべり
●コミュニケーションを取る
●文字を読む
●空気を読む
●自分で考えて行動する
●共感し合う
●感情をコントロールする
●モノを作る
●価値語を書く
●火をつける
●火を使える
「ほお」「なるほど」「いいことを言うね」
と菊池先生は相槌を打ったり、
「君は生まれてすぐに車を運転できるんだなあ」
と突っ込みを入れたりしながら、子供たちの意見を聞いていった。
![]()
「どんな意見を言ってもいい」という心理的安全性が高まると、子供たちは発表することをためらわなくなります。
多様な意見が出るようになったら、教師指名から、子供主導の自由起立発表に移行していきましょう。
自由起立発表は、「自分が次に話す」というリーチをかけて発表し、次の子がまたリーチをかけて発表を繰り返します。中には、流れるような発表形式にこだわりすぎている教師もいますが、私はそこに重点を置いていません。
流れるように発表することを第一目標に掲げると、結局は “型” を重視した教師主導になってしまいがちだからです。
自由起立発表は、自律的な発言に持っていくための指導の1つにすぎません。
自由起立発表には、自分の意見を自ら発表する側面と、人の発表する意見を聞く側面があります。
「あまり発表しない子が話そうとしたら、その子を優先する」「さっきの子は自分の意見と似ている内容の発言をしたから、自分は異なる意見を述べる」。
そういう気遣いのルールが自然に生まれてきます。
これこそが、自由起立発表の醍醐味です。みんなで聞き合える、話し合える自信と安心感が、グループの話し合いに活かされるのです。
自分の頭で聞き比べ、考える教室を目指して
菊池先生が、新たな写真を提示した。
「どこかわかりますか? これは、1月1日に起きた能登半島地震の際、地震で崩壊した家へ救援に行った自衛隊の活動の写真です。みんなもニュースで見て知っているのではないかな? ヘルメットを見ると、“千葉県” と書いてあります。ここ千葉県からも救助に行って、一生懸命、命を助けようとしているんだね。こういう災害のときに、こんな仕事をしている人について、みなさんはどう思いますか?」
真剣な表情で書き込む子供たちの鉛筆の音だけが教室に静かに響いた。
1分後、鉛筆を置くと、菊池先生がみんなに話しかけた。
「さっき、友達の意見を書き加えるとき、赤ペンで書いている人がいました。鉛筆は自分が頑張って考えた証、赤ペンは友達と協力して教え合った証。
次の意見交換では、『どうしてそう思ったの?』と、詳しく掘り下げていく対話になって、赤ペンの書き込みもちょっと変わるんじゃないかと予想しているんだけど、どう思う?」
みんなが大きくうなずいた。
2回目の話し合いでは、1回目よりさらにいろいろな友達と意見を交換し、赤ペンで紙に書き込んでいく子供たちの姿が見られた。
「それでは、とっておきの1つを発表してください」
意見交換後、そのままの位置で発表した。
![]()
自分の意見を言える子供たちだったので、あえて負荷をかけ、意見交換の内容や赤ペンの意味を考えさせる言葉かけをし、そのままの位置で意見を発表する形に変えました。
このような発表の際、発表している子にカラダを向けず、ぐにゃぐにゃとしている子が何人もいる教室があります。
話し合う、聞き合うための学びが不十分だからです。今回の5年1組の子供たちは、学び合うカラダのしっかりした芯を感じることができました。
●心のダイヤモンドが輝いている、自分で磨いている
●自分軸にしている
●一人のために
例えば、一軒家に住んでいてそれが潰れても一人が助けるのではなく、大人数で助けに行っている
ジェスチャーを交えて熱心に話す子に対し、菊池先生が、
「『手にも物を言わせましょう』の勢いで発表してくれました。大きな拍手!」
と言うと、教室の場が一気に盛り上がった。発表は続く。
●何事も自分事の人
(助けに行くというのは、人の思いを自分も感じているから。何事もその人のことを考え、自分事にしている)
●尊敬した
(人を助けるのは、自分の命をかけることだし、自分も死ぬ気で助けようとしているから)
●人を助けるという思いがあってすごいと思う
●地震はいつ来るかわからないから怖い
●自分の弱い心に負けない
(「怖い」「面倒くさい」という気持ちが、助けたい気持ちに負けると、やる気がなくなってしまうから)
![]()
ぼやっとした意見や抽象的な意見が出た場合、教師が「例えば?」「もっと詳しく話して」と声をかけ、子供の意見をもっと深めていくことが大切です。
それを何度か繰り返すうちに、子供自ら「例えば○○のように、△△だと思う」「□□だと思う。なぜなら……」と発表できるようになっていきます。
発表後、子供たちが自分の席に戻ると、菊池先生が、さらに次の写真を見せた。
(このレポートは、次回に続きます。)

