低学年のICT活用は「まず楽しくやってみる」– さいたま市立大谷場東小学校・新井弓翔先生の実践
さいたま市立大谷場東小学校の新井弓翔先生は、小学校低学年の授業におけるICT活用実践で成果を上げています。豊かな発想で1年生の子供たちと取り組んださまざまな実践を紹介していただきました。比較的難しいとされる低学年でのICT活用。試行錯誤している先生たちへのヒントがいっぱいです。

新井 弓翔 (あらい・ゆみか) さいたま市立大谷場東小学校教諭。MIEE(マイクロソフト教育イノベーター)2022-2023。玉川大学在学中、「Androidで絵本アプリ」を制作。小学校に着任しMIEE認定後、「授業・校務活用素材ポータル」にて、「小学校低学年でのICT活用」「ICTを活用した業務改善」をテーマに教材提供。Microsoft Education Day 2023にてポスター発表。SCHOOL@武蔵野大学にて、プログラミング教材を使ったワークショップを企画・提供。
目次
パソコン活用は1年生1学期からスタート
さいたま市立大谷場東小学校では、1年生の入学時から1人1台の端末が用意されており、その他micro:bit(マイクロビット)やMESH(メッシュ)など各種プログラミング教材も備えています。
1年生にパソコンは無理ではないかという声も聞きます。でも、手順を簡略化したり、段階を踏んで説明したりすれば、子供たちはどんどん使い方を覚えます。昨年度私が担当した1年生は、3学期までには自分たちでパソコンを使って活動できるようになりました。
昨年度、1年生の子供たちは、プログラミング教材Viscuitでゲームを作って算数を学ぶ、Kahoot!で自分たちで問題を作って復習をする、といった活動に取り組みました。また、Microsoft Teamsを使って、みんなの作品を共有したり、あるいはPowerPointを共同編集したりすることもできました。そして、お楽しみ会では、みんなで力を合わせて、「ピタゴラなぞなぞ巨大迷路」作りに挑戦しました。そのような活動についてお話しします。
Viscuitで足し算・引き算のゲーム作り
1年生の子供たちは、入学後に「自分の好きな絵を動かそう」というテーマでViscuitを活用しました。私はこれをぜひ教科の学習にも生かしたいと思っていました。そこで、Viscuitの活用例を調べたところ、「漢字シューティング」というゲームを見つけました。漢字の「へん」と「つくり」が合体して正しい文字になると正解、という「ぶつかると変化する」仕組みを使ったゲームです。これは、算数の「足して10になる数」や「10より大きい数」の学習にぴったりだと考え、足し算、引き算のゲームを作ることにしました。
この活動は、グループで行いました。それは「システムづくりで困難を抱えない」 ことと「他の子供も楽しめる問題を、より多く考える」ことに重点を置いているからです。もちろん学年や習熟度に応じて個人の活動として行ってもいいと思います。
子供たちに作ってもらったのは、固定された数字に動く数字をぶつけて、2つの数字の合計が10になる場合のみ数字が「10」に変化するという仕組みです。子供たちは、足すと10 になるさまざまな数字の組み合わせを考えながら問題を作りました。すべてを10にできたらクリアです。そして、これを応用して引き算のゲームも作りました。
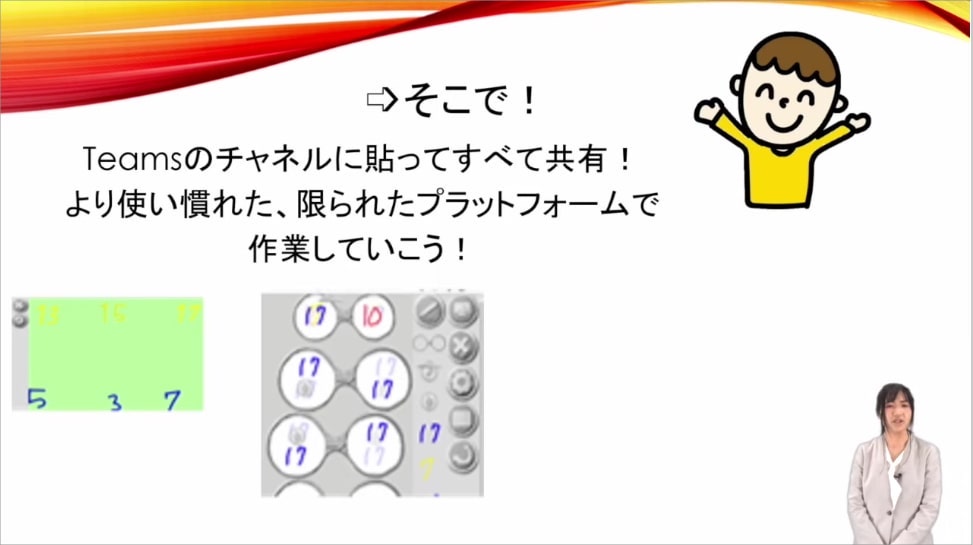
全グループのゲームのURLを、私がTeamsのチャネルのチャット欄に貼り付けて、全員で共有しました。まだTeamsを使いこなしていない1年生でも、1つの投稿にまとめることで、どこを見ればみんなのゲームがあるのかは理解することができました。
リンクを張っただけなので、誰が作った問題か子供たちにはわかりません。◯◯ちゃんが作ったゲームだからやろう、といったことは意識せずに、みんな自由にゲームを楽しみました。問題を解くだけでなく、クリアする速さや、制限時間内の正答数を競ったりしても面白いと思います。

