小1算数「ずをつかってかんがえよう」指導アイデア《ずにかいてしきとこたえをかんがえよう》
執筆/東京学芸大学附属小金井小学校教諭・尾形祐樹
編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、東京都公立小学校校長・長谷豊
目次
本時のねらいと評価規準(本時5/5時)
ねらい
場面を図に表して問題の構造を捉え、式や言葉を用いて説明することができる。
評価規準
数量の関係に着目して、図を用いて問題の解決のしかたを考え、自分や他者の考えを式や言葉を用いて説明している。
もんだい
バスていに 人が ならんで います。
ゆとりさんの まえに 4人 います。
ゆとりさんの うしろに 3人 います。
ぜんぶで なん人 ならんで いますか。
*教師が問題文を1文ずつ読んで、場面を捉えさせる。
全部でなん人か分かりましたか。
分かりました! 7人です。
違うよ。8人だよ。
意見が分かれましたね。7人と考えた人は、どうやって考えたのですか。
全部でなん人か聞いているから、たし算で、4+3=7だから7人。
違うよ! 8人だよ。だって……。
ちょっと待ってくださいね。8人と考えた人は違うのですね。では、7人と8人のどちらなのか、考えていきましょう。これまでの学習で生かせるものはありますか。
図にかけば、いいんじゃないかな。
図にかいて、7人か8人か考え、式も書きましょう。
学習のねらい
ずに かいて しきと こたえを かんがえよう。
見通し
これまで使った〇の図でかけばいいんじゃないかな。
全部でと書いてあるから、たし算だよ。
ゆとりさんは、どこにいるのかな。
自力解決の様子
A 素朴に解いている子
4+3=7と書くが、どんな図をかいてよいのか分からずに、止まっている。
B ねらい通りに解いている子
問題文の数値をそのまま使って図と式に表している。
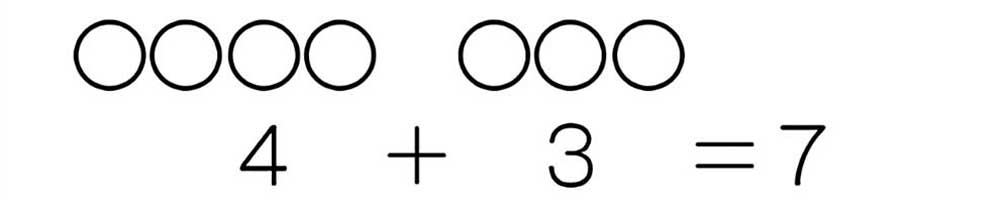
C ねらい通りに解いている子
ゆとりさんの位置を考えて図に表している。
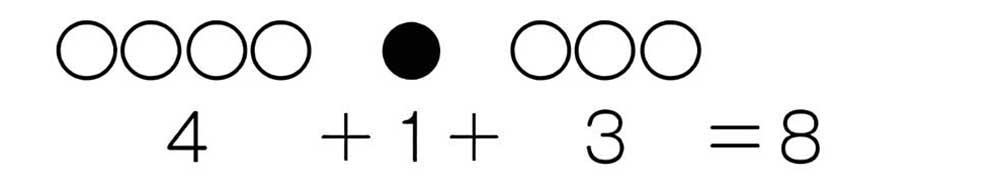
学び合いの計画
Aの子供には、4+3の4と3はそれぞれ何を表しているのかを問い、ブロックを並べて考えさせたり、この単元でかいてきた〇の図でかけないか促したりします。
イラスト/松島りつこ、横井智美
『教育技術 小一小二』2022年2/3月号より

