授業力を高めたい!③ 指導案に思いを込める|樋口綾香のすてきやん通信

Instagramでは2万人超えのフォロワーに支持され、多くの女性教師のロールモデルにもなっている樋口綾香先生による人気連載! 研究の仕方が分からなかったり一人では不安だったりする先生に向けて、授業力を高めるための手段や考え方についてお伝えするシリーズの第3回です。今回のテーマは、「授業案に思いを込める」。いっしょに学んでいきましょう!
執筆/大阪府公立小学校教諭・樋口綾香
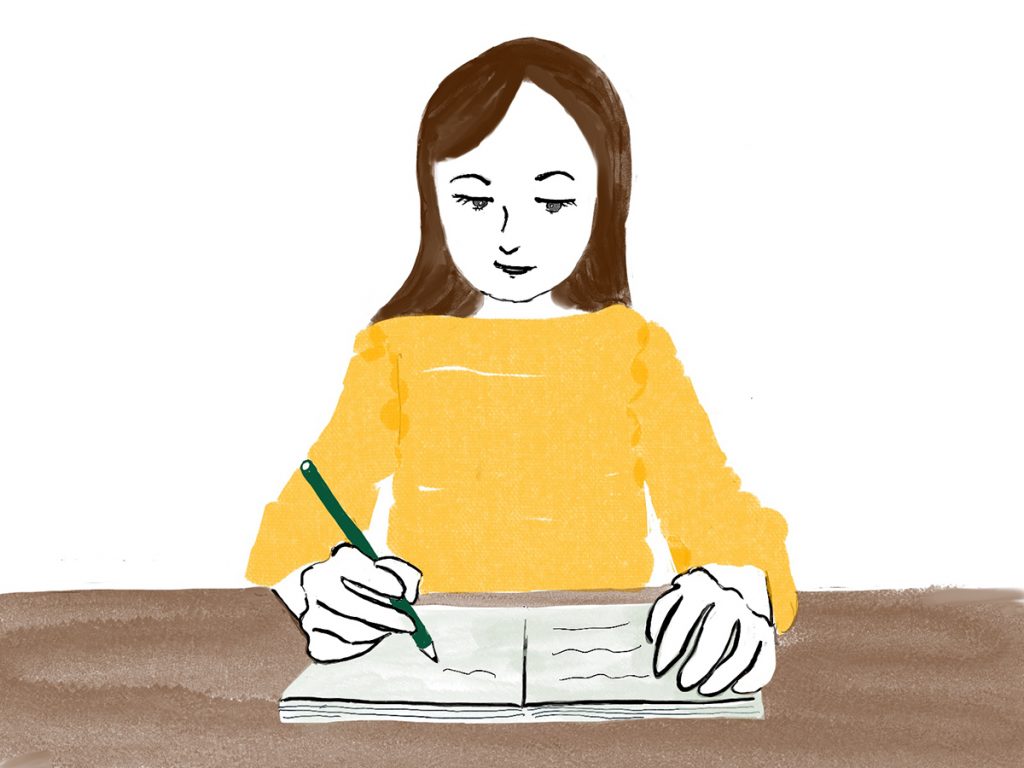
目次
指導案を書くことの価値
前回のテーマ「一年の見通し」では、以下のことに留意して授業研究を進めていくことについてお伝えしました。
- 個人研究テーマのために、自分ができることを具体的に考える
- 各学期に1本、指導案(略案)を書いて、授業を行う予定を立てる
- 授業につながりが生まれるように工夫する
今回は、上の②にあたる、「指導案の書き方」について詳しく考えていきましょう。
指導案を書くことに対して、みなさんはどんな思いをもっていますか。決して楽な作業ではないですよね。経験が浅かったころの私は、文章力がなく、苦行以外の何物でもありませんでした。50本を超える指導案を書いてきた今でも、指導案を書くのは、骨が折れる作業です。
しかし私は、この大変な思いをしながら書く指導案が、授業力を高める鍵であると考えています。
単元の全体を見通して、指導目標や評価規準を明確に捉え、それらを達成することのできる授業を組み立てていきます。一時間や一活動を見るのではなく、単元全体の中で、授業者の意図と子供の思考のつながりを織り交ぜながら、子供たちが理解を深められる授業をつくっていきます。
この計画を立てる過程において、「授業者」と「学習者」の立場を行ったり来たりしながら、思考錯誤を繰り返して指導案を書き上げることで授業力を磨いていきます。
- 予想した子供の反応と実際はどんな違いがあったか。
- 指導言や活動は目標を達成するために有効であったか。
など、自分が考えた授業実践を振り返るために、指導案は大きな役割を果たすものです。
しかし、上記のような指導案の価値を、十分に受け取れない書き方をしている場合があります。どのような書き方なのでしょうか。
指導案の価値半減? こんな書き方はもったいない!
NG① 項目ごとに分担して書く。
教材観、児童観、指導観、単元計画など、項目ごとに分けて指導案を書いているという話をよく聞きます。私もかつてこのように取り組んだことがありました。
指導案を書くとき、もっとも重要なのは、「授業者の意図」です。「研究授業ありき」で考えるのではなく、「子供ありき」で授業を考えます。目の前の子供たちが今どんな様子なのか、その子供たちにどの力をつけられる教材なのか、力をつけるためには、どんな活動がよいのか、と考えることが重要なのです。つまり、教材観も児童観も指導観も単元計画もつながりあっています。バラバラに分担してしまっては、このつながりが指導案の中に生まれません。
NG② 指導書をそのまま写す。
指導書は、具体的なクラスを想像して書かれたものではありません。そのため、大きな提案もありません。
一方で指導案は、目の前の子供のために、授業者が考え抜いた、最善の方法について書かれたものであることが望ましいのです。そのため、今のクラスで実践していること、子供たちの具体的な学習履歴とその結果、課題やそれを解決するための手立てなど、指導書には無いオリジナリティを出して、授業者の思いを込めていくことが大切です。
NG ③指導案検討によって、細かな表現を指摘しすぎる。
指導案検討というのは、授業者が指導案を書き上げたあと、学年や教科部会等で指導案を読み合わせて、授業がうまくいくかどうかを検討するものです。
指導案検討は本来、想定した授業が無理なく流れるか、子供たちの思考はつながるか、教科の見方・考え方を働かせた活動になっているかなど、「授業者」「学習者」「教材」それぞれの立場から吟味して、よりよい授業になるよう意見を出し合います。
しかし、言葉の揚げ足取りのように表現について指摘したり、誤字脱字だけを見るのは、指導案検討とはいえません。このようなことに時間をかけた結果、授業者の思いが失われてしまっては、とても残念です。

