子供の「自然をみつめる感覚」を磨く指導アイデア【理科の壺〜理科担任のはじめ方】

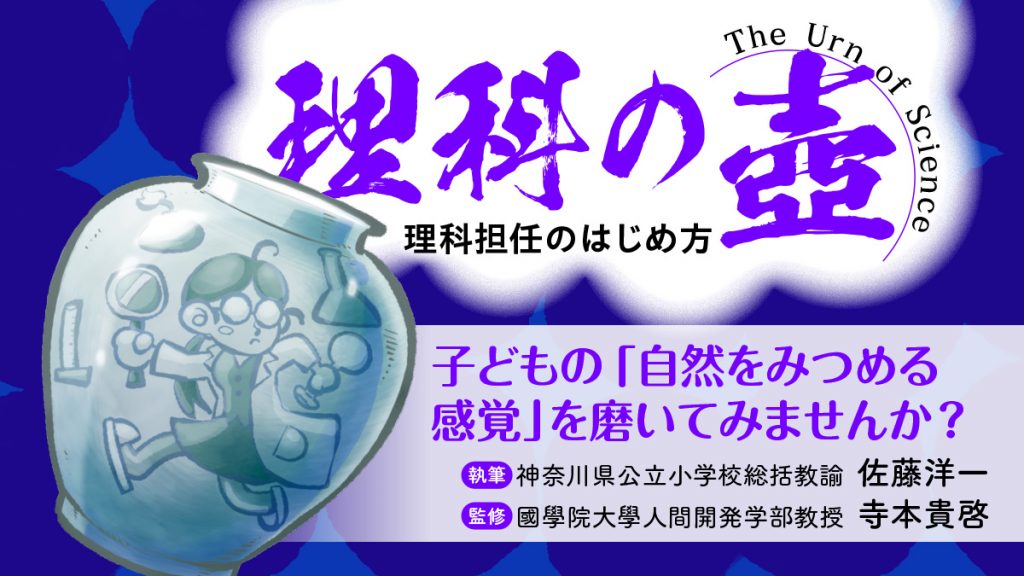
私たちが日常生活をしていると、特に意識しない限り何かをしっかり「みる」ということはしないと思います。例えば、私たちが出勤するときに毎日通る道、ここに木があるということはなんとなくわかっていても、どんな木があるのか、どのような形の葉っぱのなのか、など、細かなことを気にしていないですよね。でも、それをしっかり見ようとしたとき、何を見ますか? 「形」「色」「種」など、、、。「みるための観点」をもって物事を見ないと、自然事象を見ることはできないのです。理科では自然を様々な視点でみることができる「引き出し」を増やしたい。小学校理科では、どのように「自然をみつめる力」をつけるのでしょうか? 優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?
執筆/神奈川県公立小学校総括教諭・佐藤洋一
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
子どもの「自然をみつめる感覚」を磨いてみませんか?
学習をスタートして1か月。一緒に学んでいる子どもたちには、せっかくなら理科好きになってほしいと思いませんか?
そのために理科の授業で、子どもの「自然をみつめる感覚」を磨いてみませんか? 「自然をみつめる感覚」とは、自然の「あれ? 不思議だな」「もしかしたら…?」「こんなきまりがあるのか!」などを、自分で見つけられるようになるための感覚です。今まで見つけにくかったことを見つけられる感覚が身に付いたら…。理科好きになること間違いなしです。
「自然をみつめる感覚」を磨くには授業と授業を繋ぐことが大切です。授業で磨く「自然をみつめる感覚」って何なのか? どうやって繋ぐのか? 3年生の「植物を育てよう」と「昆虫を育てよう」の授業を通してご紹介します。
「生き物の成長を『 形 ・ 数量 』の変化でみる」という感覚を磨く視点でみてみましょう。
事例1 3年「植物を育てよう」
その1「種(たね)との出合い」
この単元では、花の種子を受け取った子どもたちが、その成長を期待することから学習がスタートします。育てたい理由を子どもたちにたずねると…「どんな芽が出るのか知りたいから!」「いつ芽が出るのか知りたいから」「どんな花が咲くんだろう? 楽しみ!!」と大盛り上がり。そこで、種と出合って、知りたくなったことを整理すると、これから学んでいくことが「植物の育ち方」であることがはっきりしてきます。
こうやって、「種はこの後どのように育つのだろうか」という単元を通した問題意識をもつことができます。
その2「芽との出合い」
「植物の育ち方」という問題意識をもって栽培活動を行ってきた子どもたちは、しばらくすると変化に気付き、喜びます。種から、芽が出ているのです。
マリーゴールドやホウセンカなど、数種類から種を選択して栽培している場合は、芽を比較することで、種類による芽の形の違いや、双葉の数が同じ(2枚)であることに着目することができます。
さらに、成長を観察すると、新しい形の葉(本葉)が見られることや、葉の数が増えていくことにも気付きます。こうやって、植物の成長と「形」や「数(量)」の関係性に気付いていきます。
「自然をみつめる感覚を磨く」ポイント
ここでは、「芽との出合い」で変化を感じた「形」や「数(量)」が、「自然をみつめる感覚」です。例えば「種から、白いひものようなもの(根)と葉っぱが2枚出てきた」のように、形や数で変化を捉えたものです。これは、2年生までの栽培経験で味わってきた「種から何か出てきた」や「新しい葉っぱが出てきた」という驚きを感じる学びから一歩踏み込んで、植物の変化を具体的に捉えています。自分も他者も「育ち方」について、同じように納得できる捉え方ということもできるでしょう。
このように、同じ感覚を通して自然を見つめ、同じことを捉えられたときに、子どもは納得します。そして、この感覚は、「次の形は…」「次の数は…」と、次の成長への明確な見通しへとも繋がっていきます。
芽と出合ったばかりの時期の子どもたちは「成長すると『形』や『数(量)』が変化する」という感覚をもち始めたばかりです。理科学習における初めての「自然をみつめる感覚」ですから、ここで全員に教え込む必要はありません。成長にともなって、形や数(量)が変わっていく様子に何度も出合い、感動し、観察することで感覚が磨かれていくと考えて指導していくとよいでしょう。
【子どもの自然のみつめ方の変化】
~その2「芽との出合い」を通して~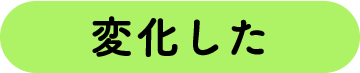
〈例〉(芽が出た)変化した
~「自然をみつめる感覚」を磨いていくと…~
〈例〉種から種類によって形が違う芽が出た。葉は2枚。白い根みたいなものもある。成長すると形の違う葉が出てくる。etc.

