小5外国語:「思考力・判断力・表現力」の育み方を教科書編集委員が解説

小学校外国語科検定教科書の編集委員でもある神奈川県公立小学校の長沼久美子先生による好評連載! 「これが知りたかった」と反響いただいた前回に引き続き、外国語学習における「思考・判断・表現」について掘り下げます。
執筆/神奈川県公立小学校教諭・長沼久美子
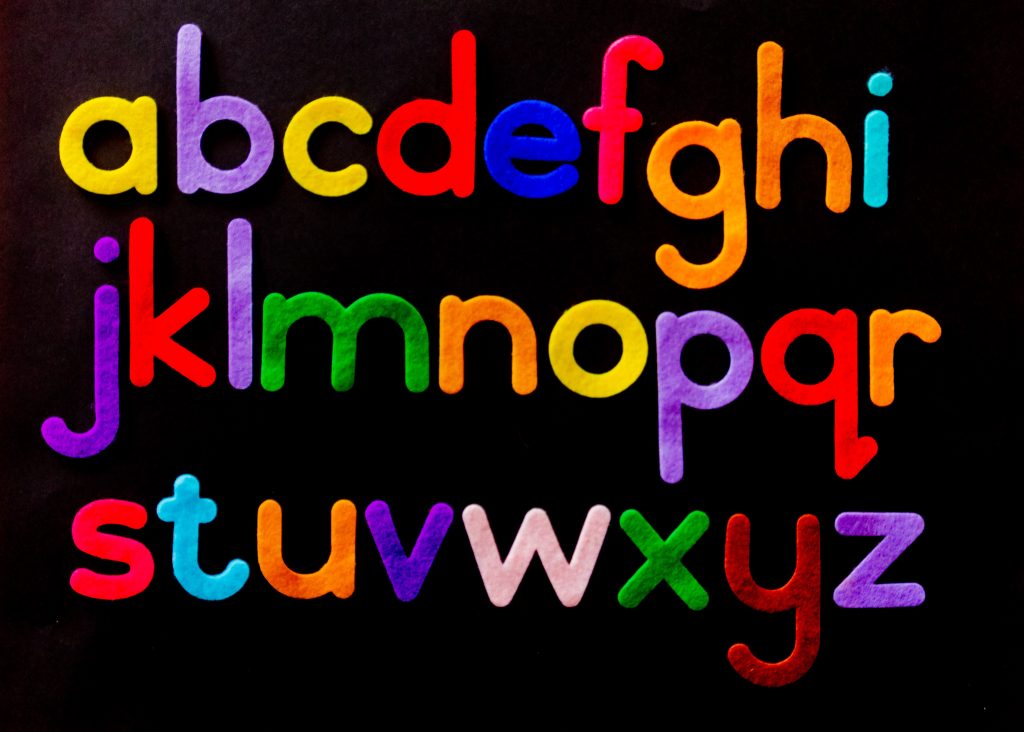
目次
Q1「オリジナルタウンで道案内をしよう」の活動で思考力・判断力・表現力を育むためには、何がポイントになりますか。
(東京書籍『New Horizon Elementary5』P.50・51)
A. 地図づくりの場面や友達とのやりとりの場面で、どんな英語表現を使うかをよく考えられるように支援してみましょう。
この活動は、目的地に向かうための道順を伝える活動です。「あなただけの町」をつくり、その町の中にある「お気に入りの場所」までの行き方をやりとりしていきます。
初めに取り組むのは「あなただけの町」づくりです。オリジナル地図をつくり、目的地となる建物や場所を配置します。どこにどんな建物を置くかなどを決める際、
policeとofficeの場所を決めよう
公園は、parkだったかな
と、英語を使いながら考えてみたり、
どのように行き方を説明すればいいのかな
と英語での表現を想定してみたりする姿などが、思考・判断になります。
ぜひ、地図づくりに取り組む子どもたちに、英語を使った表現を意識するような声かけをしてください。
次に、実際のやりとりです。
尋ねる人(案内される人)は、「Where is the〇〇?」と質問し、案内する人から行き方を聞きます。尋ねる人にとっての思考・判断は、案内する人から聞く道順の情報を組み立てて、理解することです。また、道順がわかりにくいときに質問し直すことなども、やりとりを通した思考・判断です。
案内する人は、「Where is the〇〇?」の質問において、〇〇に当てはまるものがまず何であるかを判断して、その場所を探します。そして、「どうやって行こうかなぁ」「この道順で良いかなぁ」と、思考・判断します。
考えながらやり取りすることで、定型文では収まらないやりとりが生まれるのがこの活動の魅力です。
「Turn left.」「Turn right.」等、今まで習った言葉を組み合わせながら道案内をしていく中で、話し手からの「わからない」「もう一回教えて」などの一言で更なるやりとりが生まれ、思考・判断が繰り返されると、深い学びになっていきます。
外国語学習における「思考・判断・表現」について、こちらの記事でも解説しています! → 小5外国語:「思考・判断・表現」の見取り方を教科書編集委員が解説
Q2 「Let‘s write. 自分にできることを1つ選んで書きましょう」の活動でも、思考・判断は行われますか?
(光村図書『Here We Go!5』P.65)
A. 書く活動においても、どの言葉(単語やフレーズ)を選ぶか、どのように書いていくのかという点などで、思考・判断が行われます。
教科書には、4線の上に薄い灰色で「I can」と書かれています。なぞれば良いだけになっているため、この段階で思考・判断などはしていないように思われるかもしれません。
しかし実は、「I can」を目で読み理解する瞬間に、子どもの中では、これまでにインプットされた類似の文章を想起して文章を組み立てるなどの思考・判断が行われています。
ここでは、「自分にできること」をキーワードに、同じページで紹介されている活動の英語表現を選択して、書くことを決めます。
実際に書き始めると、4線のどこに書こうか、アルファベットの大きさは十分かなど、書き方に関わる思考・判断が求められます。アルファベットとアルファベットの間隔、英単語どうしの間隔のとり方も考える必要があります。
初学習者の子どもたちにとって、アルファベットや複数の文字がつながった単語を書き写す作業は、大人が思う以上に難しいことです。
「play soccer」と書く時、playとsoccerの間がくっついてしまったり、どこか1文字が大文字になってしまったりすることもあります。文章の場合は、文頭の文字を大文字にして、文末にピリオドを打つ必要もあります。
このように、一見、単純に思えるような活動ですが、多くの思考・判断が行われています。
そして、たとえ間違って書いたとしても×をつけて返さないように。どうしてその子はそのように見てとったのかを考えながら本来の形を提示し、子どもが自ら気づくような支援を心がけると、子どもの思考・判断を促すことができます。

