「ベル音読」で子供たちに喝を【先生のための学校】

新しいクラスになれてくると、子供たちは何となくだるい態度を示す時期が出てきます。こんなときは「ベル音読」でクラスの雰囲気を変えていきましょう。
執筆/「先生のための学校」校長・久保齋

校長・久保 齋
くぼ・いつき●1949年、京都府京都市生まれ。京都教育大学教育学部哲学専攻卒業。教育アドバイザー。40年以上にわたり「学力の基礎をきたえどの子も伸ばす研究会(学力研)」において《読み書き計算》の発達的意義について研究するほか、どの子にも均質で広範な学力をつける一斉授業のあり方を研究・実践し、現在も講演活動を中心に精力的な活動を続けている。
目次
「ベル音読」とは
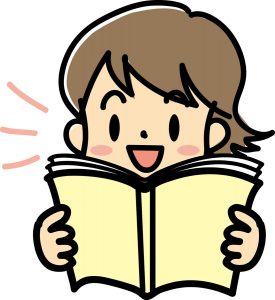
まず、先生が教室にいて、ベルが鳴ったら、すぐに音読を始めるのです。これだけでも教室の雰囲気は変わります。国語はもちろん、算数、生活、音楽、図工……、教科書のある教科はすべて、その時間に学習する範囲の音読から始めます。中学校で取り組まれている「ベル着」ならぬ、「ベル音読」です。
こうすると、遅れてきた子も授業が始まっているので、慌てて音読を始めます。遅れた子は「すみません、トイレに行ってて遅れました」などと凛々しくあいさつするように指導して、すぐに音読させるようにしておきます。
そのときの音読の方法は最もシンプルな「連れ読み」です。先生が1行読んで、それを子供全員が真似をする音読です。これを大きな声で始めるのです。
音読には不思議な力がある
音読には不思議な力があります。音読すると、なぜか子供たちが学習モードに変わるのです。
授業は文字言語の世界です。遊び時間は口頭言語・話し言葉、聞き言葉の世界なのです。音読すると、子供たちは自然に話し言葉の世界から書き言葉、読み言葉の世界へ誘われていくのです。だから、「早く授業の準備をしなさい」などと注意しているよりも、大きな声で音読させれば、子供たちは自然と授業モードになっていくのです。
もう一つ大事なことは、学習する範囲を読むということです。
こうすれば、この時間で学習する内容をどの子もおぼろげながら理解し、それがクラス全体の共通理解となっていくのです。
それだけではありません。音読は教師にとっても効果は抜群です。教材研究ができていなくても、子供たちと一緒に音読していると、自然に授業のイメージがつくられてきます。
このように授業はじめの音読、「ベル音読」 には三つの得があるのです。だまされたと思って試してみてください。

