「てびき」をキイワードに再発見する 伝説の教師 大村はまの国語授業づくり #3 代表的単元学習「花火の表現くらべ」(前編)

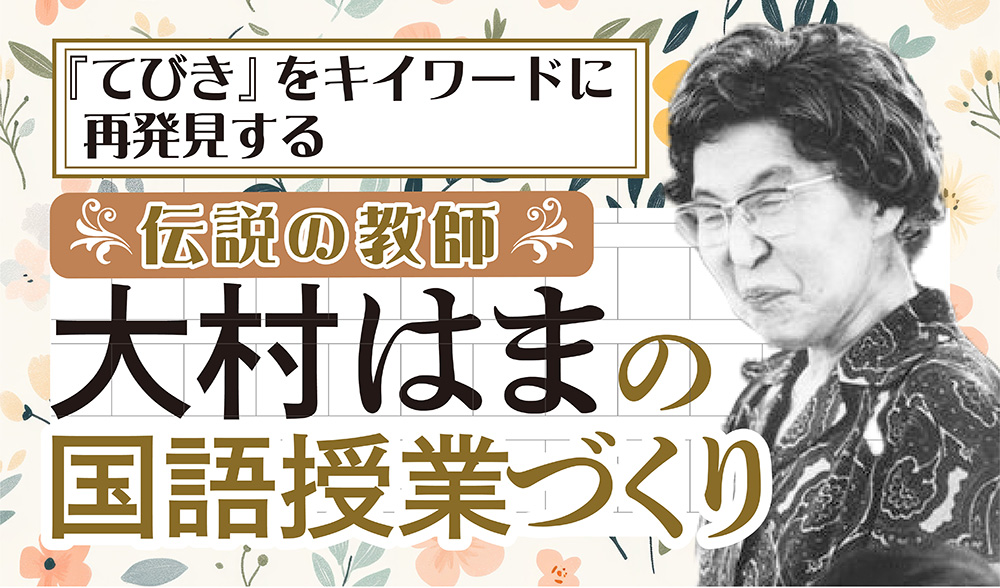
日本教育史上突出した実践を展開し、没後20年を経た今も伝説として語り継がれる国語教師、大村はま。現役時代の教え子であり、その逝去の二日前まで身近に寄り添った苅谷夏子さんが、今、改めて大村はまの国語授業づくりの「凄み」を語る連載です。今回からいよいよ、具体的な単元学習の実践例をご紹介します。
執筆/苅谷夏子(大村はま記念国語教育の会理事長・事務局長)
目次
はじめに
今回は、国語教師 大村はまのキャリア最終盤の代表的単元学習を取り上げてみたい。
1979年秋、東京都大田区立石川台中学校1年生を対象とした「花火の表現くらべ」だ。全集『大村はま国語教室』(筑摩書房)第9巻に記録されている。大村の退職から半年前の実践となる。
起源を江戸時代までさかのぼることのできる東京の夏の名物、隅田川の花火大会だが、交通事情の悪化や川の水質汚濁など社会状況が整わなくなり、1961年からはしばらく中断されていた。さまざまな努力により対策が進む中、花火大会を望む声は高まり、1978年に喜びの中で再開となった。翌1979年には、隅田川花火大会はさらに大きな期待の中で一大イベントとなり、夕刻を待たず両国橋付近には多くの人が集まり、どよめきの中で美しい花火が夜空を飾った。翌朝、在京の新聞各紙は写真入りで大きく報じた。
大村は、日頃から言語の現場に目を向け、生きた教材を求めて新聞を四紙(朝日、読売、毎日、東京)購読していたが、この花火報道を見てすぐに確かな手ごたえを感じた。ここに中学生の言葉の感覚を磨くための何よりの材料がある!
全集9巻のこの単元を記録した章の前書きで大村はこう言っている。
新聞は、同じ時の、同じ社会、同じ出来事からそれぞれに取材して書かれるので、読み比べていると、取り上げ方、見方、そして表現についても学ぶことが多く、また興味深い。
これを中学生の学習の資料としたいという気持ちで、長年、四つの新聞を探していた。
おとなとしては、読み比べて学べる記事は、ない日はないといってよいほどだが、中学生の教材にできるものは、容易に見つからなかった。
扱うのは、表現、それも語句を主に、と考え、問題の取り上げ方などは、中学生には、むりであると思っていた。しかし、たとい、語句を扱うにしても、政治・外交・経済というような面は、全体が理解できないので、教材には適さない。また、わかりやすいといっても、殺人とか誘拐とかいう事件も、内容としても語句としても適当な教材にならない。火災などは、ことばの種類が少なくて、これも教材には適さない。(略)
このようなことで、毎日見ている新聞であるのに、適当な材料に出会うことができないでいたのである。
昭和54年7月29日、朝刊を見ていた私は、実によく似た花火の写真が目についた。同じようなところから撮ったのでしょうねと思いながら見ていると、自然に、写真に添えられたことばが目に入った。朝日は「華麗 夏の夜空を彩る隅田川花火大会」。毎日は「パッと打ち上げられた隅田川の花火」。読売は「隅田川上空に咲く“巨大輪”」。そして、東京は「隅田川の夜空を彩る花火に詰めかけた観覧船もうっとり」。
私は胸が躍った。長年探していた教材であると思った。わくわくしながら、くわしく記事を見ていくと、見れば見るほど、やさし過ぎず、むずかし過ぎず、よいことば比べのできる箇所があった。
題材は花火なので美しく、また、深刻でない。みんながいっしょに見たものを、それぞれの表現にしている。何とかして、花火の打ち上げられた瞬間の美しい空を表そうとして、「絵巻物」とか「ニジ」とか「パノラマ」とか「ページェント」とか、古いもの、新しいもの、外国語、あわてたようにいろいろことばが出てくるかと思えば、人出には「繰り出す」のほかないのかなと考えさせられたほど、四紙そろって使っていることばがあったりする。
自信をもって、人数分のコピイを頼んだ。朝日一種、毎日一種、読売三種、東京二種、計七枚である。見やすくするために、大きな数字のゴム印をおした。朝日は1、毎日は2、読売が3、4、5、東京は6、7である。七枚そろえて、0号の角封筒に入れ、その封筒の右肩に、生徒の番号をおした。一番の生徒は、どの組の一番でも、教材の1を使うのである。
てびきを作り、用紙を用意し、学習に入った。
なお、てびきを渡したあと、次のような注意を添えた。
〇比較はするが、批評がましいことはしないこと。自分たちにはまだ、そういう力はない。比べて考えることで、ことばに対する感覚を鋭くする、みがくことがしたいのである。
〇ことに、もっとくわしく書けばよいとか、くわしすぎるとか、そういうことは考えないこと。他の記事との関係で、短く書いたり、少し長く書いたりすることもあり、新聞には、自分たちの作文とはちがう条件がある。
長年探しもとめていた格好の材料に巡り合って、大村はどれほど喜んだだろう。「胸が躍った」という表現は誇張ではない。
単元学習「花火の表現くらべ」
一つの出来事をめぐって四紙七つの記事が出揃えば、それを教材として展開できる国語の授業はかなりさまざま考えられるだろう。社会事象としてとらえ、報道の姿勢や取材方針などを研究するような「立派な」単元もありえるかもしれない。しかし大村はそうした派手な展開は考えず、「扱うのは、表現、それも語句を主に、と考え、問題(テーマ)の取り上げ方(の比較)などは、中学生には、むりであると思っていた」「比べて考えることで、ことばに対する感覚をするどくする、みがくことがしたい」と最初から方向性を限定している。このことの背景となる考えは何か。
まず、大村は、「表現、それも語句」を注視し、細かく味わい理解し、違いに敏感になることは、すべての言語活動の基本であり、良いチャンスがあれば常に最優先で鍛えたいと考えていた。言葉・表現にしっかりと焦点を当てて考える、ということを本気でやって、自分の言語感覚を覗きこむ体験を味わうと、生徒はそれを「面白い」と感じ、さらに良いことには、言葉が好きになる。これは大村の体験から確かなことだった。言葉が好き、という生徒が生まれれば、国語教室はいきいきとし、伸びる素地が生まれ、そして実際に言葉の力は少しずつ鍛えられていく。基本的な言葉の力が脆弱であると、どんな学習にも悪い影響がでた。素晴らしい材料に出会ったら、まず「表現、それも語句」となるのは、大村の優先順位として自然なことだった。
そして、「~などは中学生にはむりであると思っていた」ということばに見られる、子どもの力の把握の厳しさにも注目したい。生徒にも「比較はするが、批評がましいことはしないこと。自分たちにはまだ、そういう力はない。(略)新聞には、自分たちの作文とはちがう条件がある。」という注意をしている。新聞社の編集方針やほかの記事との兼ね合いなど、知り得ない部分が多い。内容や構成の適否などへの十分妥当な批評は、中学生にはまだできない、と判断しているのだ。
この「まだそういう力がない」という見極め――中学生には見えない、教室とは違う世界があること、取り上げられるできごとの「全体が理解できない」部分がどうしても残ること――そうしたことを直視する大村の姿勢は、大村のキーワードの一つである「実の場」ということばと強く結びついていることを感じる。ちゃんとできることを、ちゃんとわかっている範囲で、確かに進めていく。教室の絵空事にしない、という感覚だ。これは、前号でお伝えした子どもを困らせない、ということとも直結している。確かにできることだけを、確かなやり方で力いっぱい考えさせる、そういう基本姿勢だ。能力や経験を大きく超えたよくわからないことを、わかったつもりになって言う、ということを、あの教室では決して求められなかった。それはとても大事なことだった。そして、手の届く、自分の意見が自ずと生まれることについては、いくらでも掘り進め、考え抜いていけばいい。そういう国語教室だった。
こうして、目標を「語句の表現の比較」に絞ったわけだが、花火の記事は、その目標に即しても飛びぬけて優れていたと大村は言う。
なによりまず、扱っている出来事、光景、人々の姿が明るく、楽しげで美しい。どこをどれほど掘り下げ、追求しても、暗いもの、辛いもの、苦しくなるもの、厄介な事情に突き当たることがない。悲しくなる子が生まれない。これは、大村が非常に重視したことだった。
ことばの勉強をするときに、この「力いっぱい、存分にことばを見つめ、比べ、追求する」という頭の使い方を体験させ、体得させたいと狙っているからこそ、「存分」に追求しても教室を明るい発見で満たせる材料は、そう簡単に手に入るものではなかった。大村が「はじめに」に書いているように、事件的なものなどは、どれほど新たな語彙に満ちていようと、中学校の教室を明るい知の現場にするには、不向きであった。
そして、花火報道で使われた語彙が、生徒に身近な範囲のものである点も重要だろう。花火大会は事象としては中学1年生たちに十分既知であり、「わかる」ことがらだ。使われる語彙も幅広く、一般的である。子どもにとって未知の、あるいは縁のない領域に属するものではない。それは、学習をシンプルにしたことだろう。背景となる知識の獲得に時間を取られたら、表現くらべをする前に、子どもたちは疲れてしまったことが想像される。
夏休みの間に、大村は四紙の新聞記事を丁寧に読みすすめ、観点を拾い上げ、整理し、該当する表現を収集し、比較に結び付けていく作業をしてみた。国語教師として、大村は常に「比べる」という視点を大事にしていた。この花火大会を報じる多岐・多彩な表現を、詳細に、堅実に比べていく作業を、まず大村自身が大いに興味を惹かれ、知的興奮の中で進めていった。その下勉強の過程で、大村は全体と全体を比べる比較が非常に難しく、実際には子どもにはほとんど無理であることをまず確認した。一方、とにかくしっかりと着眼点を整理し、比べるべきものを並べていけば、確かな比較が成り立つ、表現を比べることを通してことばの感覚が磨かれる、という手ごたえをつかみ取った。たとえば、次の通りだ。
主な着眼点
・花火大会の概要 ・空模様 ・人出 ・見に来た人たち ・橋の上の情景 ・川面 ・花火打ち上げ開始 ・打ち上げの様子 ・美しい花火の形 ・花火の空 ・花火を見る人々 ・伝統を思う ・花火の玉 ・花火打ち上げ時間 ・交通整理 ・写真撮影の位置 ・その他
打ち上げの様子(各紙の記事から表現を拾っていく作業の一例)
朝 ポンポンと気ぜわしく打ち上げられ
毎 絶え間なく打ち上げられ
読 息もつかせず夜空を染める
絶えまない破裂音が耳にそう快に響く
息つくまもなく繰り広げられる
東 「無数の花火」
花火を見る人々(各紙の記事から)
朝 「下町の夏」に酔う
毎 花火を楽しんだ。 興奮
読 光の競演を堪能した。花火を楽しんだ。思わず歓声とため息が漏れる。
東 うっとり。酔っていた。楽しんだ。
大村の自宅の机の上では、こうして四紙七つの記事からことがらが拾われ、材料が拾われていき、表現を比べるという作業の具体が姿を現す。その過程で、比較という作業が直感的にも進めやすいシートも、まさに現場で得られた。単元を立ち上げる際にまず自分自身が本気で取り組んでみる、その過程をしっかり意識し、子どもに手渡すべきことを探っていくのが、大村の流儀だ。「てびき」はその過程で生まれてくる。大村自身の勉強のプロセスと知見が子どもたちにちょうどいいてびきとして、手渡されることになる。
夏休みが明けていよいよ単元がスタートする。
〈てびき プリント〉
表現くらべ 学習のてびき
七月二十九日の隅田川の花火、同じその夜の情景を報道する朝日・毎日・読売・東京の各紙の記事。
短い時間の情景を、どんなことばを使って、どのように表現しているだろう。いろんな角度から比べてみよう。できるだけたくさん、取り上げる。
一致して、同じことばの使われているところもある。どんなことばか? 興味をかきたてられる。
同じ情景をべつのことばを使って表しているところもある。どう違うか、説明のむずかしいような小さな意味の違い、語感の違い。まず、細かく読んで、比較してみるところを見つける。次に、つっこんで考え、味わうこと。
YSIの用紙を活用して、心にひらめいたこと、友だちのちょっと言ったことをすかさず書きとめる。話の筋などとはちがって、書きとめないと、せっかく気づいたことが消えてしまいやすい。これは、書いておこうかどうしようか、などと考えていないで、とにかく素早く書きとめる。
用紙は、五つの部分に分かれている。上の左を朝日、右を毎日とし、下の左を読売、右を東京にする。中央の、けいのないところ、ここへ、まわりの四紙から考えたことを書く。
このてびきはプリントとして配布されたが、もちろん大村の話し言葉による手引きも加わったことと思われる。上記の黄色くハイライトを入れた部分(ぜひ注目していただきたい部分にハイライトを入れたが、ハイライトだらけになってしまった。こういうてびきを丁寧に、確かに読み解くこと自体が勉強だった)は、事前に取り組んだ大村ならではの実感や期待のこもった誘いが感じられ、また「ひらめいたことをとにかく素早く書きとめる」というような仕事の仕方の伝授は、先輩ならではのアドバイスだ。マルチシートYSIは当時市販されていたものだが、この仕事には恰好の形であり、着目する項目ごとにこの紙を一枚使うというやり方は、中学1年生にはたいへんスマートな方法に見えたことだろう。どのグループもこのシートを10枚以上並行して扱いながら、表現比べをしていくことになる。

話し合いのてびきと学習記録
この導入のてびきのあと、学習は4人のグループに分かれて行われた。まずは、記事を丁寧に読んでいきながら、どの表現に着目し、比べるか、それをグループで出し合うことになった。話し合いのてびきはこんなだ。
〈てびき プリント〉
話し合いはこんなふうに てびき1
A(司会)では始めます。よろしくお願いします。
BCD よろしくお願いします。
A 今日は、まずどのことば、どの表現を取り上げましょうか。
B 〇〇のところ、どうですか。花火がきれいということを書いているところです。四新聞とも、これは出ていますから。
C 賛成、今、わたしもそれを出そうと思っていました。
A Dさん、どうですか。
D 賛成。賛成だけど、〇〇というところ、これも、似たような言い方で、ことばの感じがちがうので、比べてみたらおもしろそうだなと思っていたのです。
C そう、そこもぜひやりたい。
A ほかに、まだそういうところ、見つけてあるものを出してください。
B 〇〇〇の表し方はどう?
D そうそう、そこもいいと思っていた。
A わたしも一つ、出させてください。〇〇〇のところ、比べてみたいと思っているんだけど。
B そこもおもしろいと思う。その表現のちがい、なかなかことばで説明するのはたいへんだと思うけど、それだけにやりがいがある。
C それは、四つの新聞に出てる?
A いえ、三つです。
D 三つでもいいじゃない?
これは、話し合いの台本型てびきと言われ、大村がしばしば活用したスタイルだ。4人のグループで、まずどういうところから、どういう調子で話しだせばいいか、それにどう応じ、どう自分の考えを添えていくか、たとえ四紙に共通していない事柄であっても、三つでもいいんじゃない、というようなヒントも出している。これをクラスで共有してから、表現を比べる事項を洗い出し、整理する作業が始まっていくことになる。
<↓生徒たちによるYSI用紙の記入例>

ある生徒の学習記録にはこんな書き込みがある。
9月21日
グループ全員で新聞を読んだ。そしてYSIという紙に、「花火がきれいなこと」というテーマで各新聞のそれぞれの言葉を探しだした。
〈今日の感想〉
どの新聞にもたくさんの表現があり、それぞれちがっていた。四種の新聞の中には、同じ表現もあったが、あまりにもいろいろな表現があるのにおどろいた。今日はまだ初めてなので、一つのテーマしか探せなかった。が、次の時間からは、がんばってたくさん探したい。
9月25日
1番のテーマ「花火がきれいなこと」は、多くの種類のものを一まとめにしてしまったので、今日はそれを種類別に分けた。2番もやった。
〈今日の感想〉
新聞を読めば読むほど、いろいろなテーマが出てくる。一度目に読んだ時には気が付かなかった表現に気づいたりした。
いろいろな表現が見つかるととても楽しい。
9月27日
テーマは一グループ最低10個。私たちのグループの目標は15個。一日5個ずつ探し出す。今日は目標が達成され、5個探し出せた。
〈今日の感想〉
5個探し出せて、とてもうれしい。明日はもっとたくさん探したい。
このグループは、最初、「花火がきれいなこと」という観点から表現を拾い集めようと試みた。しかし「あまりにもいろいろな表現があるのにおどろ」き、そして実は「花火がきれいなこと」という観点では、つい多くの種類のことを一まとめにしてしまったために比較がむずかしくなっていたことに気づき、テーマを更に細かく分けることにした、と言う。このプロセスを自力で行ったというだけでも、中学1年生にとっては知的な、高度な取り組みだったと言えるだろう。「読めば読むほど、いろいろなテーマが出てくる。……いろいろな表現が見つかるととても楽しい」。大村のてびきが、道筋を示しすぎることなく、しかしちゃんと生徒たちを惹きつけて主体的な考える人にしているのがわかる。比べるということを、比べるべき材料を集めるところからスタートさせることを、つい半年前まで小学生だった、大村に出会ってまだ半年しか経っていない13歳たちが体験し、明日はもっとたくさん探したいと張り切っている。実は、表現を比べる作業は、すでにテーマを拾い出すプロセスの中でスタートしていたはずだ。
この単元の続きは、次回お届けしたい。

<大村はま略歴>
おおむら・はま。1906(明治39)年横浜市生まれ。東京女子大学卒業後、長野県諏訪市の諏訪高等女学校に赴任。その後、東京府立第八高等女学校へと転任。すぐれた生徒たちを育てるが、戦中、慰問袋や千人針を指導、学校が工場になる事態まで経験する。
敗戦後、新制中学校への転任を決め、後に国語単元学習と呼ばれるようになった実践を展開。古新聞の記事を切り抜いて、その一枚一枚に生徒への課題や誘いのことばを書き込み、100枚ほども用意し、駆け回る生徒を羽交い締めにして捕まえては、一枚ずつ渡していったと言う。1979(昭和54)年に教職を去るまで、単元計画をたて、ふさわしい教材を用意し、こどもの目をはっと開かせる「てびき」を用意して、ひたすらに教えつづけた。退職後も、90歳を超えるまで、新しい単元を創りつづけ、教える人は、常に学ぶ人でなければならない、ということを自ら貫いた。著書多数。
2005年、98歳10ヶ月で他界。その前日まで推敲を進めていた詩に、「優劣のかなたに」がある。
<筆者略歴>
かりや・なつこ。1956年東京生まれ。大田区立石川台中学校で、単元学習で知られる国語教師・大村はまに学ぶ。大村の晩年には傍らでその仕事を手伝い、その没後も、大村はま記念国語教育の会理事長・事務局長として、大村はまの仕事に学び、継承しようとする活動に携わっている。東京大学国文科卒。生きものと人の暮らしを描くノンフィクション作家でもある。
主な著書に『評伝大村はま』(小学館)『大村はま 優劣のかなたに』『ことばの教育を問い直す』(鳥飼玖美子、苅谷剛彦との共著)『フクロウが来た』(筑摩書房)『タカシ 大丈夫な猫』(岩波書房)等。
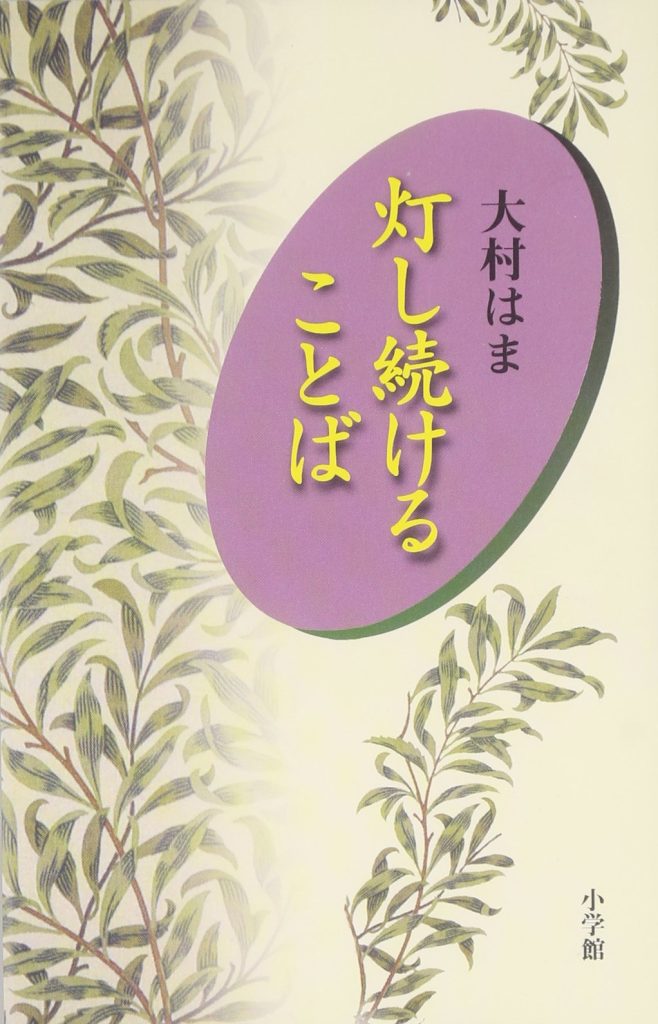
ロングセラー決定版!
灯し続けることば
著/大村はま
「国語教育の神様」とまで言われた国語教師・大村はまの著作・執筆から選びだした珠玉のことば52本と、その周辺。自らを律しつつ、人を育てることに人生を賭けてきた大村はまの神髄がここに凝縮されています。子どもにかかわるすべての大人、仕事に携わるすべての職業人に、折に触れてページを開いて読んでほしい一冊です。(新書版/164頁)
大村はま先生の貴重な講演動画!「忘れ得ぬことば」大村はま先生 白寿記念講演会 5つのことばがつむぎ出す、国語教育の源泉【FAJE教育ビデオライブラリー】〈動画約60分〉がこちらでご覧いただけます。

