【シリーズ】高田保則 先生presents 通級指導教室の凸凹な日々。♯13 巡回指導教員だから見えた「小中連携」の課題と可能性
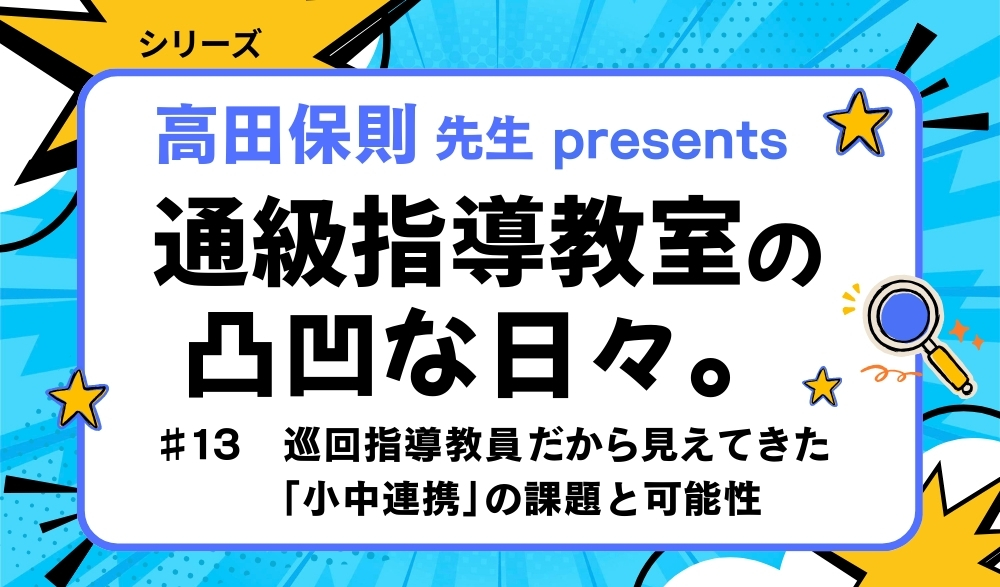
通級指導教室担当・高田保則先生が、多様な個性をもつ子どもたちの凸凹と自らの凸凹が織りなす山あり谷ありの日常をレポート。情熱とアイデアに満ちた実践例の数々は、特別支援教育に関わる全ての方々に勇気と元気を与えるはずです。今回は、複数校を巡回するお立場ならではの考察と提案です。
執筆/北海道公立小学校通級指導教室担当・高田保則
目次
はじめに
北海道オホーツク地方の小学校で、通級指導教室を担当している高田保則(たかだやすのり)です。日々、子どもたちと向き合う中で感じたことや考えたことを綴っています。ここに記す事例は、これまでに出会った子どもたちのエピソードを組み合わせてつくった架空のお話ですが、実際に過ごした時間の空気感を込めています。
今回は「巡回指導から考える小中連携」をテーマにまとめてみました。私は近隣の学校を訪問する巡回通級指導を担当しています。中学校の美術教諭が複数校で授業を受け持つように、今の学校現場では複数校を行き来して指導にあたる教員が少なくありません。その職務に自ら就いてみて感じたことを記します。
1.巡回指導を担当する
これまでの私の仕事は、通級指導教室に来室した子どもと活動する、いわば“待ちの指導”でした。そこに新しく加わったのが、近隣の学校を訪問して行う巡回通級指導です。そして訪問先には中学校も含まれていました。小学校一筋でやってきた私にとって、中学校での指導は初めての経験でした。新しいことにワクワクする性分の私は、期待に胸をふくらませていました。
2.戸惑いのスタート
しかし、中学校への巡回を始めてみるとイメージとの違いに戸惑うことが多くありました。中学校の職員室は静かでした。教員は授業の合間に職員室へ戻り、事務作業に没頭していました。コピー機の音やキーボードを打つ音だけが響き、雑談の余地は感じられません。そうなると、週に一度の訪問では、教職員の顔と名前を覚えるのに時間がかかり、関係を築く機会も限られてしまいました。
私は子どもの情報を多面的に集め、分析して指導に生かすことを得意としています。しかし中学校では情報が十分に得られず、指導の手立てを考えるのが難しいのです。さらに、生徒は敬語で挨拶をするものの、私がどんな立場の人間なのかを理解しておらず、一線を画すような空気をまとっていました。
次第に私は中学校への巡回を憂鬱に感じ始めました。
「どうして、子どもの面白いエピソードや成長を笑顔で語らないのだろう?」
「生徒の学力を伸ばすことが、そんなにも大切なのだろうか?」
「生活態度の改善に注力するあまり、生徒の困りが見えなくなってはいないだろうか?」
そんな風に思うようになったのです。中学校で目にする光景や耳にする声をネガティブに感じるようになっていきました。
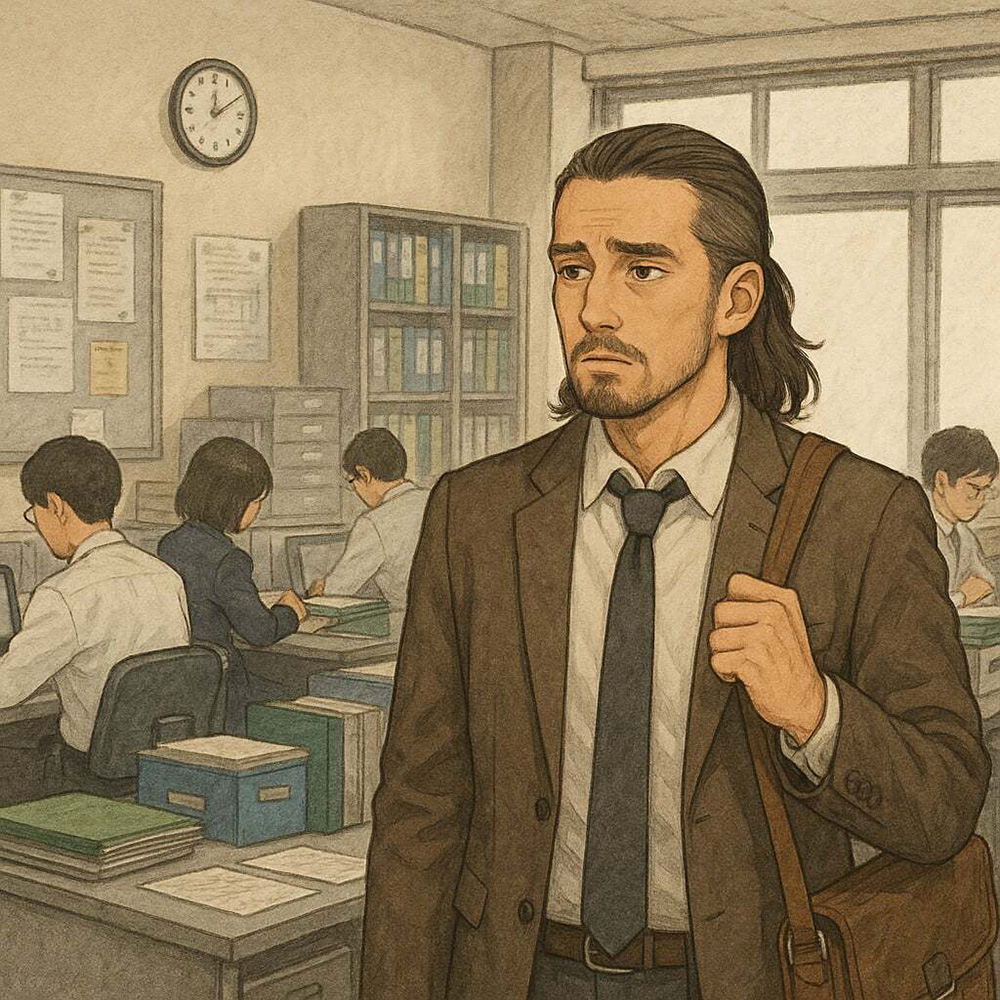
3.装う生徒と関わる
そんな折、校長先生から「通級指導教室に通う生徒は高田先生が来る日をとても楽しみにしています」と言われました。実際、出勤すると生徒は笑顔で迎えてくれ、次第に担当以外の生徒からも声をかけられるようになりました。すると、私の心も軽くなり、生徒と話すのが楽しくなってきました。
サッカーに夢中のAさんは、逆転ゴールを決めた試合を誇らしげに語ってくれました。しかし出席簿には欠席が続き、心理的な要因が背景にあると聞きました。明るい語りと現実とのギャップを強く感じました。
クルマ好きのBさんは、職員駐車場に並ぶ車の名前をすべて言い当て、特徴まで熱心に解説してくれました。その知識量には舌を巻くほどでした。一方で、生活面ではルール違反が増えており、日常の姿との落差が際立っていました。
アニメ好きのCさんは、動画サイトで見つけた海外アニメ映画を嬉しそうに紹介してくれました。設定や描写の違いを語る表情は、生き生きと輝いていました。しかし、感情の波が激しく、時に友達に暴言をぶつけてしまうこともありました。
週に一度の短い時間しか会えない私に、生徒たちは「良いところを見せたい」という思いを込めて接してくれていたのかもしれません。そして、自分のポジティブな面だけが見えるように装っていたのかもしれません。
「巡回指導教員ならではの、役割が果たせるかもしれない。」
私はそう閃きました。
4.巡回指導教員の役割
私は生徒の話にじっくり耳を傾けることにしました。
「中学生って、すごいのね。」
「大人並みに、いろいろ知ってるんだ。」
「マニアックだなぁ。」
そう返すと、生徒の表情はますます輝きを増し、喜んで語りました。
これでよいのだと思えるようになりました。巡回指導教員は限られた情報しか得られません。だからこそ、生徒のポジティブな側面に光を当て、中学校の教職員とは違う視点で情報を提供することが役割なのだと気付きました。
半年が経った今では、中学校の職員室でも職員と冗談を言い合えるようになり、生徒の視線も温かさを帯びて感じられるようになりました。「中学校だから」と過度に構えていたのは、私自身だったのかもしれません。

5.違いを活かした小中連携へ
少子化が進むオホーツク地域では、小・中9年間の教育を一貫して行う義務教育学校が増えています。義務教育学校の開設に向けた教員研修も盛んに行われています。そうした研修の場で、小中の教員が意見を交わすと、指導の前提となる考え方の違いが浮き彫りになります。
小学校教員は6〜12歳の発達を見守り、中学校教員は13〜15歳の自立を支えます。両者の視点は異なります。それは発達段階に応じたアプローチの違いによるものです。その違いを互いに認め、良さを活かし合うことが、これからの小中連携には欠かせないと感じます。
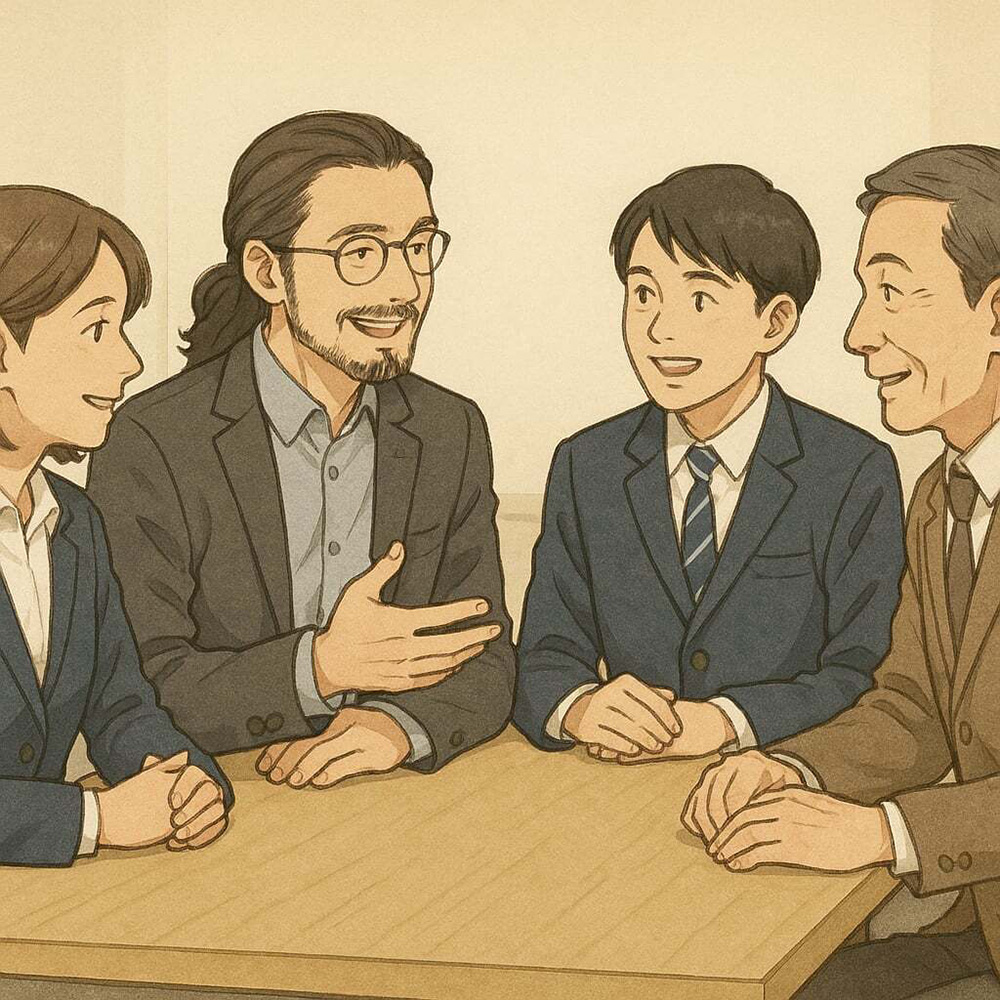
おわりに
巡回指導を通して見えた小中の違いは、義務教育学校が目指す「9年間の一貫教育」にもつながります。互いの立場や視点の違いを尊重しながら、子どもの成長を継続して支えることこそが、小中連携の本質であり、地域の教育の未来を形づくる力になると確信しています。
※参考資料
〇『複数校指導の手引き』 文部科学省(令和3年3月)
〇『学校基本調査』 文部科学省(令和7年8月)

高田保則先生プロフィール
たかだ・やすのり。1964年北海道紋別市生まれ。オホーツク地域の公立小学校教諭。公認心理師。特別支援教育士。開設された通級指導教室の運営を任され、新たな指導スタイルを模索している。趣味はバンド演奏。

