「すごいね!」「いいね!」のその先がある「価値付け」 ~子どもの学びを広げ、深める「価値付け」をしよう~【理科の壺】

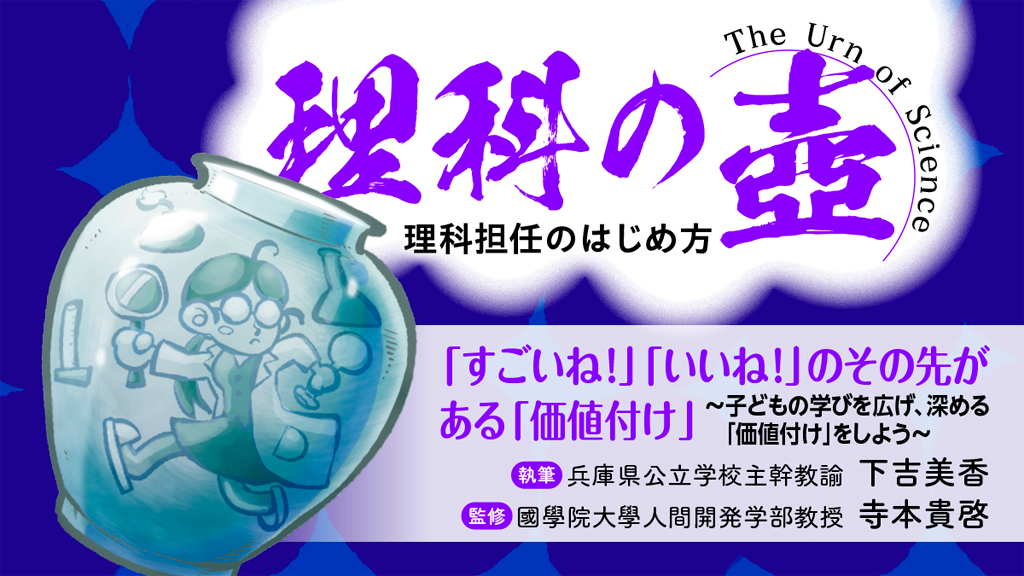
言葉の表面上で「いいね」と言われて、みなさんはうれしいでしょうか。具体的に何がよかったかを言ってくれると「よく見てくれている」と思いますし、何でほめられているかよくわかるので、よりうれしく思うのではないでしょうか。教育場面での「価値付け」は、個人への「ほめ」の役割だけではなく、学級全体の「学びの機会」と捉えることができます。今回は、価値付けをどのように行い、どのように学級全体の「学びの機会」とするのかについて考えていきます。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/兵庫県公立小学校教諭・下吉美香
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1.「価値付け」ってどういうこと?何のためにするの?
「価値付け」とは、子どもの言動をしっかり見取り、その意味や価値を、教師が言語化して具体的に伝えることです。
子どもの頃、ノートに花丸がつけてあったり、先生からの「すごいね!」「いいね!」などのコメントがあったりすると、嬉しかったことを覚えていませんか。そして、もっとがんばろう、と思ったことを覚えていませんか。「価値付け」には、子どものやる気や主体性を引き出す効果があります。つまり、「価値付け」は、子どもの力を引き出し、伸ばすために行う、教師ができる大切な役割の一つなのです。
2.「すごいね!」「いいね!」だけでは、真の「価値付け」になっていない?!
日々、子どもたちと学習している中で、「すごいね!」「いいね!」と思わず声をかけたくなる瞬間があります。新任の頃、先輩の先生に、ほめる言葉は、子どもの心に届くよう、短く、インパクトがあるように、と教わったことがあります。たしかに、「すごいね!」「いいね!」は素直に嬉しい言葉ですし、やる気や主体性を引き出すことができます。ですが、経験を重ねてきた今、「すごいね!」「いいね!」だけでは、真の「価値付け」になっていないな…、と思うようになりました。なぜなら、「いいね!」「すごいね!」のその先に、何がいいのか、どこがすごいのかを明確に、的確に伝えてこそ、子どもの学びを広げ、深める「価値付け」となる、と考えるからです。

