読む必要感を生む「AI生成画像まちがいさがし」|子供たちが前のめりになる学級経営&授業アイデア #6

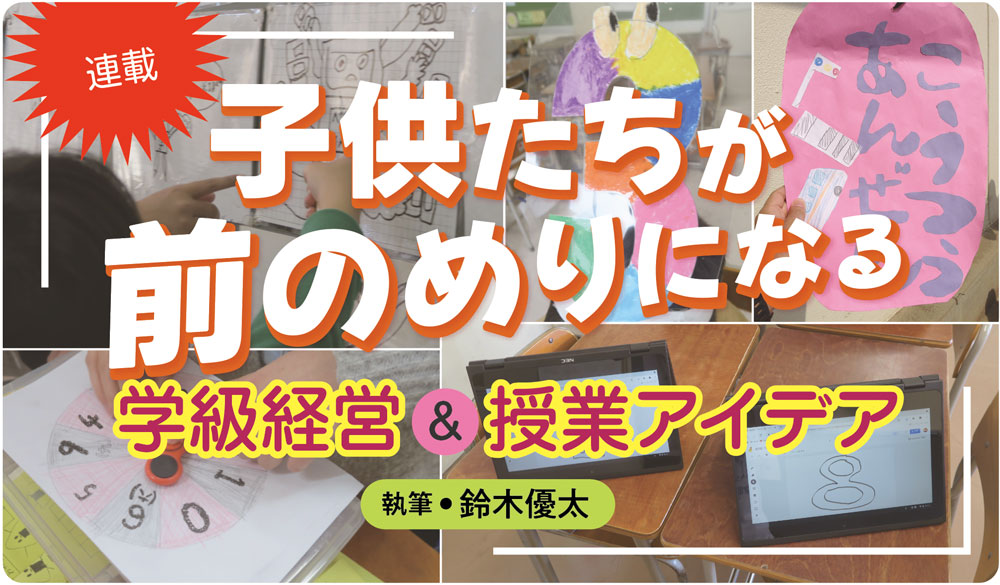
学級経営と授業改善について、アナログとデジタル、それぞれのよさを融合しながら唯一無二の実践を続ける鈴木優太先生の連載です。子供たちが熱量高く、前のめりに学習したり活動したりする学級づくりや授業のアイデアを、毎月1本紹介します。今回は、国語の授業アイデア「AI生成画像まちがいさがし」を取り上げます。
執筆/宮城県公立小学校教諭・鈴木優太
目次
今や必須スキル「生成AI」を活用した授業づくり
子供たちの目が教科書に釘づけになり、何度も本文に立ち返りながら、自分の根拠を伝えようと前のめりになる姿が教室にあふれます。
きっかけは、AIが作った少しだけまちがった画像。ズレを見抜くためには、教科書の細部を正確に読み取らなければなりません。
読まなければ説明できない—そんな読解の「必要感」が、自然と生まれてくるのです。「AI生成画像まちがいさがし」で読む力を深める、国語の授業での新提案をお届けします。
必要感のある読解はこう生み出す―フェイク画像で深まる読解力

これ、ちがう! 夜じゃないよ、お昼すぎって書いてあるもん!
隣の子に顔を寄せながら、教科書と画像を見比べて指摘する子供の声。2年生の国語「どうぶつ園のじゅうい」(光村図書出版)の第6時です。
教科書の文章をもとにAIが生成した「フェイク画像」を提示しました。

これはフェイク画像です。ペアでまちがいさがしをしましょう。
子供たちは、この画像と教科書を何度も見比べます。画像の中のまちがいを探すという明確なミッションのもとに、教科書の記述を頼りに次々と証拠を挙げていきます。「教科書を読みなさい」と、教師が指示をしなくても、何度も何度も読み返しています。線を引いたり、囲んだりしている子もいます。そして、自分の気付きに理由を添えて説明します。
夜ではありません。なぜかというと、お昼すぎだからです。
目の治療ではありません。なぜかというと、歯ぐきの治療だからです。
飼育員は一人ではありません。なぜかというと、(P128)9行目に「三人」と書いてあるからです。
「時」「仕事」「工夫」など、押さえたいポイントを、子供たちは自らつかみ取っていきます。「なぜかというと〜、だからです」という論理的な表現が口から出てきます。この姿から見えてきたのは、「必要感」を伴う仕掛けがあれば、子供は自ら教科書にかじりつくということです。「教科書を読みましょう」「線を引きましょう」「理由を説明しましょう」と教師が丁寧に指示を出す授業ももちろん大切です。しかし、今回はやりたいからやってしまう構造が自然と成立していたのです。その鍵は、「AI生成画像」という新たな教材と、子供たちが大好きな「まちがいさがし」のゲーム性にあります。
「AI生成画像まちがいさがし」は、子供たちに説明させるのではなく、「説明したくなる授業」を生み出す強力な仕掛けです。

