【連載】坂内智之先生の 愛着に課題を抱えた子が伸びるアプローチ~学級担任にできること~#8 愛着障害の子どもを伸ばす特別活動、5つのポイント―実践編その4―
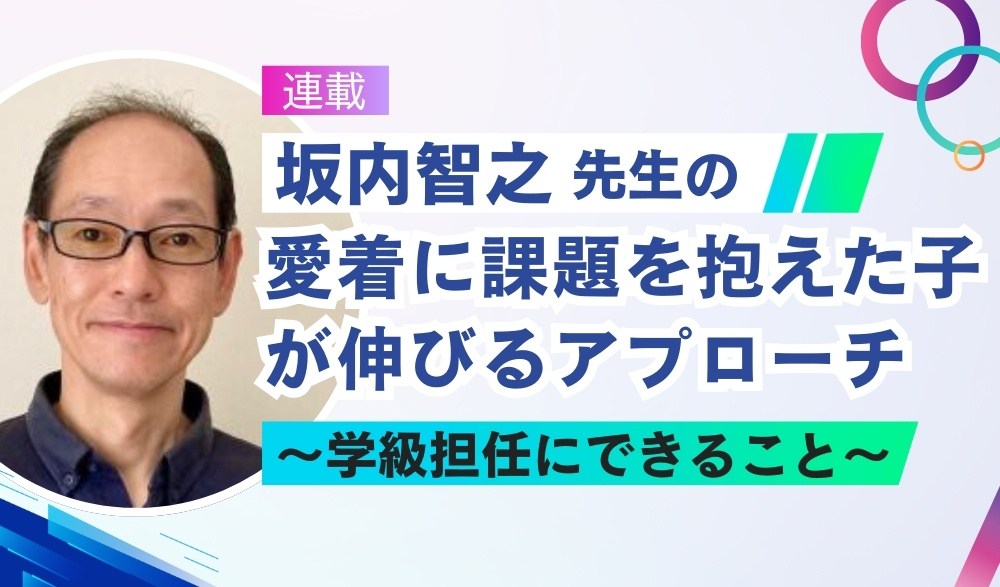
近年、教員たちが対応に苦慮し、学校現場を根底から揺るがしている「愛着障害に苦しむ子どもたち」。そうした子どもたちによって荒れた学級を何度も立て直してきた坂内先生が、今、学級担任に何ができるのかを提案し、これからの学級のあり方について考えていく連載第8回。今回は、愛着障害の子どもたちを伸ばす特別活動のあり方について提案します。
執筆/福島県公立小学校教諭・坂内智之
目次
はじめに
「特別活動」は、どの学校でも毎日のように行われている教育実践です。一方で、特別活動のもつ力をフルに引き出せている先生方は少ないのではないでしょうか。
特別活動とは、学級活動、児童会・生徒会活動、クラブ活動、そして学校行事の4つの活動から成り立っています。この活動の大きな特徴は、「自己評価」「自己調整」「集団活動」「自ら考える」「相手のよさを実感する」「自分のよさを感じ取る」など、自分の姿や相手に焦点を当てながら、心を育てていく活動であることです。
ところがこれら上記のキーワード、子どもと最前線で接している教師なら分かるように、愛着障害、愛着に課題を抱える子にとっては、どれも苦手なことばかりです。当然、困り感やトラブルも、特別活動の場ではとても起こりやすくなります。特に運動会や発表会などの学校行事で、大いに苦戦した経験がある方も多いことでしょう。
それでも前回お伝えしたように、こうした教師が苦戦しやすい場にこそ、子どもの愛着を修復していく新しい回復モデルのヒントが隠されています。
今回はこの特別活動に焦点を当て、愛着に課題を抱える子どもたちの回復プロセスについて提案していきたいと思います。
1 なぜ、特別活動が苦手なのか
愛着に課題を抱える子どもが特別活動を苦手とする理由は、特別活動で求められる下のような子どもの姿を再確認してみるとよく分かります。
「自己評価=自分を客観的に見つめること」
「自己調整=自分の心を見つめまわりの状況に合わせること」
「集団活動=相手の心に自分の心を寄り添わせること」
「自ら考える=自分の考えていることを見つめること」
「自分のよさ=自分のよいところを探し出せること」
このように言葉を置き換えてみると、愛着に課題を抱えている子どもはこうしたことがとても苦手だと実感できると思います。
「あなたはどう思った?」→「分かりません!」
「あなたはどうしたい?」→「どうでもいいです!」
「どっちを選びたい?」 →「先生が決めて!」
「みんなとどうする?」 →「やりたくない!」
教師が言葉をかけても、こうした返事が返ってくることが多いものです。
また、近年は集団活動になると参加したくない、一人でいたいという子どもも多くなりました。気になるのは、愛着に課題を抱える子どもは、どうしてこういう反応をしてしまうのかということです。
私はその理由を、自己有能感の感じにくさ、そして不安感だと考えています。
それは、以下のようなエピソードからも分かります。
足の速いAさん。Aさんは愛着に大きな課題を抱えているなと思われる子で、授業でも担任とのトラブルが多くありました。
ある時期、陸上の大会に向けて自分の種目である100m走の練習をしていました。一人で練習している姿はとても熱心で、一生懸命走りこんでいます。ところが、練習の途中でAさんよりも足の速い子が隣のコースで走り出した途端、Aさんは練習をやめて座り込んでしまいました。そしてそれ以上練習しようとしません。声をかけてみると「足が痛い」と言います。
足が痛くなる原因も特定できず、実際に痛そうな様子は見られませんでした。
結局Aさんはその後、走ることなく練習を終えてしまいました。
私はこうしたAさんを眺めていたのですが、その時、全く同じ光景を自分の記憶の中にも発見しました。
この連載の第3回でお伝えしたように、私自身、子どものころ、強い愛着の課題を抱えていました。ですから、私にもAさんと全く同じような経験があったのです。
6年生として陸上で100m走を練習していました。私は身長が高かったこともあり、足はそこそこ速かったのです。ところが自分よりも足の速い5年生がいて、その子が一緒に走り出した途端、私は走るのをやめてしまいました。その5年生に負ける自分が許せなかったし、負ける姿を見られるのが苦しかったのです。担当の先生から「どうした? どうして走らないの?」と声をかけてもらったのですが、私は何も答えずにその場から去りました。
それからもう二度と100m走には参加しませんでした。
その時の私の姿は、目の前のAさんの姿と重なります。ですから、Aさんの気持ちがよく分かります。「自分が駄目な人間だと思われたくない」「自分は凄いのだという気持ちに浸りたい」……。そうした気持ちを打ち壊されるのはつらく、不安で仕方がないのです。
そうした気持ちが原因で、課外活動や学校行事の中で不適切な行動をとったり、その場から逃げ出したりしてしまう子どもには、自分のよさを感じにくく、心の奥には上記のような「不安」が隠されているのだと考えられます。
また、特別活動には、様々な場面で「自分で判断する」「自分で行動を決める」という自己選択が求められます。愛着に課題を抱える子どもたちには、「自分で何をするのか決める」「誰とするのかを決める」ことを避けたり、嫌がったりする姿がよく見られます。こうした姿の裏にも同じように、不安が隠れています。「自分で決めたことに責任をもちたくない」「自分のせいにされたくない」「みんなと同じようにできない」「失敗したら苦しくなる」という気持ちから、自己判断を避けているのです。
「それでも」と無理に判断させ、行動させようとすると、怒り出したり逃げ出したりします。その苦しみの表し方は様々ですが、どの子も心の奥底に「不安」を抱えていて、特別活動の場面ではとくに不適切な行動が出やすいのだと考えられます。
2 特別活動を通して子どもが伸びていくアプローチ

坂内智之プロフィール
ばんない・ともゆき。1968年福島県生まれ。 東京学芸大学教育学部卒業。福島県公立小学校教諭。協働学習の授業実践家で「学びの共同体」から『学び合い』の授業を経て、20年以上にわたり、協働学習の授業実践を続ける。近年では「てつがく」を取り入れた授業実践を行う。 共著に『子どもの書く力が飛躍的に伸びる!学びのカリキュラム・マネジメント』(学事出版)、『放射線になんか、まけないぞ!』(太郞次郎社エディタス)がある。

