【昭和100年記念リレー連載】昭和世代の教師として、20~30代の教師に伝えたいこと ♯5 藤原友和 ~生成AIを携え、まちに出よう。
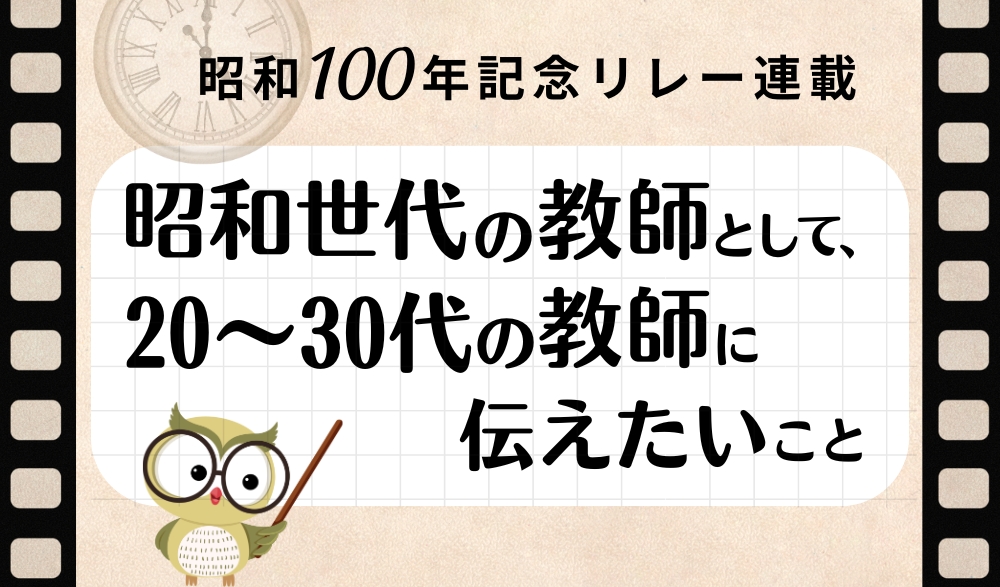
今年は昭和100年。 昭和100年を記念して、昭和世代の、昭和世代による、令和時代に向けてのセミナー(2025年8月9日~10日)を開催することになりました。ついては、登壇者たちから現在教職に就く皆さんへのメッセージとして、リレー連載を行うことになりました。 昭和世代の熱い想いをお読みいただければと思います。第5回は北海道函館市の気鋭の実践者、藤原友和先生によるご寄稿です。
編集委員/堀 裕嗣(北海道公立中学校教諭)
目次
はじめに
みなさん、こんにちは。
函館の藤原友和です。小学館の「せんせいゼミナール」や「オンライン授業をオンラインで学ぶ会」等のセミナー企画で覚えのある方もいらっしゃるかもしれません。縁あって仲間と共に学び合う場に携わらせていただきながら仕事を続けています。経験年数は小学校・中学校の教員として25年を過ごしたところです。
本リレー連載では、昭和世代教師から20代・30代の先生方にメッセージをお届けするという趣旨のもとにベテランの先生方が御論考を寄せられています。その末席に加えて頂いたことを大変名誉に感じるとともに、私でいいんだろうかと恐縮する気持ちも小さくはありません。
とはいえ、いつの間にか若者ではなくなっていた自分です。過ぎていった時間の分だけやってきたことの意味もなんとなく言葉にしやすくなったような気もします。本稿ではここ数年の間、一生懸命に取り組んでいる地域教材の開発についてお伝えしようと思います。よろしくお付き合いください。
1 まちに出る
地域教材の開発に関わり、私の中では「2014年」という年が、大きなターニング・ポイントになりました。
読者の皆さんは、その頃、どこにいて、何をしていたでしょうか。どんなことがあったか覚えていますか? 試しにGoogleで検索してみますと、国内では「集団的自衛権の容認」「衆院選で自民党が圧勝」「消費税率の10%への引き上げ延期」がニュースになっていました。御獄山の噴火や広島県における土石流の発生など、自然災害に襲われた年でもありました。国外に目を転じると、「ウクライナ危機」や「イスラム国の勢力拡大」など、不穏なニュースが世界を駆け巡った年でもありました。
そしてこの年は、岩手県知事を経て総務大臣を経験した増田寛也氏による『地方消滅 東京一極集中が招く人口急減』(中公新書)が刊行された年でもあります。「このままでは、896の自治体が消滅しかねない」とする増田氏の提言は大きなショックをもって迎えられ、人口減少社会の厳しさを否応なく突きつけられる「事件」であると感じられたものです。
人口減少による税収の減額、それに伴う行政サービスの縮小・撤廃が現実のものとして迫ってくる危機感は「消滅可能性がある」と判定された自治体にあっては強烈であり、私の身近なところでも、人口減少社会におけるまちづくりがテーマとなったイベントが盛んに開かれるようになったのも、この頃からではなかったかと思います。
それまでの私は、学校教育や授業づくりに関係するセミナーや学習会にはよく出かけていたものですが、正直に言うとまちづくり関連のイベントやサークル活動にはそれほど興味をもっていたわけではありません。
しかし、話合いを円滑に進める技法である「ファシリテーション・グラフィック」の実践をまとめた自著を刊行してしばらく経った頃から新聞やテレビの取材を受けるようになり、様々な団体からの仕事依頼が届くようになりました。
例えば「道南摂食嚥下研修会」という、医療と福祉の間をつなぐ、医者、看護師、地域包括ケアマネージャー、介護士の集う研修会でグラフィック・レコーディングの仕事をしたり、とある病院のスタッフによるチームビルディング研修を担当したりということがあり、教員以外の方とのネットワークが広がりました。
こういった場からつながったご縁で、大学や行政機関が開催するワークショップ、そして現在も籍を置いている「はこだて国際科学祭」に参画するようになっていきます。こうした動きを私がするようになった原動力になっているのが、この危機感です。
「函館に人がいなくなり、空き家ばかりになって、100万ドルの夜景も輝きを失ってしまう」
それは嫌だな、という思いから、自分にも何かできることはないかと考え行動したのが「まちに出る」ようになったきっかけでした。

