「読書推せん文コンクール」学校参加の具体的メリットとは?【PR】
全国の小中学生が参加できる「お気に入りの一冊をあなたへ 読書推せん文コンクール」は、今年で5回目。子どもたちに読書の楽しさ、自分の思いを言葉で表現することのよさを伝えるコンクールであり、子ども理解にもつながる取組として現場の先生方からも好評です。では、学校側からの人気の理由はどんなところにあるのでしょうか? 前回、前々回に続き、主催団体・博報堂教育財団の常務理事にお話を伺いました。
あわせて読みたい「読書推せん文コンクール」関連記事:
前々回:https://kyoiku.sho.jp/373797/
前回:https://kyoiku.sho.jp/373842/
提供/博報堂教育財団
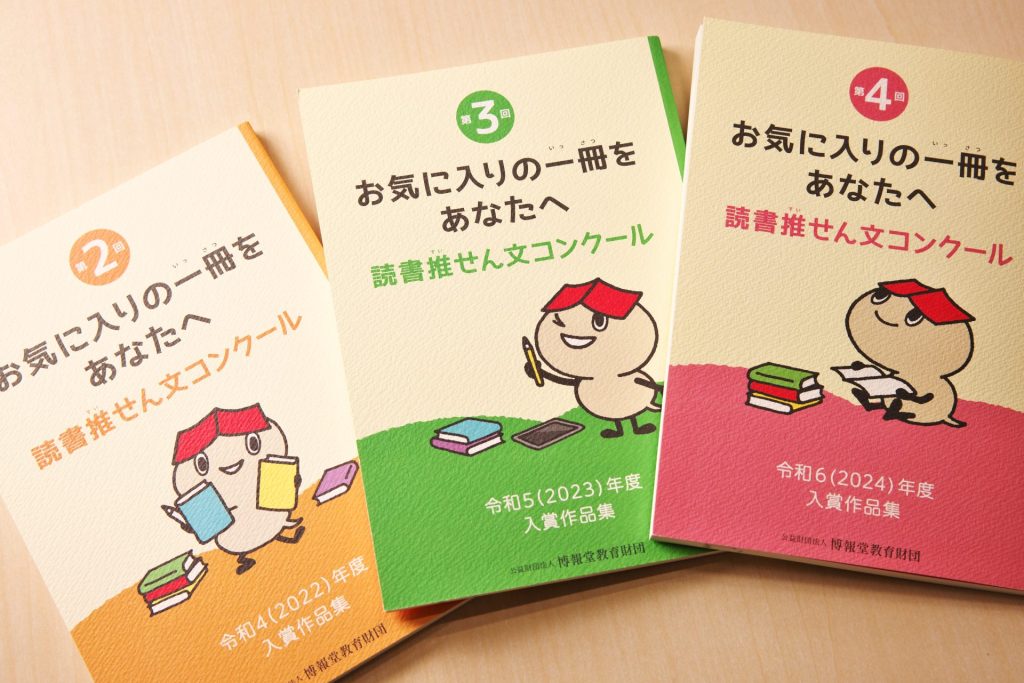

お話を伺った人:公益財団法人 博報堂教育財団
常務理事 中馬淳さん
1985年博報堂入社。PR局、研究開発局、経営企画局、人材開発戦略局長を経て、2021年より現職。博報堂では企業内大学である「博報堂大学」の運営など、人材開発を牽引してきた。「読書推せん文コンクール」では選考委員も務める。
目次
子どもの発達段階や隠れた一面、時代背景が作品を通して伝わる

――「お気に入りの一冊をあなたへ 読書推せん文コンクール」では、カテゴリが小1〜小3、小4〜小6、中学生、と3つに分かれています。それぞれ、読んでいてどんなことをお感じになられますか?
やはり、それぞれの発達段階による特徴は感じます。小1〜小3は、素直な気持ちが真正面に出てくる作品が多いので、読んでいて大変温かい気持ちになりますし、中学生くらいになると自分の中の葛藤や人生への悩みなど、シリアスな内面が出てきて、読みながら私もハッとさせられます。
また、その年の時代背景も大きく影響します。以前はカラッとした作品が多かったのですが、前回は戦争や震災に関わる重いテーマも多く、読みながら、子どもたちの今の感情やムードのようなものをリアルに感じられます。そのあたりは、学校の先生ならば、さらに指導の学びにつながったり、参考にしていただけることも多いのではないでしょうか。

団体でご参加いただいた学校からのアンケートのコメントでは、「自分の気持ちを文字にするという機会が減っている中、子どもにとっても有意義な体験である」「教師としては、その子どもがどんな本を選んでどんなことを書くのか、という点で、普段見られない一面を知られるよい機会にもなる」などというご意見を多数いただいております。
また小規模学校からのご応募も多く、そういった学校からは、「学校外に活動を発信する機会が少ないので、このようなコンクールを利用できるのはうれしい」という声もいただいており、私たちも大変ありがたく思っています。文字数も250〜300字と少なめなことと、本のジャンルを限定していないことで、読書に苦手意識のある子どもや低学年の子どもにもアプローチしやすいという利点もあるようです。 私も、選考委員の一人として、推薦文を読みながら興味が湧いた本を実際に取り寄せて読ませていただいているのですが、普段自分が読まない本にも触れることができて、毎年とても楽しみにしております。
「読書推せん文コンクール」2024年度(第4回)の入賞作のまとめページはこちら
https://www.hakuhodofoundation.or.jp/okiniiri/winners/
参加学校の取り組み例〜授業や読書活動につなげる学校も〜
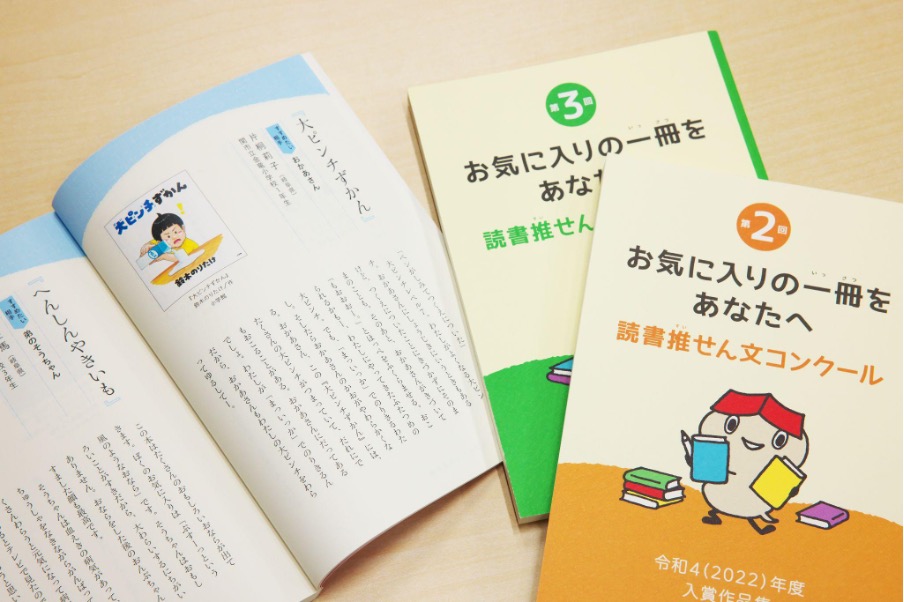
――コンクールに団体で参加されている学校では、このコンクールを様々な取り組みにつなげられている例もあるようですが、実際にどんな実例がありますか?
それは、非常に興味深いアプローチがたくさんあるようです。このコンクールを活用しながら子どもたちに手紙の書き方を教えたり、学校図書館の活用促進につなげたりしている学校もあります。面白いと思ったのは、推薦文を書いたあとに、学校図書館にある本に帯を作るという取り組みをされた学校です。確かに、先生や親など大人から薦められるよりも、子ども同士からのお薦めのほうが響きそうですよね。
ビブリオバトルで、本を選んで対決型で推薦するという実践に繋げている学校もありますし、また、子どもだけでなく先生、そして校務員さんまで学校全員でお薦めの本を紹介するという取り組みをされたという話も聞きます。
本当にいろいろなアプローチがあるようで、毎年コンクールで団体賞をとられるような学校は、やはり読書活動に対して多角的な取り組みをされていることが多いようですね。
他にも、参加された学校からの声がこちらにまとまっていますので、ご覧ください。
参加校からの声はこちら
https://www.hakuhodofoundation.or.jp/okiniiri/voice/
学校で「読書推せん文コンクール」に参加する6つのメリットまとめ
- 1 子どもへの読書をする機会の提供
- 2 自分の気持ちを言葉にする力の育成
- 3 参加ハードルが低く全校で参加できる(250〜300字と字数が少なめ・本の選定が自由)
- 4 一人ひとりの子ども理解が深まる
- 5 授業や学校図書館の活性化など、様々な取り組みにつなげられる
- 6 対外的な発信機会となる
これから応募される方へのメッセージ
――最後に、学校の先生に一言お願いいたします。
あくまで本に親しむという目的であり、誰でもチャレンジできる気軽で自由なコンクールです。ぜひみなさんでご参加ください。文章のスキルよりも、自分の素直な気持ちを言葉で伝えるということを大切にしていますから、先生には、適切なご指導はいただきつつも、ぜひ過剰な介入はせずに(笑)、子どもの自由な発想に任せていただければと思います。多少荒削りでも大丈夫。のびのびとした作品をお待ちしております。

以上、今回は「読書推せん文コンクール」を学校教育に活用する具体的事例とアイデアについて、主催団体である博報堂教育財団の中馬常務理事にお話を伺いました。一人ひとりの子どもをより深く理解できたり、学校の様々な取り組みにもつなげられたりする魅力いっぱいの「読書推せんコンクール」。結果よりも参加することに意義のあるコンクールだと感じます。先生も子どもも、このコンクールに参加して、楽しみながら自分の好きな本を誰かに紹介してみてはいかがでしょうか。
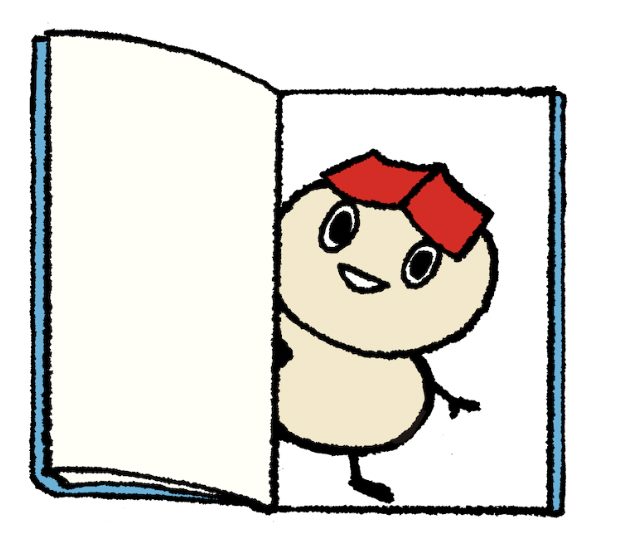
皆さんからのご応募を楽しみに待っているよ!
――コンクールキャラクター:もちぽん
コンクールの詳細情報は公式サイトでご確認ください
↓↓↓
リンク先:https://www.hakuhodofoundation.or.jp/okiniiri/#top
取材・文/田口まさ美(Starflower inc.)

