小3特別活動「スッキリそうじ~みんなのためにきれいに~」指導アイデア

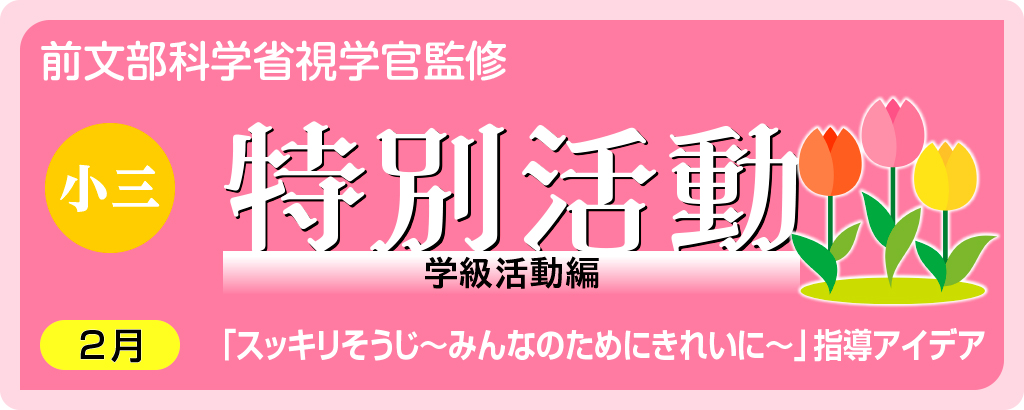
前文部科学省視学官監修による、小3特別活動の指導アイデアです。2月は、学級活動(3)イ「スッキリそうじ~みんなのためにきれいに~」の実践を紹介します。友達と力を合わせて清掃し、自分のためだけではなく学級のために働くことのよさを学びます。学級や学校のみんなが気持ちよく過ごすことができるようにするための清掃の方法や工夫を考え、一人一人がよりよく意思決定できることをめざします。
執筆/神奈川県川崎市立小学校教諭・筒井俊
監修/帝京大学教育学部教授(前文部科学省視学官)・安部恭子
日本体育大学教授・橋谷由紀
目次
年間執筆計画
4月 学級活動(3) ア 3年生になって
5月 学級活動(1) 係を決めよう
6月 学級活動(2) ウ ぼうさいマスターになろう
7月 学級活動(1) なかよし集会をしよう
9月 学級活動(3) ウ 家庭学習パワーアップ大作せん
10月 学級活動(1) 係活動発表会をしよう
11月 学級活動(1) クラス運動会をしよう
12月 学級活動(1) がんばったね集会をしよう
1月 学級活動(2) エ よくかんで食べることの大切さ
2月 学級活動(3) イ スッキリそうじ~みんなのためにきれいに~
3月 学級活動(1) ありがとう集会をしよう
学級活動(3)イの指導について
学級活動(3)「イ 社会参画意識の醸成や働くことの意義の理解」は、学校や学級のために力を合わせて働くことの意義を理解し、工夫しながら自己の役割を果たすことができるようにすることなどを通して、社会の一員として、責任をもって主体的に行動しようとする態度を養うことを内容としています。
子供たちが働くことの意義を理解することや、力を合わせて働いたり、学級や学校の生活の向上に貢献したりする喜びを実感することができるように、学校での話合いを生かして自分に合った目標を立てられるようにしましょう。
扱う題材によって、学級活動(2)ア「基本的な生活習慣の形成」と混同してしまうことが考えられます。しかし、学級活動(2) ア「基本的な生活習慣の形成」は、生活習慣や節度ある生活の大切さを理解することを内容として扱っています。「掃除の上手な仕方」についての指導などは、上記に示した学級活動(3)イ「社会参画意識の醸成や働くことの意義の理解」の内容とは異なるため、注意しましょう。

