【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第66回】今どき教育事情・腑に落ちないあれこれ(その7) ─閑話休題 「否定の生産性」の復権─

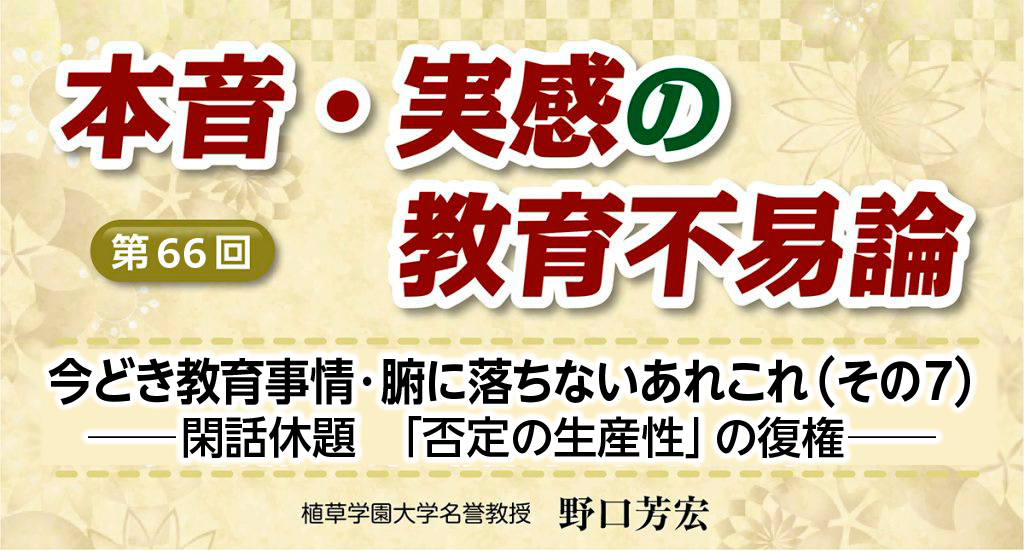
国語の授業名人として著名な野口芳宏先生が、60年以上にわたる実践の蓄積に基づき、不易の教育論を多様なテーマで綴る好評連載。今回のテーマは、【今どき教育事情・腑に落ちないあれこれ(その7)─閑話休題 「否定の生産性」の復権─】です。
執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。

目次
12、閑話休題(承前稿)
「否定の生産性」についてもう少し書いておきたい。重要な問題、看過すべきではない、と思うからだ。そもそも「教育」というもの、教育という営為は誤りや過ち、短所や欠点、利己的で自分本位、暴力や妨害、欺瞞や甘言などのマイナスの要素や現象を否定、破砕し、善なる方に導くこと、古い言葉だが「勧善懲悪」を本質とするものである。むろん、生まれ乍らに備わった善の芽は伸ばし育てつつであり、そのことは改めて申すべくもない。
さて、自分の持っているマイナスの要素、という改めるべき点については、残念なことに「無自覚」であることが多い。自分のマイナス要素には気付かず、見えにくいものなのだ。
あるいは、自分で分かっていても、それを改め、善に向かわせるということについては、人は一般に消極的である。「一般に」であって、そうでない人もある。そういう子供、そういう人が伸びるのである。そういう人を多くするのが教育なのだ。
悪気はなくとも、その性向をそのままにしておくことは拙い。ここでそのマイナスに気付かせ、改めさせる方がその子の今後のためになる、と大人の教師の眼には映るということはよくある。そういう場合には、指摘したり、注意したりして「気付かせ、改めさせる」ことが肝要である。そういう教師が良い教師なのである。また、そういう教師の働きかけに対して、子供がそれを受け入れ、成程と気付き、先生の助言、導きに従うのが子供の成長なのである。そういう子供を昔は「素直な子供」「素直な心」という言葉で呼んでいた。全く以て明快、爽快である。
ところが、である。このような善意の働きかけに対して、この頃は教師の側にためらいが生まれている。次のような風潮に依る。
ア、ありのまま、今のままでいい。
イ、それぞれの生き方、考え方を大事にしたい。個性を大切に。
ウ、外からの指示や命令は努めて控え、本人の考え方を大切に。
エ、十把一からげの見方は良くない。多様性に対して寛容に。
オ、子供一人ひとりの人権は尊重されなければならない。
このようなことを言われると、つい「指導」の気持ちが萎えてくる。こんな妄言に惑わされることなく、敢然と正対する教師でありたいのだが、別の事情も加わってくる。
一つはモンスターペアレンツである。そんなのに関わったら面倒この上ない。もう一つは、上司、管理職、教委にも脅えと保身と無難の傾向があって、なるべく「事勿れ」という思いが強い(ようである)。そうなると、部下職員の腰が引けるのは当然、とも言える。
かくて、「否定の生産性」の大切さは頭では分かるものの、心の納得という所まではいかない。まあ「言わずにおくか」ということになりがちだ。
「いじめ」が、大きな問題になって30年は経つ。「不登校」然り。「引きこもり」の発生は少し新しいが、かなりの時間が経過している。 現在の学校は、校門を閉ざしてひっそりとしている(ように見える)。若者も、そんなことを察知したのだろうか、「教員志願者」が急激な減少を見せ、採用試験の競争率が、ほぼ1倍強、つまり応募すればほぼ全員合格という所まで下がった地方もあるらしい。
新採用者の減少も問題だが、その日、その日の学校の運営が立ち行かぬほどの教員不足が常態化しているようだ。教頭も、校長も教室に出向いて子供の授業に当たっているという話も珍しくもない状態と聞く。これは一つの非常事態だ。これらの事態を、どのように受け止めるべきか。
13、教育界昏迷の最高責任は
非常事態という言葉を荒唐無稽の戯言と一笑に付すことができるか。この頃密かに思うことがある。
恐らく、時代や空間を超えて言えるのではないかと私は思うのだが、教育者を目指し、教員になるような人は、ほぼ善良、勤勉、誠実、真面目、従順という資質、性格を有する善人だと私は考えている。だから、校長や、教育委員会や文科省の示す方針や施策に対しては大方従順に従って日々を過ごしていると言える。
更に言うなら「働き過ぎる」ほどに職務に精励しているのが実情ではないか。その故にこそ「働き方改革」などの施策をとらざるを得ないのであろう。
「もっと働け」「もっと職務に励め」などと言われれば、教員は身体を壊すか、心を壊すかという事態に追い込まれるしかあるまい。現に、そういう教師が少しずつだが増えているようである。それほどに日本の教師は誠実に働いているのに、子供の現実、教育の現実、あるいは成果、評価は残念ながら高くはない。
──とすれば、これは「このようにすべきだ」「このようにせよ」「こうすればもっとよくなる」と言って指示し、指令し、リードしているそのトップの機構、機関の指示、指令のどこかに、何か大きな欠陥、欠落、勘違い、誤認があるのではないか。そうは思いたくない。そんなことはない。──という思いもあるのだが、戦後も78年になるという長期間に亘る教育の成果はどうも思わしくない。
上部機関の指示や指令に、誠実に従いながら「働き方改革」を指示されるほどに働いてきたのに、その戦果が「非常事態」ということになれば、指示、指令の戦略、戦術のどこかに非があったのではないかと考えるのは道理ではないのか。──そう思いたくはないのだが、私の考えは間違いなのだろうか。大方の批判を期待している。
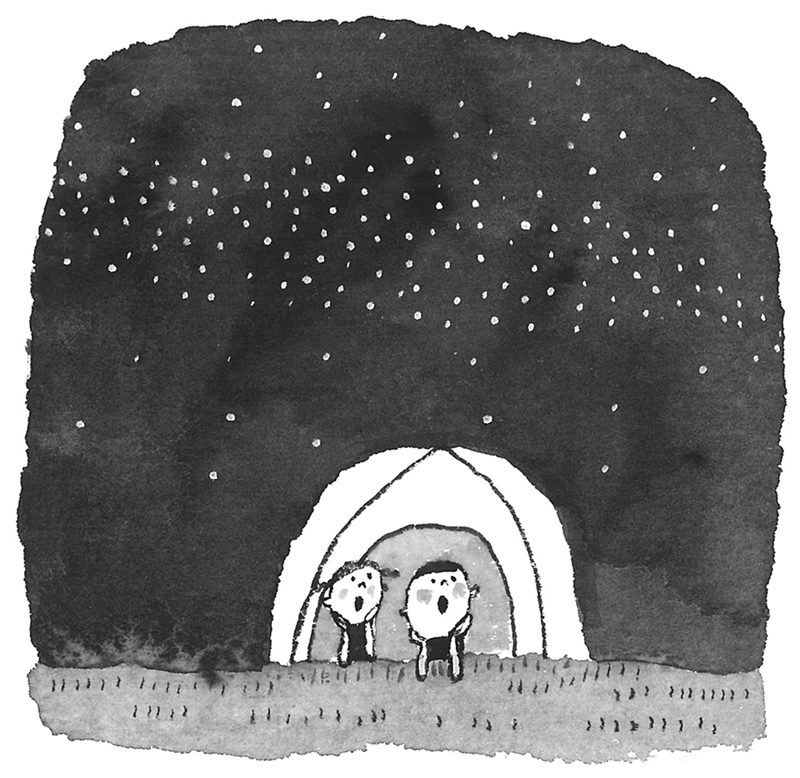
14、「教学聖旨」今こそ再び
明治12年(一八七九)に「教学聖旨」という文書が、明治天皇の名で政府要人に示された。この文書は「五箇条の御誓文」が国民の間に望ましく行き渡っているかを明治天皇が巡幸、視察されて成ったものだ。実状は、御誓文の趣旨通りに進行していないのみか、誤解や過大解釈によって欧化の真似事が進み、日本本来の美徳が損なわれる気配さえあると憂慮された由である。日本の美徳への復帰を望み元田永孚(もとだながざね)に原案を起草させ、吟味の末に公にした文書が明治天皇の「教学聖旨」である。
この後段の「小学条目二件」の一に次の文言がある。
「仁義忠孝の心は人皆之れ有り。然れども其れ幼少の始に其の脳髄に感覚せしめて培養するに非ざれば、他の物事すでに耳に入り先入主となる時は、後にいかんとも為す可からず。故に、当世小学校(以下略)」
ここには、国家としての国民教育の原点を「仁義忠孝」と明示し、幼少の頃から「脳髄に感覚せしめて培養するに非ざれば」と強く当時の教育事象を戒めている。
一国の君主としての堂々たる宣言である。──そういう全体主義がいけないのだ。それが日本の不幸を招く遠因となったのだ、という考え方もある。承知している。だが当時の政府要人は明治天皇の憂慮を重く受け止め、教育の改革に立ち上がり、教育はかなり正された。
「教学聖旨」を読むと、日本の現今の教育界の昏迷と酷似しているように思われる。当時も、今も、教育界の「非常事態」としては軌を一にする事態ではないか。
大きく違うのは、明治天皇と元田永孚クラスの傑物、偉人が不在という一点だ。
賞味期限が十年と限られた指導要領の小手先いじりのめまぐるしい改訂に振り回され、国家百年の大計という骨太の国是が見えない。改正によってかなり良くなった教育基本法も、具体的に子供が学ぶ教科書にその精神が具現されているかと言えば心許ない。「教学聖旨」は明確に「仁義忠孝」と教育の原点を示した。
これが、諸徳を統べる「元徳」であり「主徳」である。
仁義忠孝に替わる令和時代の元徳、主徳は依然として不透明、不明であり、「人格の完成」という抽象語で示されている。当たり障りのない玉虫色の観念語彙である。「これで行こう」「これなら間違いない」という具体的な理念の共有を持たない一億総根無し草の平和日本ではある。
15、教育正常化の困難
「否定の生産性」という「子供をより良く導く為に、子供の中にあるマイナスに気付かせ、善導しよう」とのごくごく当たり前の考えが言い辛い教育界への「腑に落ちない」思いから述べ始めたのだが、話題を広げ過ぎたかもしれない。
私が述べた事態が、おいそれと簡単に解消されるとはむろんのこと思ってはいない。その最も大きな要因は日本の敗戦である。その敗戦につけこんで「二度と再び、日本という国家が、米国に逆らったり、世界を恐怖に陥れたりすることのないように」と目論んで進めたGHQの巧妙かつ入念な占領政策もある。壮大な、日本人の洗脳政策は、美事な大成功を収めたものだと、私は舌を巻く思いだ。
その洗脳状態から脱しようと立ち上がったのが「戦後レジームからの脱却」を旗印にした安倍晋三総理だった。教育基本法の改正はその一次内閣の折の成果である。不慮の暗殺によって兇弾に倒れたことが本当に無念、残念である。
このように書いてくると、右翼的だ、右翼だ、などと思う向きもあろうかと思うが、私は中立、中庸を以て自認している。左端に立てば全ては右に見える。右端に立てば全ては左に見える。中央に立てば右も左も見える。中央、中庸は最も公平、公正、無偏である。
ここのところ耳にした教育現場の新しい動きがある。「とにかく叱るな。叱ったら負けだ」ということだ。◯◯ハラスメントが大はやりで、担任が子供の悪さを見かねて大きな声で叱るとパワーハラスメントになるというのである。
明らかに、事の起こりは子供にあるので注意し、制止するのだが教師が優しいのにつけこんだ子供は言うことを聞かない。堪りかねて大きな声で叱るとパワハラになるというのである。
ここには二つの問題がある。一つは子供が教師を舐めていることだ。師弟関係の崩壊である。友達の一人くらいにしか思っていないから言うことを聞かないのである。
「怖いもの知らず」という慣用句があるが「怖い存在がある」ということは人間としての一つの教養である。「恐れ入ります」「畏まりました」などは、恐れ、あるいは畏れを知る人にして言える言葉だ。恐れ、畏れの前に慎むのは人としての教養であり、先生を先生とも思わないのは無教養である。
もう一つは、子供が「従わない」「受け入れない」ということだ。これは、自分中心、利己的態度であって傲慢にも通ずる。私が子供の頃は、式典の席上、来賓の祝辞はほとんどが、「親の言うことや先生の言うことには従いなさい。そういう素直な子になりなさい」と言うのが常だった。目上や大人の言葉に素直に従うのが良い子であった。昔の子供は多く「素直」であったが、今の子供は「自ら考え、自ら判断する」「主体性、自主性、個性を大事にしよう」と言うのだから、教師も教え辛くなっている。
どこかがおかしい。どこかで狂ってしまった、としか考えようがない。大人の「子供観」が、子供を持ち上げ、奉っているようにさえ思える。子供でなく「こども」と書くのが望ましい、と「こども家庭庁」が言い出している。「こどもまんなか社会」などとも言っている。「子供の本質は、無知、未熟」と言っている私は風下に立つしかないか。
執筆/野口芳宏 イラスト/すがわらけいこ

