<連載> 菊池省三の「コミュニケーション力が育つ年間指導」~3学級での実践レポート~ #5 千葉県船橋市立田喜野井小学校5年1組①<前編>

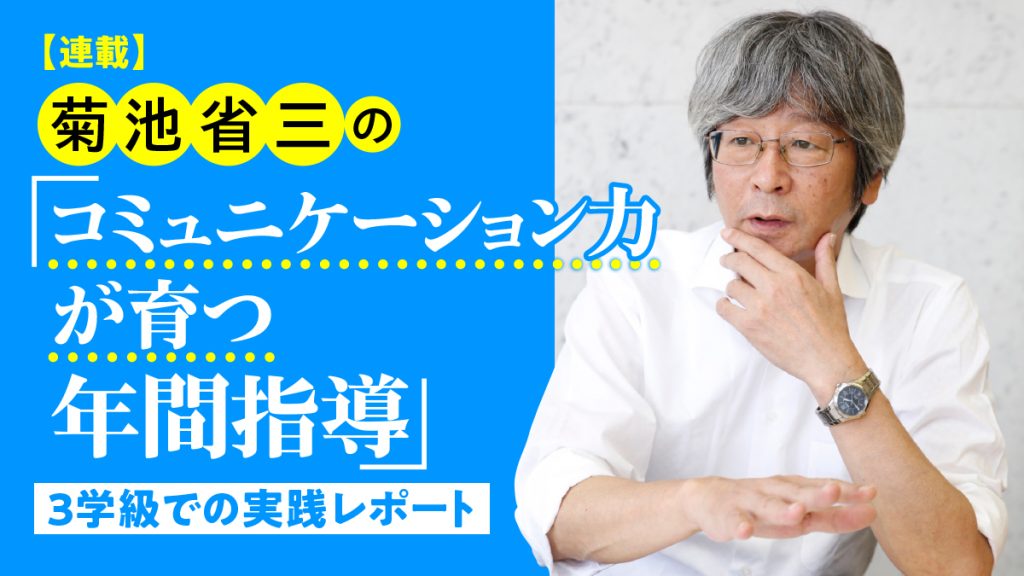
菊池実践を追試している3つの学級の授業と子供たちの成長を、年間を通じてレポートします。3学級の担任は、徳島の堀井悠平先生、高知の小笠原由衣先生、千葉の植本京介先生。それぞれの学級をローテーションでレポートしていきます。今回からは、千葉の植本学級(5年生)における、6月下旬の授業レポートです。

目次
担任・植本京介先生より、学級の現状報告
3月末に、「エネルギーがあり、素直でかわいい。行事もがんばる。でも勉強は二の次で衝動的に行動してしまう」と、前学年の先生方から引き継ぎを受けました。授業中に教室を飛び出したり、友達とトラブルを起こしたり。そのため、“きつめ”の指導も多かったようで、なかなか大変な学年だと聞いていました。
しかし、始業式で子供たちと顔を合わせると、どの子も「担任とつながりたい」と強く思っているように感じました。
そこで、始業式の日に「昨年度までのことを先生はよく知りませんが、問いません。今日からがんばりましょう」と“リセット”することを話すと、子供たちには響いたようです。みんな「変わりたい」と思っていたのです。
私は、一年後のゴールイメージとして、<自己開示をし合い、個性を発揮しながら、お互いを高め合う学級>を目指すことにしてスタートしました。
自分をアピールして一方的に話すだけでなく、友達の意見を聞き合い、納得するまで考えることの価値を丁寧に伝えていきました。
元気いっぱいの子供が教室を引っ張っていましたが、中には、不規則発言はしても、いざ表に出されると尻込みしてしまう “積極的だけど無責任な子” も少なくありませんでした。その子たちに “責任感はあるが消極的な子たち” が圧倒されていました。
また、「授業中は黙って座ってさえいればいい」と諦めている“無責任で消極的な子”も気になりました。そこで、自由な立ち歩きで意見を交わす活動を多く取り入れ、いろいろな友達とかかわるようにしていきました。
4月下旬に、菊池先生のオープンエンドの“納得解”の授業を受け、子供たちは「自分が何を言っても受け止めてもらえる」「相手と話し合うことは気持ちが高まる」ということを実感し、その後、話し合いの授業を楽しみにするようになりました。
一方、相手の話は聞いていても、「相手は相手」で止まってしまい、人の意見から自分の意見を高めるところまではなかなか意識が向かない子もいました。「聞く必要性のある授業」「聞き合うから楽しいと思う活動」をしていかなければ、と感じました。
そこで、意見を「かみ合わせる」授業を意識し、国語科や社会科などで、話し合いを多く取り入れ、総合的な学習の時間ではマイクロディベートにも取り組みました。
学級活動でも、会社活動(係活動)やほめ言葉のシャワーを通して、子供同士が徐々につながるようになってきました。
内容的に難しいと感じると、他人任せで “お客さん” になってしまう子たちもいる中、話し合い活動をどう展開していけば全員参加になるか、これからも意識していきたいと思っています。
菊池先生による飛び込み授業レポート
「2時間目の植本先生の授業を見せてもらいました。(それについて)黒板の左端にすぐに書きたい。授業のスピードを上げたいので、大きな拍手で後押ししてもらっていいですか?」
菊池先生が、教室の外から話しかけると、子供たちが指の骨が折れるほど大きな拍手で迎えた。
<話し合い力=学○力>
菊池先生が、○に入る文字をゆっくりと綴っていくと、「ああーっ!」「わかったー!」と子供たち。
<学級力>
「やっぱりー!!」
「4月より、学級力が上がっていますね。隣の人と『私たち上がっているよね』と言い合いましょう」
笑顔で言い合う子供たちに、菊池先生が、
「今日は(学級力を)もっと上げていく授業にしたいと思います」
と話すと、みんなが笑顔になった。
![]()
積極的に発言する男子がみんなを引っ張っている様子が感じられたので、「学級全体で頑張るんだよ」とエールを込めて、黒板の左端に、最初に書き込みました。
初期の頃、一部の子が中心になって学級を引っ張っていくのは当然と言えば当然ですが、今後、少しずつ学級全体を意識して学級力を高めていかなければ、白熱した話し合いの授業は成立しません。
2時間目の植本先生の授業を参観したとき、4月に授業したときと比べ、発言している子が増えたものの、まだ一部の子に留まっていたので、布石として挙げました。
「2時間目で勉強した国語の教科書に、イソップ童話の話が出ていましたね。何ていう話だったか、覚えていて言える人?」
菊池先生の問いかけに半数が手を挙げた。すると、菊池先生が廊下側後方の男子のところに行き、握手をしながら、
「図書委員会で彼が頑張っていると思う人は、大きな拍手を送りましょう」
と声をかけると、みんなが拍手を送った。
![]()
4月下旬、1回目の授業に入ったとき、この男子は「体調が悪い」と机に顔を伏せていました。植本先生から話を聞くと、中休みに行われた図書委員会の仕事に出席するのを忘れた、とのことでした。担当の先生に叱られることを恐れ、体調が悪いことを理由に早退しようかどうか、迷いながら授業に参加していたそうです。
私の授業が始まり、最初の頃はチラチラ伏せた顔を上げていましたが、授業が進むにつれて顔を上げる頻度が増え、いつしかみんなと一緒に話し合いに参加していました。
今回の授業では、最初からしっかりと前を向いて参加していたので、あえて彼のところに行き、「頑張っているな」と認めるサインを送りました。
「『うそつき少年』です」
「そうですね。4月の授業で私がとりあげた『きつねとつる』もイソップ童話でした。今日はパート2です」
と、菊池先生が『金のおの、銀のおの』とタイトルが書かれた一枚の絵を見せると、みんなが、
「ああーっ」と声を上げた。
「近くの人と7秒ほど、どんな物語か話しましょう」
7秒後、
「ほんのちょっとでも言える人?」
と菊池先生が尋ねると、半数以上が手を挙げ、縦列の5人が発表した。
●鉄の斧を落として、女の人に「金の斧か、銀の斧か」と言われて、「鉄の斧だ」と言った
●鉄の斧で木を切っていたら川に落として、「銀の斧か、金の斧か、鉄の斧か」と聞かれて、「鉄の斧」と言ったら、金の斧もくれた
●鉄の斧を川に落としたら、中から人が出てきて、「あなたが落としたのは、金の斧か、銀の斧か、鉄の斧か」と聞かれて、「鉄の斧」と言ったら、全部くれた
●木を切っていたら、川に落とした。川から女の人が出てきて、「金の斧か、銀の斧か」と聞いたので「鉄の斧」と答えたら、「あなたは正直者ですね」と全部くれた
●木こりが木を切っていたら、斧を落とした。そうしたら、川から神様みたいな人が出てきて「あなたの落としたのは、金の斧ですか? 銀の斧ですか? それとも鉄の斧ですか?」と聞いたので、「鉄の斧です」と答えたら、「あなたは正直者ですね。じゃあ全部あげましょう」とくれた
子供たちは少しでも前の発表と異なる表現をしようと意識しながら発表した。
菊池先生が黒板に書いた<学級力>を指しながら、
「そうですね。今の話をもとに、これを上げていきたいと思います」
と話すと、子供たちが期待でいっぱいの表情になった。
木こりが木を切っていたら、沼の中に斧を落としてしまった。
女神が出てきて、「金の斧ですか?」と尋ねると、木こりが「違います」。
「それでは、この斧ですか?」と銀の斧を見せると、「いえ、違います」。「ではこれですか?」と鉄の斧を見せると、木こりが「はい、そうです」と答えた。すると、女神が金と銀と鉄の斧全てを「どうぞ」と言って渡したので、木こりがもらった。
「これが、木こり1です。
木こり1はいい人だと思う人は○、よくないんじゃないかと思う人は×をつけましょう」
と菊池先生が問いかけると、子供たちはさっとノートに書いた。30人が○、1人だけ×をつけた。
すると、菊池先生が×をつけた男子と握手し、
「いいなあ。君は『よくない』と思ったから×をつけたんだね」
と話しかけると、男子がうなずいた。
まず、○を書いた人の中から、指名された縦列の4人が発表。
●金と銀の斧を欲しがらず、自分が落とした斧を言ったから、正直者でいい
●嘘をつかずに、正直に自分の斧を選んだから
●欲張らずに、自分の斧と言った
●正直に、自分の斧を言ったから
最後の男子が発表し終わると、菊池先生が傍に行き、いきなり、
「ちなみに4年連続ゴールデン・グラブ賞は誰?」
と、突然の無茶振り。<四年連続ゴールデングラブ賞>というロゴのTシャツを着ていた野球大好きなその男子が嬉しそうに、
「今宮(健太)選手です」
と速攻で答えると、聞いていたみんなも「すごい!」とにっこりした。
「…では、×だった君、どうぞ」
菊池先生が、たった1人×をつけた男子に振った。
●「鉄の斧だ」と正直に言ったのはみんなと同じだけれど、金と銀の斧をもらうのは違うと思った
男子の意見を聞いた何人かが、
「ああー」「なるほど」とうなずいた。
「深く考えていますね……ここで拍手だな」
と言うと、みんなが大きな拍手を送った。
![]()
たった1人でも自分の意見を堂々と発表した男子をほめ、全員で認める拍手を促しました。
彼の意見を聞いて、納得したようにうなずく子も大勢いました。いろいろな意見を聞くことは、新たな発見であり、自分自身の考えを深めることです。聞き合う=考え合うことを実感した場面です。

