「条件制御花壇」を活用して、植物の成長条件を調べよう!<5年生 植物の発芽と成長> 【理科の壺】

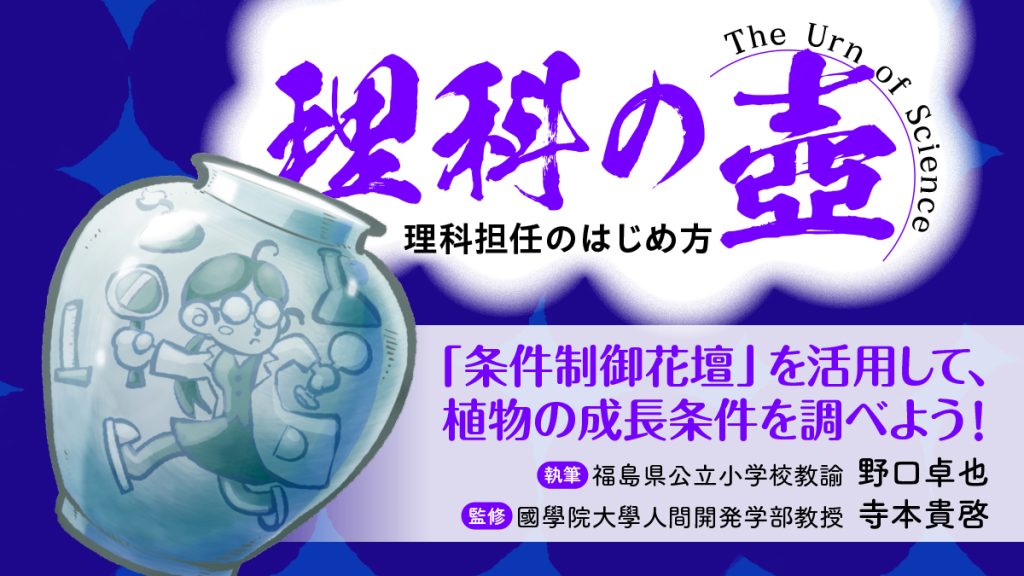
今回は、肥料の必要性を子どもに感じさせられなかった、という反省から生まれた実践についてご紹介します。5年生「植物の発芽と成長」において、インゲンマメには個体差があるため、「肥料なし」でも青々と大きく成長しているものもあれば、「肥料あり」で小ぶりなものもあったため、より分かりやすく条件制御の方法を改善するための取組です。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/福島県公立小学校教諭・野口卓也
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1.子どもは、植物の成長における「肥料」の必要性を実感できていますか?
春も終わり、夏に向けてまっしぐら! 発芽した植物たちも、ぐんぐんと成長している時期だと思います。5学年理科では「植物の発芽と成長」において、主にインゲンマメを用いて植物の発芽や成長の条件を解決していきます。ちょうど今頃は、ある程度大きくなってきて、プランターや花壇に植え替えて、成長条件について調べ始めているのではないでしょうか。
以前、わたしは5年生を担任して、インゲンマメを用いて植物の成長条件についての考察をしている際、「先生、肥料がなくてもインゲンマメは大きくなっているから、肥料はあってもなくてもいいんじゃないかな」というA君に出会いました。たしかに肥料がなくても、植物は成長します。A君に、「肥料があるとこんなに成長の仕方が違うんだ!」と感じさせることができなかった、わたしの授業に課題があるのだと思い、改善点を振り返ってみました。
すると、一番の原因は「インゲンマメの個体差」だったのではないかと考えました。つまり、植木鉢に一株ずつインゲンマメを植え替え、「肥料あり」と「肥料なし」に分けて実験をしていたのです。そうすることで、子どもは「肥料あり」と「肥料なし」の植木鉢を比較して結果を整理していくのですが、インゲンマメにも個体差があるため、「肥料なし」でも青々と大きく成長しているものもあれば、「肥料あり」で小ぶりなものもあったのです。
そのとき、わたしは「インゲンマメの個体差が気にならないように実験していくことが必要かもしれない」と考えるようになりました。
そこで、子どもからの「肥料ありと肥料なしの場所を作って、そこに植え替えて実験してみたい」という声に応え、子どもと共に条件制御花壇を整備して実験を始めました。インゲンマメを群生させて、個体差による影響を無視して実験できる「条件制御花壇」を製作したのです。
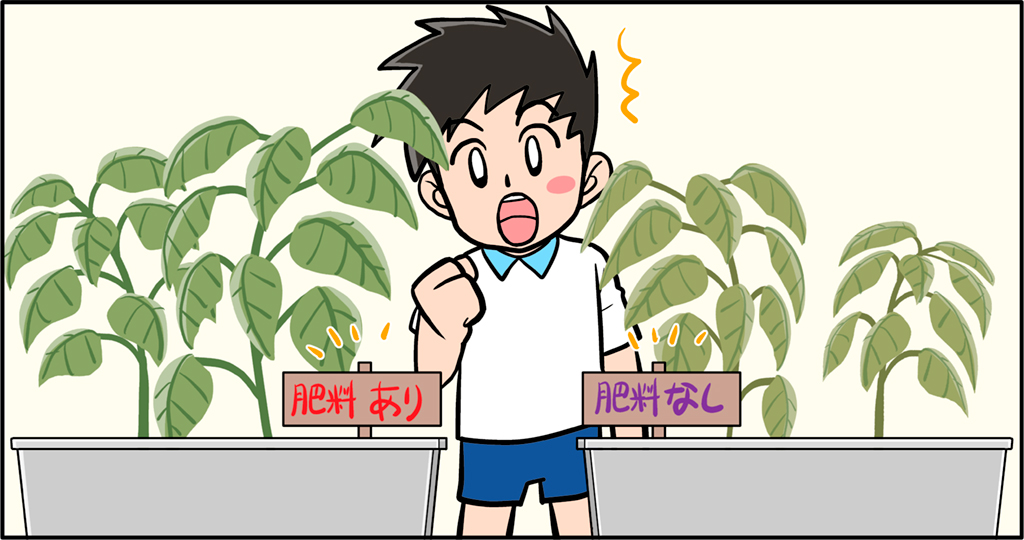
2.「条件制御花壇」を作ろう
条件制御花壇は、学校園の一区画を活用して製作できます。学校の実態に応じて、製作する花壇のサイズは変わりますが、小スペースでも効果を発揮します。製作に向けての準備物や手順は、次の通りです。
<準備物>
・レンガ(製作する規模に応じた個数)
・接着剤(レンガ用またはコンクリート用)
・培養土(製作する規模に応じた量)
・バーミキュライト(製作する規模に応じた量)
<製作手順>
① 製作する場所に、レンガを四角形になるように並べる。(この時、レンガを2個積んで並べると深さが出る)
② できた四角形が半分になるようにレンガを並べる。
③ 並べたレンガのつなぎ目に接着剤を流し、固定する。
④ 接着剤が乾いたら、培養土とバーミキュライトを8:2くらいの割合で混ぜて入れる。
⑤ 培養土側に肥料(化成肥料または牛糞など)を混ぜこむ。
子どもたちが種子から育てたインゲンマメの苗を植え替えると、右の写真のようになります。「条件制御花壇」は、子どもと共に製作しても、教師で環境づくりとして製作してもよいと思います。


