小5理科「動物のたん生(魚のたまご)」指導アイデア
文部科学省教科調査官の監修のもと、小5理科「動物のたん生(魚のたまご)」の板書例、教師の発問、想定される子どもの発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。
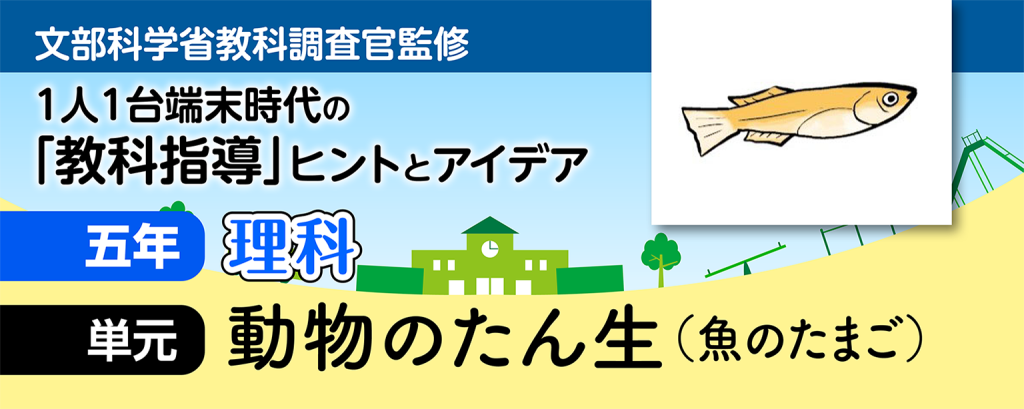
執筆/福岡県大野城市立下大利小学校教諭・水野麻江
監修/文部科学省教科調査官・有本淳
福岡県大野城市立月の浦小学校校長・清尾昌利
目次
単元目標
魚を育てる中で、たまごの様子に着目して、時間の経過と関係づけて動物の発生や成長を調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身につけるとともに、主に予想や仮説を基に、解決の方法を発想する力や生命を尊重する態度、主体的に問題解決しようとする態度を育成することがねらいとなります。
評価規準
知識・技能
①魚には雌雄があり、生まれたたまごは日がたつにつれて中の様子が変化してかえること。
②動物の発生や成長について、観察、実験などの目的に応じて、器具や機器などを選択し、正しく扱いながら調べ、それらの過程や得られた結果を適切に記録している。
思考・判断・表現
①動物の発生や成長について、予想や仮説を基に、解決の方法を発想し、表現するなどして問題解決している。
②動物の発生や成長について、観察、実験などから得られた結果を基に考察し、表現するなどして問題解決している。
主体的に学習に取り組む態度
①動物の発生や成長についての事物・現象に進んで関わり、粘り強く、他者と関わりながら問題解決しようとしている。
②動物の発生や成長について学んだことを学習や生活に生かそうとしている。

