実際の川との出合わせ方の工夫 ~小5理科「流れる水のはたらき」〜 【理科の壺】

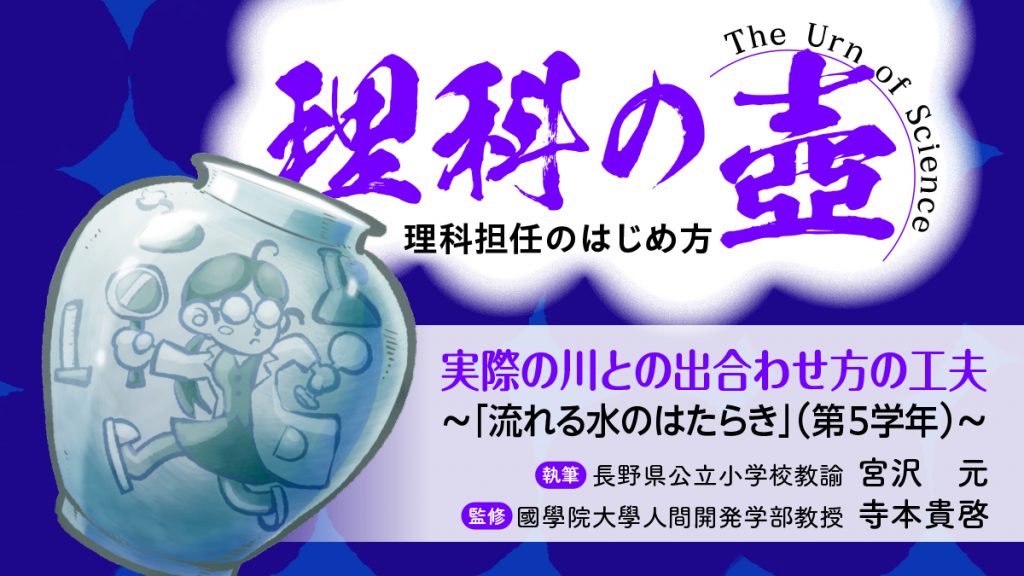
第5学年「流れる水のはたらき」の単元では、「川」をテーマに授業が進められます。実際に川を観察できればいいのですが、ちょっとハードルが高くなることもありますよね。それは、実際に観察しに行く手続きの煩雑さだけではなく、安全管理や、実際に行ったところで何をどのように観察させるのかなど、課題が多いからだと考えられます。しかし、あらかじめ留意点や、観察のポイントを押さえることで、だいぶハードルが下がると思いませんか。今回は、実際の川の観察を行うにあたって、留意すべきことについてご紹介していきます。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/長野県公立小学校教諭・宮沢 元
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1.実際に川に行って問題を見いだすためには
「流れる水のはたらき」の学習では、児童を実際に川へ連れて行く場面があります。そして実際に現場に着くと、教師の方で説明したくなって、児童が気づく前に流れる水のはたらきについて説明してしまったことはありませんか?
これでは、児童が自然事象と出合い、出合った時の気づきをもとにして、問題を見いだしていくチャンスを教師が奪ってしまうことになります。では、児童と自然事象をどのように出合わせ、教師はどのような発問をしたらよいのでしょうか。今回は、第5学年「流れる水のはたらき」の導入場面を例にして、実際に川に観察に行く場合の安全面の配慮と自然事象との出合わせ方について考えてみたいと思います。
新米のA先生は、先輩の先生の授業の様子を見に行くことにしました。どんな授業をしているのでしょう?
2.安全に観察できる場所を下見する
児童を実際の川へ連れて行く学習を進めるに当たっては、児童が行っても安全な場所であることが大前提となります。そのために事前に下見をして、安全確認をしておく必要があります。
<安全確認の下見をするポイント>
●当日の児童の動きをイメージし、予測しながら、事前に教師が川に近づいて確認をする。
・児童の人数と観察スペースは適しているか。
・川岸に近づいたとき、地面が崩れたり、石に滑ったりして落ちる危険性はないか。
・教師の目が届かない死角を作る岩や樹木、草むら、建造物はないか。
●危険性のある動植物が川原に生息していないかを確認する。
・ヘビやハチなど毒性のある動物はいないか。
・ウルシなど触るとかぶれてしまう植物はないか。
●観察場所だけでなく、観察場所より上流の川の変化も確認しておく。
・上流にダムがあって放流することはないか。
・上流での急な天気の変化による増水はないか。

