「〇〇をよく見よう」で始める理科の授業 【理科の壺】

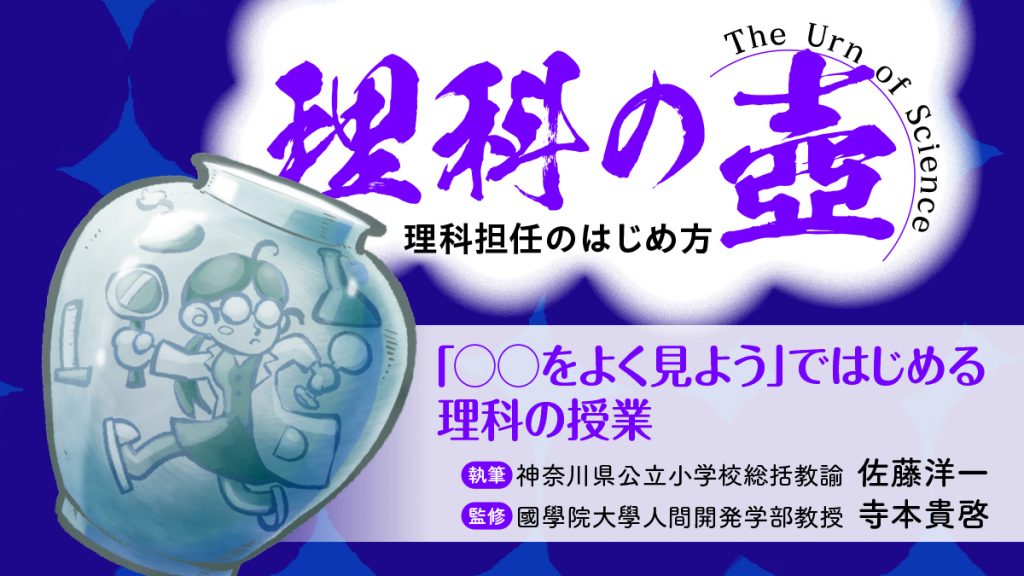
理科の授業では、自然事象の「実物」を観察して問題解決をしていきたいですね。動画や写真だけで授業を終わらせるような、「知識さえ教えればよい」という考えはNGです。しっかり目的を持って観察や実験をし、多くの体験を得てほしいです。
また、実際に観察や実験をする場合、しっかり事象を見てほしい。今回は、事象をよく見るための授業展開が紹介されています。子どもがよく見るためには、先生の働きかけが重要です。どのように子どもに働きかけていけばよいのか考えてみましょう。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/神奈川県公立小学校総括教諭・佐藤洋一
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1.自然ってどう見るの?
小学校理科の教科の目標の冒頭には「自然に親しみ」と示されています。自然に親しむには、子どもたちの方から自発的に働きかける活動が必要です。
私は、「〇〇をよく見よう」と子どもに投げかけることをおすすめします。この言葉によって、子どもは諸感覚を使って自然に働きかけることを意識します。それにより、自然の多様さに気付くことができるような子どもの育成へと繋がっていきます。子どもは自然から実に多くのことを発見します。発見できないのは、よく見る、という意識がないだけかもしれません。今回は、「よく見る」を取り入れた学習活動を2つご紹介します。
「〇〇をよく見よう」ではじめる理科の授業。あなたも夏休み明けからはじめてみませんか。
2.3年「音の性質」で「音をよく見よう」
「今日は、音をよく見ようの学習です」
この言葉で単元をスタートしてみましょう。きっと子どもたちは、「あれ?」と違和感を感じるでしょう。なぜなら、音は聞くものと思っていたのに、「目で見る」と言われたからです。
じっくり音を見る、という自然へのアプローチをするだけで、この単元の狙いである「音」と「震え」の関係に着目する子どもが育ちます。
今日は音の学習です。音をよーく見ましょう。
どちらの太鼓が音が鳴っているかな?
A(音が鳴っている太鼓の映像)…ここではあえて、実物ではなく動画を使います。撮影のアングルなどで、太鼓の皮(鼓面)の震えがよく分かるものにします。音を消して、映像を見ることだけに焦点化させます。
動いている。
揺れている。
震えている。
この太鼓は音が鳴っているんじゃないかな。
B(音が鳴っていない太鼓の映像)…Aとの比較になるように、音を鳴らしていない動画も見せます。
何も変わらない。
震えていない。
音は鳴ってないんじゃないかな。
2つの太鼓は、どちらが音が鳴っていると思いますか?
Aの太鼓。だって太鼓が震えていたから。
でも、確かめてみないと絶対とは言えない。
確かめたくなったことが、見つかったようですね。確かめたいことを、ノートに書いてみましょう。

