子どもが「問題の見いだし」ができる!“成功” と “失敗” の分かれ目【理科の壺】

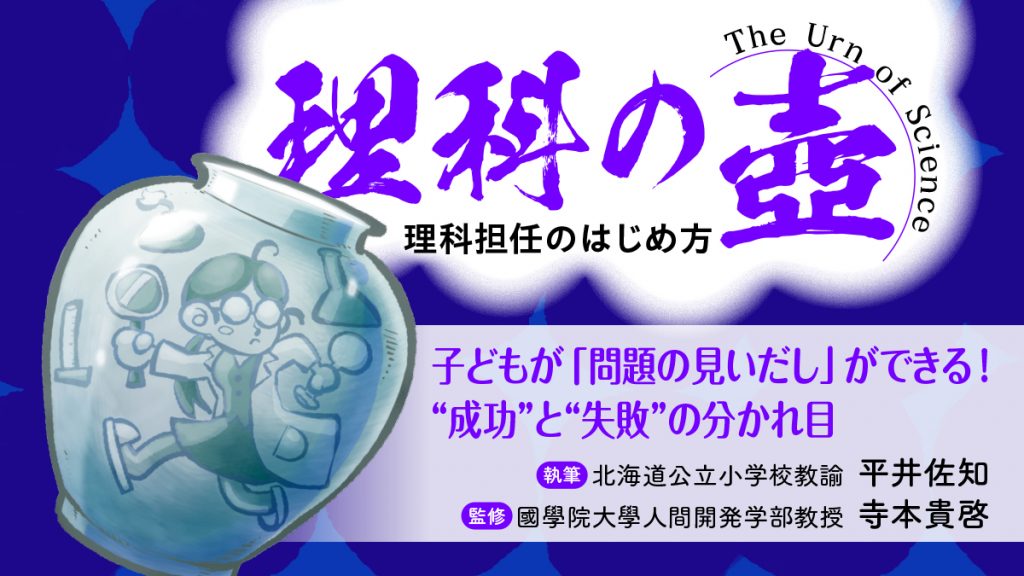
導入の時間は、子どもの実態や教材、先生の発言次第で、子ども自身で問題の見いだしができるかどうかが決まります。問題の見いだしができる、できないことには多様な要素があり、授業のその場で瞬時に判断する必要があり、難しいと言われます。今回はその問題の見いだしのポイントについて整理し、“成功”と“失敗”の分かれ目がどこにあるのか、具体的に解説します。学習内容や先生のキャラクターによっても発言の仕方が変わりますが、参考になるのではないでしょうか。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/北海道公立小学校教諭・平井佐知
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1.問題を見いだすのは“子ども自身”です!
単元の導入等で子どもたち一人一人が問題の見いだしをしていますか?
子どもたちが自然事象と関わり、「あれ?」「どうして?」と思ったことから、解決したい問題が見いだされます。問題を見いだすことは、その後の問題解決を進める上でとても重要です。出会った自然事象からせっかく子どもたちが様々な気付きや疑問をもったのに、交流した後、ついつい陥りがちがちな展開とこうなったらいいなという理想の展開を紹介します。
2.「問題」と「課題」の違いを知っていますか?
まず、ここでの「問題」とは何か?をはっきりしておきましょう。
これは一体何だろう、どういうことだろう、という学習者自らの「問い」が問題です。
課題は与えられた題目で、問題は自ら解決したい問いです。
<問 題>
◆研究・論議して解決すべき題
◆答えを求めるための問い
◆解決しなければならない事柄
◆理想と現実のズレ
<課 題>
◆課せられた題
◆与える、与えられる題目
◆問題を細分化したもの
◆理想に向けた解決の方向性

