読書指導のアイデア ①ブックトーク

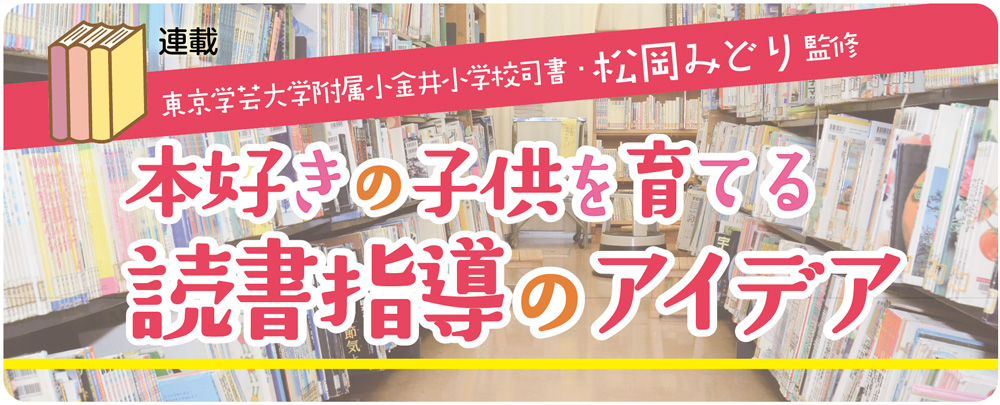
読書は子供の成長につながる大事な活動です。本好きの子供たちを育てるためのアイデアの1回目のテーマは「ブックトーク」。様々なジャンルの本を楽しく紹介して、目の前の子供たちが本を好きになるきっかけにしてみませんか。
監修/東京学芸大学附属小金井小学校司書・松岡みどり

目次
ブックトークを始めよう
ブックトークとは
ある1つのテーマを立て、テーマに添って、数冊の本を選び、順序立てて、集団を対象に紹介する手法です。本のあらすじを紹介したり、一部を読んだりすることによって、聞き手に、「面白そう」「続きを読みたい」など読みたいという気持ちを起こさせるほか、関連分野や著者などにも興味をもたせることをねらいとしています。
ブックトーク 準備~実践
1 テーマを決める
テーマを決めてから本を選ぶ場合と、この本を紹介したいという核となる本を決めてからテーマを決める場合があります。ここではテーマから決める場合を紹介します。
テーマを決めるときには、例えば、10月なら遠足や運動会などの学校行事や季節の行事、季節の風物など、子供たちの身近な生活から選ぶとつながりやすくなります。
また、野菜や生き物を育てている学級なら、その野菜や生き物をテーマにするのも子供たちの興味をかきたてるでしょう。
2 本を選ぶ
本を読むのが苦手な子もいれば、難しい本を読みこなす子もいるなど、子供によって本への接し方はまちまち。それを考慮して、やさしいものから、難しいもの、美しい絵や写真が多いもの、物語だけではなく、図鑑や詩など、幅広いジャンルから本を選ぶようにします。対象年齢によっても興味が異なりますので、対象年齢の興味も考慮しましょう。絵本は幼い子が読むイメージがありますが、絵を楽しめるうえ、様々な情報が詰まった絵本も数多くあるので、絵本を1冊入れておくことをおすすめします。
10分のショートバージョンなら2~3冊、30分程度なら4~5冊をめやすに選びます。
本選びは、子供たちがすぐに借りることができる学校の図書館から探すとよいでしょう。また、司書に相談すると、もっと多くの情報が得られ、協力してもらえることでしょう。
3 全体の構成、シナリオを考える
紹介する本が決まれば、次は全体の構成、シナリオを考えます。構成は、作文のはじめ、中、終わりをイメージすると立てやすいでしょう。シナリオを考える秘訣は、本の中にあるワードをつなげていくこと。ワードをピックアップすることによって、各本のどの部分を紹介すればよいかが明確になるうえ、自然に全体の流れにつながりが出てきます。
あらすじを紹介する本、挿絵や写真を紹介する本、興味を引くような場面の読み聞かせをする本など、紹介する本のバランスや紹介するページを決めて、あらかじめ付箋などを付けておくとよいでしょう。
4 実践する
本番前にリハーサルを行うことで、より落ち着けて臨めます。実践時には、書名を言って、表紙をしっかりと見せます。本の中を見せる際にも、子供たちからきちんと見える位置で本を持つようにします。本を紹介した際に、子供たちに興味がなさそうな様子がある場合は、その本は短く紹介するなど、緩急を付けて飽きない工夫もしてみましょう。
ブックトークの後、その本を借りることができたり、手に取ることができたりしておくと、子供たちはより興味をもつでしょう。子供たちに紹介した書名や著者名、出版社名などを書いたプログラムやブックリストをブックトーク後に配ると、子供たちが読みたくなったときの情報になります。

松岡みどり司書からのメッセージ
ブックトークをする場合、先生(担任)が読んで興味がある本を選ぶのがよいでしょう。子供たちは先生が「面白かった」と紹介すると、一気に興味がわいてきます。また、シナリオを組み立てて、そのとおりに進めるということも大切ですが、それ以上に大事なのは、先生の思いが伝わることです。「先生はこのシーンがすごく好きだよ。なぜなら~」というだけでも先生からの面白いというメッセージが伝わります。内容を教える場合、あくまでもネタバレは避けるようにします。ブックトークを難しいと思わないで、自分たちも楽しむ気持ちで一度実践してみてはいかがでしょう。子供たちが目を輝かせ、本を手に取る様子を見れば、「実践してよかった」と思うはずです。
子供たちにもブックトークを
実際にブックトークを体験すると、子供たち自身も本を紹介したいという気持ちがわいてきます。学級活動などの時間を活用してブックトークをするのもよいでしょう。その場合、本の冊数や絵本、物語本、その他の本などジャンルを決めておき、子供たちが班でのリレー形式で紹介するとやりやすいでしょう。また、テーマを決めておいて、子供たちの好きな本を持ち寄るのも意外な本が紹介されて、面白い実践になります。

