理科の予想は勘でも良いの?予想に対する根拠について【理科の壺〜理科担任のはじめ方】

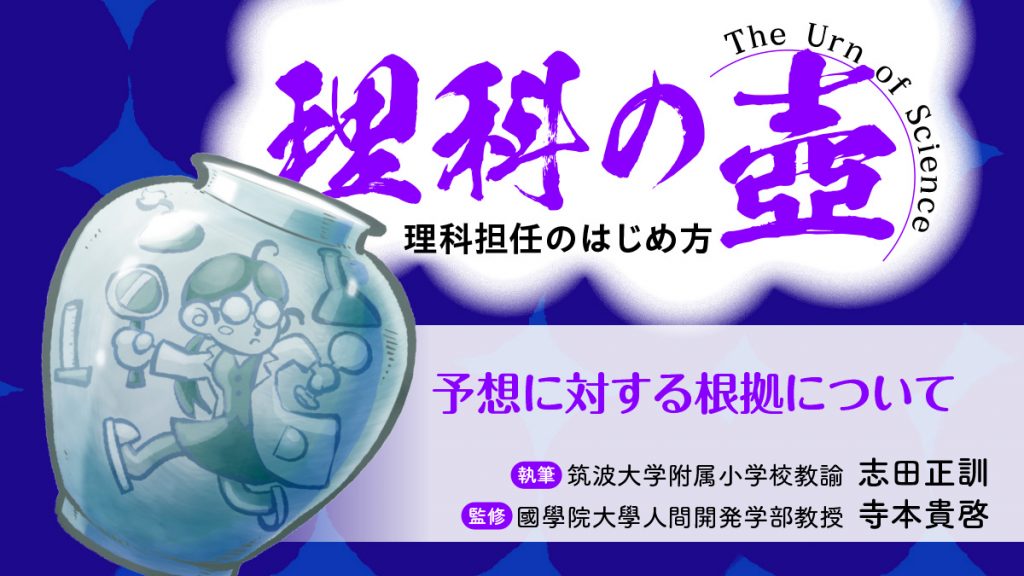
皆さんが理科の「予想」をさせるのは何のためですか?
「○○と思う」「○○なんじゃないかな」の「○○」の部分を答えさせるため? 理科では「科学的に」問題解決することが大切になります。そのため、「予想する際に『勘』でもいいのか?」が問題になります。そもそも、「なんとなく」と勘で予想させることに意味があるのか? ということです。今回は、理科の予想について、どのように考えたらいいのか、ご紹介します。
優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?
執筆/筑波大学附属小学校教諭・志田正訓
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
目次
子どもたちの予想や仮説に根拠は必要?不要?
理科では、子どもが見いだした問題に対して、「原因は〇〇なんじゃないかな?」といった、予想や仮説を子どもが自分で発表したり、ノートに書いたりする場面があります(「予想や仮説を発想する」といいます)。子どもが予想や仮説を発想することは、自分で見いだした問題に対して、その原因が何なのかなどについて自分なりの考えをもつことです。この、予想や仮説を発想することは、次の2つの点でとても大切になる学習活動です。
①その後の観察や実験を行う際に、視点を明確にして取り組むことができる。
②考察をして結論を導出する際に、予想や仮説に基づいて考えることができる。
では、予想や仮説に対して「根拠」は、必要でしょうか、不要でしょうか。どちらかで答えるなら、「必要」です。なぜならば、『小学校学習指導要領解説 理科編』でも、特に第4学年を中心として育成すべき「問題解決の力」に「根拠のある予想や仮説を発想し、表現すること」が挙げられていて、評価にも大きく関係するからです。
全ての問題で根拠のある予想や仮説を発想することは可能か?
子どもは、予想や仮説を発想する際に、主に「家で○○だったから…」といった生活経験や、「前に○○という学習をしたから…」といった既習事項を根拠にします。では、理科の教科書に出てくる全ての問題に対して、子どもは生活経験や既習事項を根拠にして、予想や仮説を発想することができるのでしょうか。
やはり中には、根拠を明確にしづらい問題もあります。例えば、第6学年の「人の体のつくりとはたらき」で、「人や他の動物は、空気を吸って、空気中の何をとり入れているのだろうか。」という呼吸に関する問題に対して、「酸素」などの気体名を予想として考えることはできても、なぜそうなのかを生活経験や既習事項から考えるのは難しいのではないでしょうか。他にも、第3学年の「昆虫の成長と体のつくり」に関する学習で、モンシロチョウを扱う際に、「チョウの成虫のからだは、どのようなつくりをしているのだろうか。」という問題に対して、「いくつかに分かれている」といったような予想を考えることはできても、なぜそうなのかを考えるのはやはり難しいでしょう。
このように、予想や仮説を発想する場面では、子どもが根拠を含めて表現することは大切ですが、その内容によっては、根拠を考えることが難しい場面もあります。このような場面では、無理に根拠を考えさせることに授業の時間を割くのではなく、子どもの予想や仮説をどうやって確かめていくかということを考えていく時間にしていくと良いでしょう。


