小1算数「わかりやすく せいりしよう」指導アイデア《ものの個数を分かりやすく表す方法を考える》
執筆/神奈川県公立小学校主幹教諭・黒木正人
編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、島根県立大学教授・齊藤一弥
目次
本時のねらいと評価規準
(本時1/2時)
ねらい
ものの個数を簡単な絵や図を用いて表すことのよさを感じ、今後の生活に生かそうとする。
評価規準
ものの個数を分かりやすく表す方法を考えることができる。

問題
なんかいめにつれたかずがおおいでしょう。
※問題は掲示しない。魚釣りゲームをした結果を掲示。
1かいめ
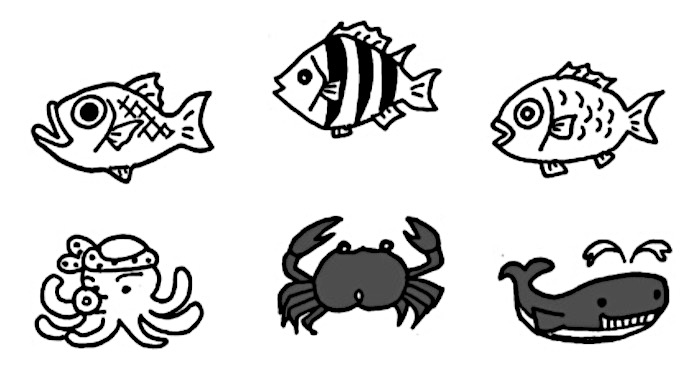
2かいめ
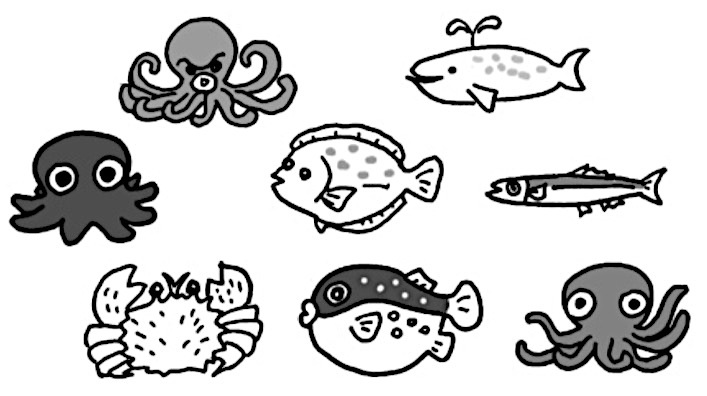
3かいめ
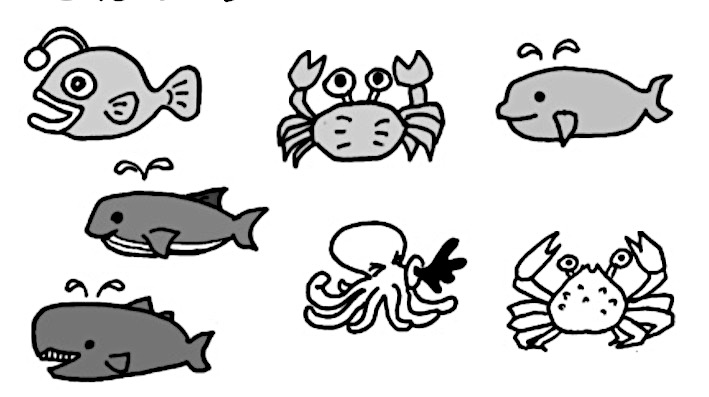
釣りゲームで、釣った全部の数は分かりましたか。
(数を数えて言う)
全部で3回やりましたが、何回目が一番多く釣れたか分かりますか。(問題の掲示)
うまくなってきたから3回目かな。
2回目もたくさん釣れたよ。
見た目だと3回目が多いな。
このままだと数えにくいよ。
どのようにすれば比べやすくなりますか。
並べたら見やすそう。
大きさが違うから並べにくいな。
どんなふうに並べたらよいですか。
まっすぐ並べたらいいと思うけど…。
学習のねらい
もののかずをわかりやすくあらわすことができるかな。
見通し
- 長さを比べたみたいに、端を揃えて高さで比べたら分かりやすいよ。
- 大きさが違うから、横も揃えると見やすくなるはず。
自力解決の様子
A つまずいている子
並べたが、揃えることができず、数えて求めている。
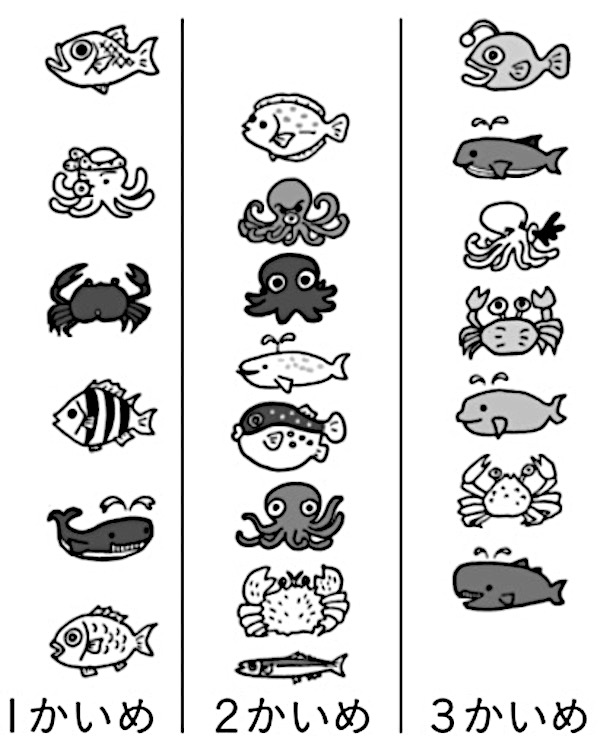
B 素朴に解いている子
端は揃えているが、横を揃えることが分からず、 数えて求めている。
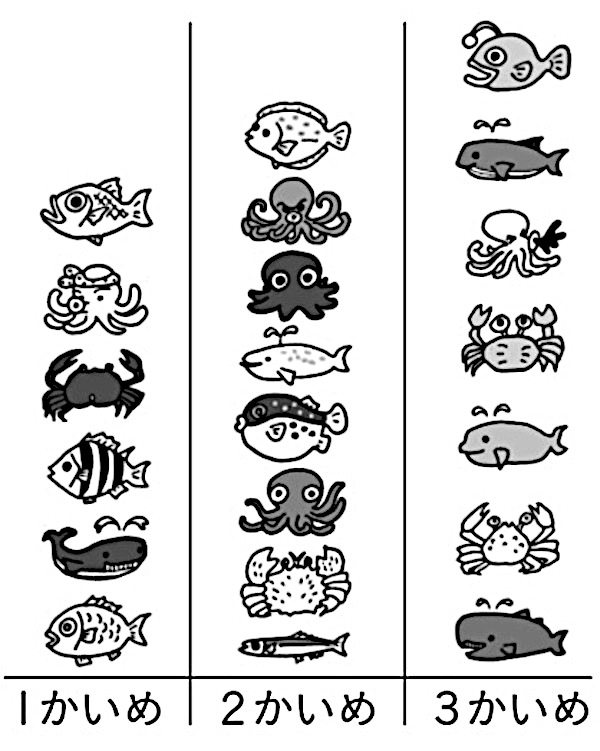
C ねらい通りに解いている子
ます目の中に入れるなど、端と横を揃えて、高さで比べている。
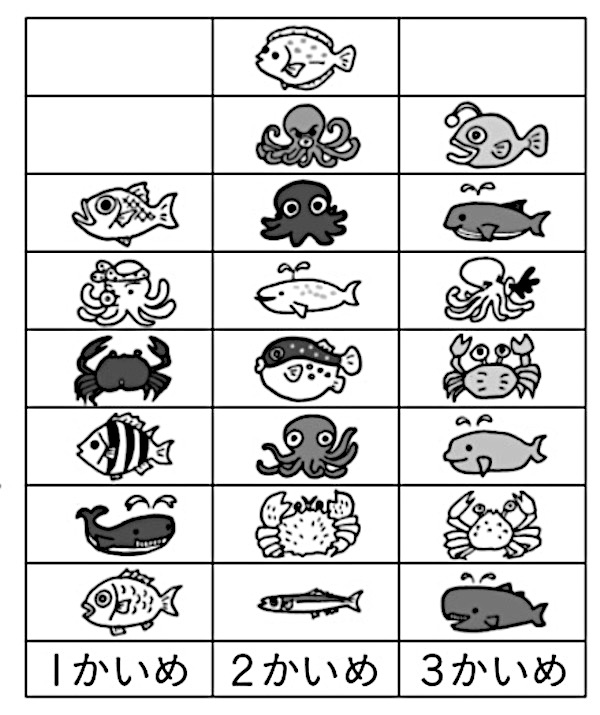
学び合いの計画
イラスト/松島りつこ・横井智美
『教育技術 小一小二』2020年9月号より

