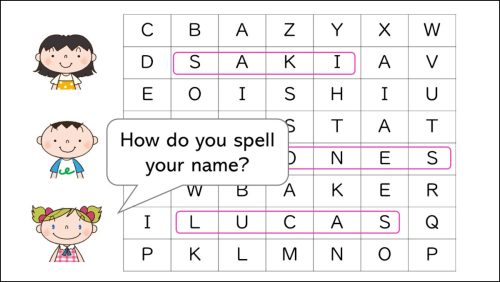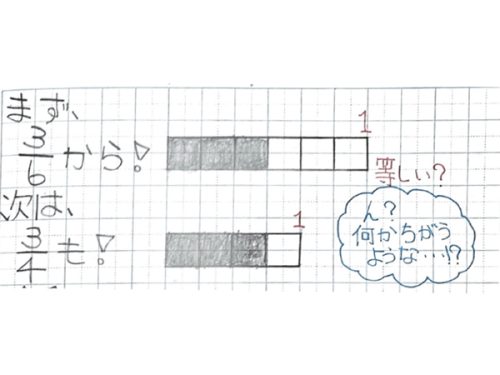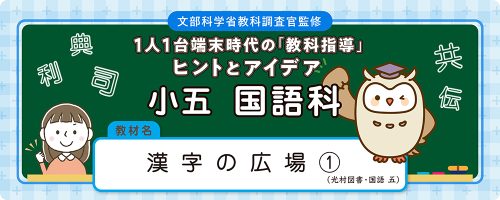小3算数「わり算」指導アイデア(1/11時)《何かを同じ数で分けるときの計算》
執 筆/福岡教育大学附属福岡小学校教諭・田中智史
編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏
目次
本時のねらい
本時1/ 11時
問題場面の数量を具体物に対応させて、それらを等分する活動を通して、等分除の場面の数量の関係を式で表す方法について理解する。
評価規準
等分除の操作や図を、除法の式で表すことができる。(知識・技能)
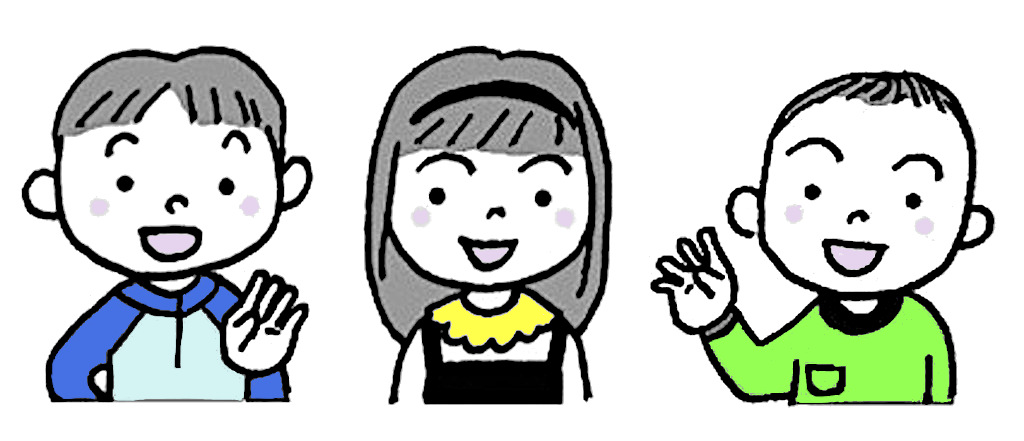
問題場面
12このクッキーを、4人に同じ数ずつ分けます。1人分は何こになりますか。
何かを同じ数で分けるときはどんな場面がありますか。
お菓子を分けるときがあります。
給食のときもみんなで分けています。
トランプでカードを配るときも分けます。
※本時は、具体物操作で等分の意味を理解させていきます。はじめに身近な等分場面を想起させることで、等分の操作の見通しをもつことができるようにしましょう。
学習のねらい
ブロックを使って、1人分がいくつになるか調べよう。
見通し
ブロックとお皿で考えます。いくつ必要ですか。
ブロックはクッキーのことだから12個使います。
4人に分けるからお皿は4枚必要です。
同じ数ずつに分けるには、どのようにしたらよいでしょう。
トランプみたいに、1個ずつ順番に分ければいいです。
大体で分けて多いところから少ないところに移します。
3個ずつになると思います。
自力解決の様子
A つまずいている子
ブロックの数や皿の数が場面と異なっている。またはブロックを等分することができていない。
B 素朴に解いている子
1つずつ順番に分けたり、まとめて分けた後に調節したりして、場面に合った等分の操作ができている。
C ねらい通り解いている子
活動の結果をふり返り、3×4=12という乗法と関連付けて考えている。
学び合いの計画
自力解決の後は、活動をふり返るための交流をペアで行い、「12個を4人に等分すると3個ずつになる」ということを確認させます。
イラスト/小沢ヨマ ・横井智美
『教育技術 小三小四』2020年4/5月号より