小2道徳「みんなの ものって?」指導アイデア

執筆/北海道公立小学校・藤原友和
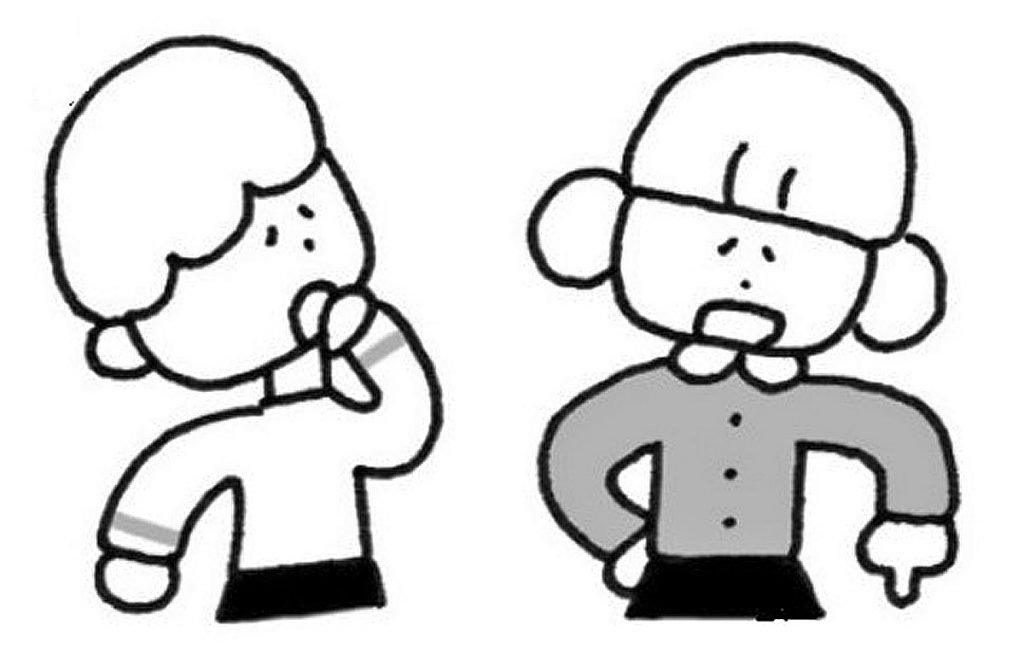
目次
指導項目「規則の尊重」
約束やきまりを守り、みんなが使うものやみんなのものを大切にすることができるようになる。
趣旨
「使った道具はきちんと片付ける」
二年生の子どもは、「ものを大切にする」とはどういうことか、頭では理解していますし、「どうしたらいいのかな?」と問われたらこのように答えるでしょう。
しかし、実際の生活の中ではまだまだ行動が伴わず、そのたびに注意をされてしまいます。これは、「言葉でわかっていること」と「実際に行動すること」の間にいくつかの「壁」があることが原因です。
その中の一つが、幼児期のもつ自己中心性です。「みんなで使うものを、片付けなければいけないことはわかっている。けれど、別の遊びがしたい」「みんなで使うものは大切にしなければいけない。けれど、遊びに夢中で乱暴に扱ってしまった」というように、自分の都合を優先してしまうことが、わかっていてもできない要因です。
日常的に指導を重ねていく必要はもちろんありますが、道徳科の授業でこの時期に取り上げ、みんなで考え、みんなで確かめておくことは、その後の指導に効いていきます。
「自分のものも、みんなのものも大切にする」
本時の指導内容だけに限らず、「みんなで使うものを大切にする」ことは、道徳科の時間に一度扱ったからといって、すぐに身に付くものではありません。しかし、さまざまな角度から考える経験をしておくことで、その後の生活の中で「できている自分」に自信を持ったり、「ついうっかりしてしまった自分」に気付いて、改めようとする気持ちをもつことができたりします。
例えば、授業後の学校生活の中で指導するときにも、「あのときの勉強で、こんなこと話し合ったよね?」「覚えている? どうするのだったっけ?」などと想起させながら、「気付いて自分で再挑戦する」ことができるようにします。こうした中期的な見通しの中に本時を位置付けることで、効果を高めることができます。
また、本時では、「片付けなさい」と声をかけられたときに、どのような返事をするのかという設定で「ロールプレイ」を行います。「ロールプレイ」は楽しい活動ですが、あまりに盛り上がると、ねらいからはずれてしまったり、演技の後でその思いや判断、友達の演技を見た後の言語化が上手くいかないことも心配されます 。 しかし、同種の活動を繰り返すことで徐々に習熟していきます。
なお、教育出版の教科書では、この単元で2つの教材が扱われていますが、ここでは後半の教材のみを扱います。

