【シリーズ】高田保則 先生presents 通級指導教室の凸凹な日々。♯15 通級指導は、何のためにあるのか?
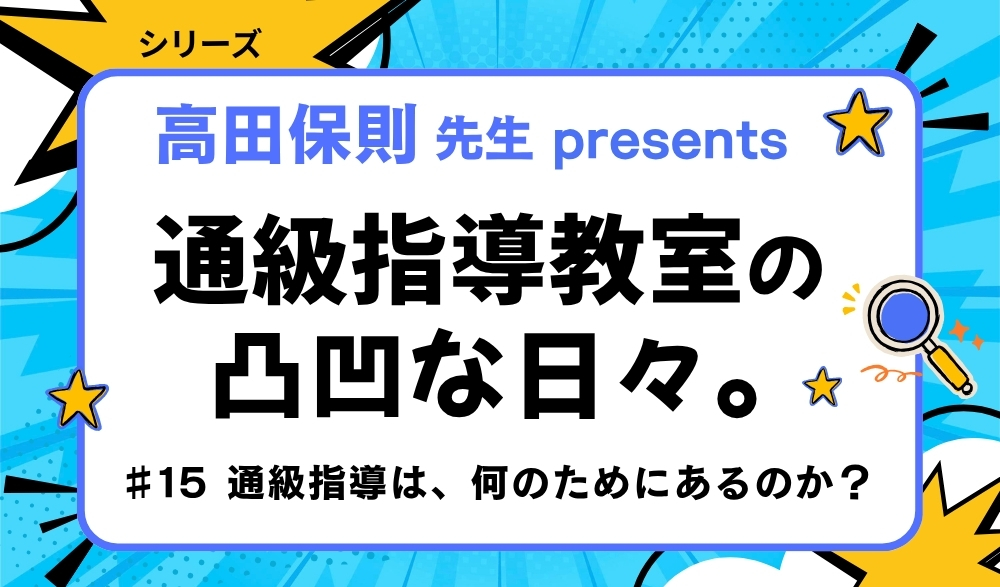
通級指導教室担当・高田保則先生が、多様な個性をもつ子どもたちの凸凹と自らの凸凹が織りなす山あり谷ありの日常をレポート。情熱とアイデアに満ちた実践例の数々は、特別支援教育に関わる全ての方々に勇気と元気を与えるはずです。
執筆/北海道公立小学校通級指導教室担当・高田保則
目次
はじめに
北海道オホーツク地方の小学校で、通級指導教室を担当している高田保則(たかだやすのり)です。日々、子どもたちと向き合う中で感じたことや考えたことを綴っています。ここに記す事例は、これまでに出会った子どもたちのエピソードを組み合わせてつくった架空のお話ですが、実際に過ごした時間の空気感を込めています。
通級指導を担当した教員の多くが、最初に悩む問いがあります。
「通級指導は、何のためにあるのか?」
目的が曖昧なまま、日々の指導にあたっている先生も少なくないでしょう。
「学習面の支援をしても効果が上がらない」
「子どもの気持ちが不安定なまま」
「授業中のお喋りや立ち歩きが収まらない」
今日も、思い悩みながら指導を続けられている方がいらっしゃると思います。
私自身、この問いに長く向き合ってきました。行き着いた答えは1つです。
今回は、「通級指導の核心」というテーマで綴ってみます。
1.「困り」をめぐる誤解 ー 通級指導は治す場ではない
「この子に困りはないんです」
学級担任から、そう言われることがあります。私は、モヤモヤします。
“困りがない”とは、何を根拠に言うのでしょうか。悩みや不安を全く持たない子どもはいません。困っているかどうかは、子ども自身が感じるもので、学級担任が判定するものではありません。
私が思うに、通級指導の目的は、困りを“治す”ことではなく、困りの背景を理解することです。通級指導担当者の仕事はアセスメントです。その子にどんな困りがあるのか、あるいは困りを感じているのかを分析するのが仕事です。だから、学級担任の主観で、「困りはない」と言われると、私はモヤモヤするのです。
子どもと毎日接している学級担任からすれば、「週に1度しか子どもと関わらない通級指導担当者に何がわかるの?」とイライラするのかもしれません。学級担任がイライラし、通級指導担当者がモヤモヤする背景には、2つの要因があると考えます。
①通級指導教室を支援学級の“前段階”のように運用している実態がある。
不適応を起こした子どもを一時的に通わせ、改善が見られなければ支援学級を勧めるというケースが多くあります。そんな運用では、通級指導教室が「不適応を改善する場」として固定されてしまいます。
➁通級指導担当者が子どもを指導して改善することに躍起になり分析を怠っている。
通級指導の担当者が、その子の困りの背景要因を丁寧に掘り下げず、困りの改善の指導に走ってしまう現実があります。例えば、計算が苦手な子に、過去に成果を上げたプリント教材を沢山与えるというようなケースです。もしもその子が、字を書くことや集中の維持に弱さをもっているとしたら、通級指導は苦行になってしまいます。
通級指導教室が制度化されて30年以上経つのに、未だ運営方針が確立されていない現実があります。
「通級指導の業務は、アセスメントです」と明記した方が、通級指導の業務がより明確になるし、学校運営も通級指導担当者の努力目標もはっきりすると思うのです。
2.そのアセスメントはその子のオリジナルですか?
生成AIの進化には著しいものがあります。年齢と主な困りと検査データを入力するプロンプトを提示すると、生成AIは瞬時にそれらしい分析と指導の手立てを示します。そのまま検査レポートとして、保護者や担任にお示ししても、疑問が生じないような出来栄えです。一見すると、もっともらしく見えます。
でも、生成AIのアセスメントは、その子だけのオリジナルなものでしょうか? 私は違うと思います。生成AIは、情報を速く正確に処理できますが、意味を理解しているわけではありません。その子のアセスメントは、子どもに関わって子どもを理解しようとしている教職員にしかできないのです。理解とは、関係の中で生まれる営みです。子どもの表情、しぐさ、視線の揺れなど……。それらを感じ取りながら見立てをするのが、子ども理解に基づくアセスメントです。
子ども理解に基づいたアセスメントをしないと、効果的な指導にはつながりません。通級指導で求められるのは、その子だけのオリジナルのアセスメントです。
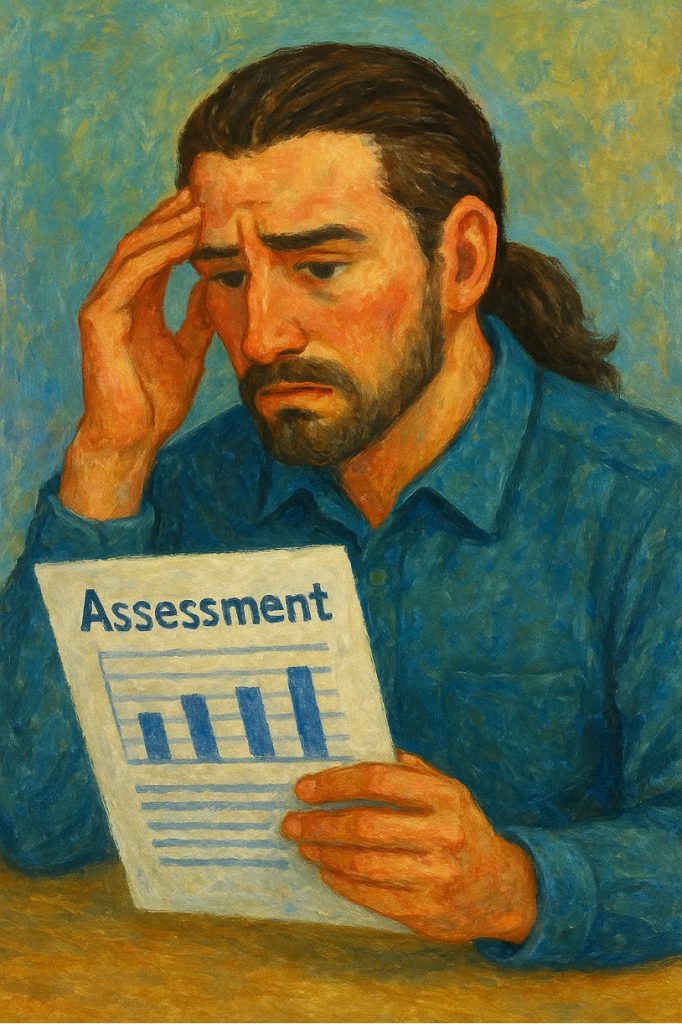
3.事例から見るオリジナルのアセスメント ー AさんとBさんの核心
〈Aさんの場合:学業面の困り〉
Aさんは、学業成績が伸び悩んで自信を失いかけていました。自ら望んで、通級指導での学習アドバイスを受けました。知能検査をしたところ、高い能力が確認されました。理解力と記憶力が高く、見て捉える力と作業能力は年齢相応でした。その差はかなり大きなものでした。でも、学業不振を説明できる根拠にはなりませんでした。
そこで、Aさんの学習の様子を詳しく訊くことにしました。
「これを見て。速く書くと、こうなっちゃう。」
Aさんはそう言って、ノートを見せてくれました。読めるものの、かなり崩れた字でした。一方、Aさんは習字とピアノを習っていることが分かりました。また、イラストを描くことも好きでした。そのことから、手先の不器用さはないと分析しました。
次にテスト問題の誤答について尋ねました。
「テストの端に筆算をした時、自分で書いた0と6が自分で分かんなくなって間違えたことがある。」
困りの背景が見えてきました。高い理解力を有するAさんは、頭の中で色々な事を考えてしまいます。一方、作業能力は年齢相応のため、それをアウトプットする時に処理が追い付かなくなるのです。それは、右利きの人が左手で字を書くような状態に近いかもしれません。アウトプットを焦るあまり書字が適当になり、誤答を招くのではないかと仮説を立てました。Aさんの困りの本質は、内容理解の不足ではなく、作業の“雑さ”にあると分析したのです。
「つまり、キミの困りは“雑”ってことだよね。“雑”を改善する方法を考えよう。」
手立てを3つ提案しました。
a. 大人のぬり絵を丁寧に仕上げる。
b. 美文字アプリで書字の練習をする。
c. ベースギターを練習して発表会で披露する。
Aさんが選んだのは、美文字アプリでした。習字の練習にもなるので一石二鳥だと教えてくれました。
「タカダ先生と美文字勝負をするってことですよね。」
私の字が下手くそなことを知っているAさんは、そう切り返してきました。
「受けて立とうじゃないか。大人の本気を見せてやろう!」
私はそう応えて、翌週からAさんとの美文字対決が始まりました。
さて、通級指導教室の担当として、Aさんと良好な関係を結ぶために、私は2つの点に留意しました。
①子どもに自分の分析を伝える
②子どもに選択肢を提示する
通級指導担当者の私の仕事は分析することです。だから、分析結果は当事者の子どもにも分かりやすく伝えるべきだと思っています。分析結果を伝えられたAさんは、私に尊敬の気持ちをもったようです。休み時間に見せる『ダメなおじさん』じゃない顔を知ってしまったからなのでしょう。私へのタメ口が敬語に変わりました。
複数の手立てを示すのは、子どもに選択肢を示し、やらされ感を減らすためです。どんなに良い方法でも一つだけだと、意欲は長続きしないのです。子どもは、自分で選ぶことで責任を感じます。自分で決めたからこそ、できるまで頑張ろうとするのです。
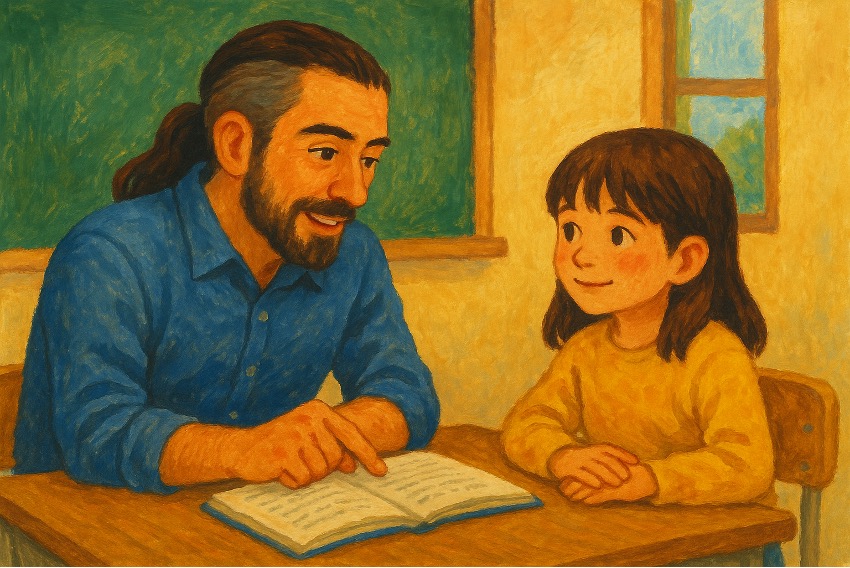
〈Bさんの場合:不可解な行動〉
学校で、パーカーのフードを被ったまま過ごす子が時々現れます。私のこれまでの経験では、そうする子は何らかの心の問題を抱えていました。遅刻や欠席が続いたり、トラブルを起こしたり、攻撃的になったり、極端に口数が少なくなったりする背景に心の問題があるのです。
学校を休みがちで、遅刻も多いBさんは、私の通級指導の対象の子でもあります。Bさんが、パーカーのフードを被って登校しました。私は、Bさんがフードを被りたくなる心境を想像しました。
“話したくない”“聞きたくない”“見たくない”“そっとしておいてほしい”
何らかの不安定な気持ちがBさんの振る舞いの背景にあると考えました。
私は、フードを被っている子に服装を正す指導はしません。校内で帽子を被らないのと同じく、フードを被るのはマナーに反することを子どもは分かっています。マナー違反をするには、理由があるはずなのです。Bさんと何気ない会話をしながら、「なにかあった?」と尋ねました。
Bさんは「別に……。」と答えました。私はそこで、Bさんから何かを引き出そうとは考えませんでした。Bさんに、「気にかけているよ」というメッセージが伝われば充分だと思ったのです。翌日、Bさんは、何事もなかったように明るい顔で登校しました。昨日は保護者と大喧嘩していたことを教えてくれました。その後の通級指導では、保護者と上手くやる方法について、2人でアイデアを出し合いました。
子どもがフードを被る背景は様々です。“話しかけないで”という意思表示でもあれば、“気付いてほしい”というメッセージの場合もあります。だから、見立てと関わり方もケースバイケースになります。
Bさんとの関わり方はあくまで私のやり方で、これが正解だなどとは思いません。そもそも、教職員が子どもと関わる時に、たった1つの正解なんてありません。情報共有や共通理解は必要ですが、教職員の関わり方や指導の仕方まで統一する必要はないと思います。それは、多様性に反するからです。学校には、いろいろな個性を持つ教職員がいた方が、子どもたちにとって面白いはずです。
だから、フードを被っている子に、「だらしないから取りなさい!」と指導する教職員がいたっていいと思うのです。“先生によって叱る地雷は違う”と子どもは学びます。
私は、「指導の足並みをそろえる」という言葉が、学校の許容範囲を狭めて、子どもと教職員の関係を窮屈にしていると感じてしまうのです。
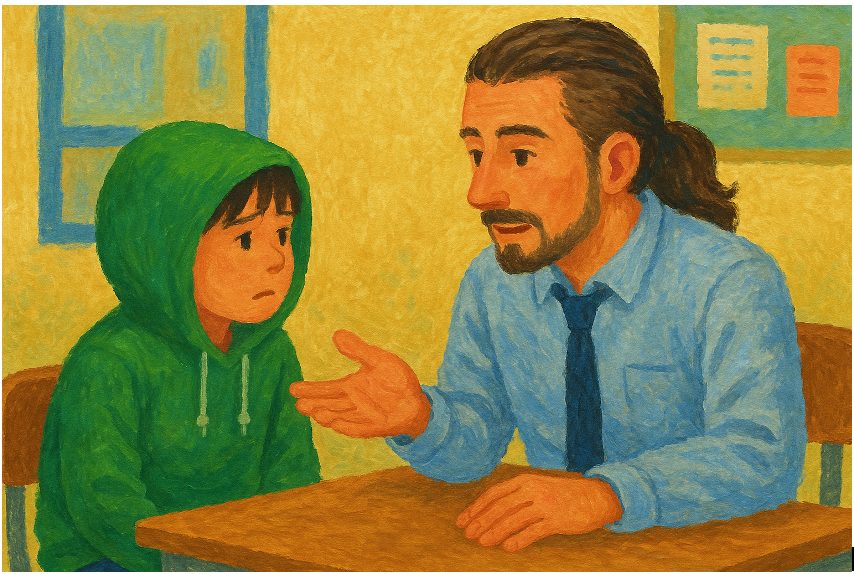
4.アセスメントを繰り返す
通級指導の話に戻ります。通級指導を繰り返すたびに、子どもが見せる様子は変化していきます。子どもの成長速度は速いので、1週間前とは違う姿を見せてくれます。それに伴い、見立てた指導の仮説は、修正されていきます。通級指導とは、子どもの様子を観察・分析して、アセスメントを繰り返すことそのものです。そして、得られた情報を保護者と関係職員、そして子どもにも伝えて、子育てと指導と学びに活かしてもらう営みだと思うのです。それが私の考える通級指導の核心です。
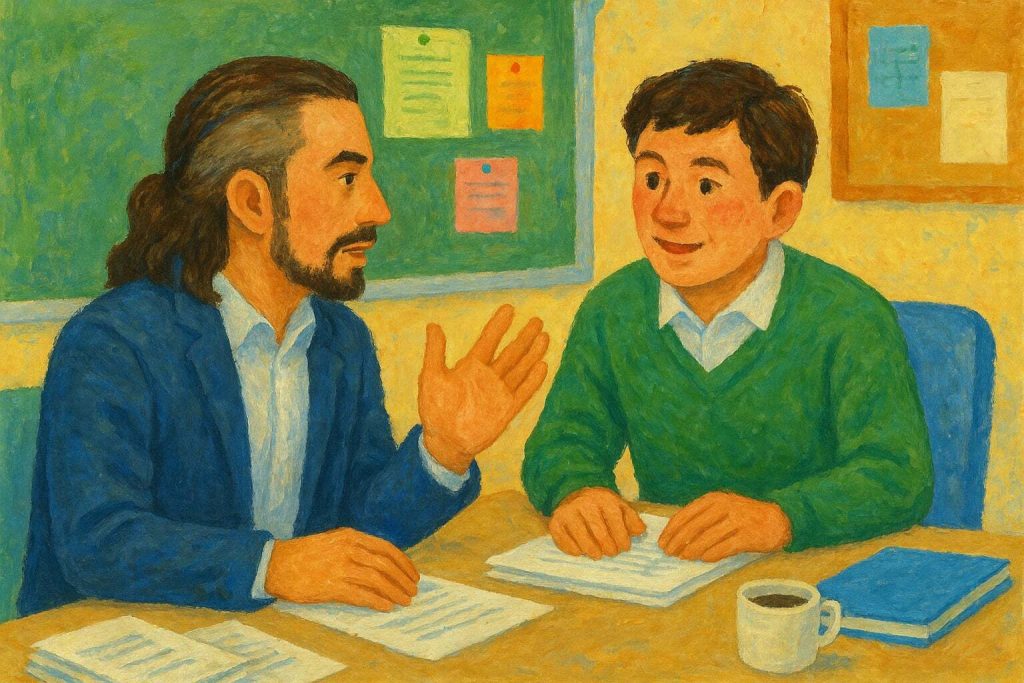
6.おわりに
お世話になっているスクールカウンセラーの方から1冊の本を紹介されました。現役のカウンセラーであり、臨床心理学の研究者でもある東畑開人さんの書籍でした。以来、新著が出る度に勉強させていただいています。
東畑さんは、カウンセリングを「謎解き」「作戦会議」「冒険」と表現しています。それは、通級指導にも通じる部分が大いにあると頷きながら読んでいます。
〇謎解き:子どもの行動の意味を読み解くアセスメント
〇作戦会議:教員・保護者・子どもと共に方法を考える
〇冒険:新しい学び方を試みる挑戦
アセスメントし、方法を考え、試みる。上手くいかなければ、アセスメントを修正して、方法をアレンジして、再び試みる。その繰り返しが、通級指導の核心だと考えます。
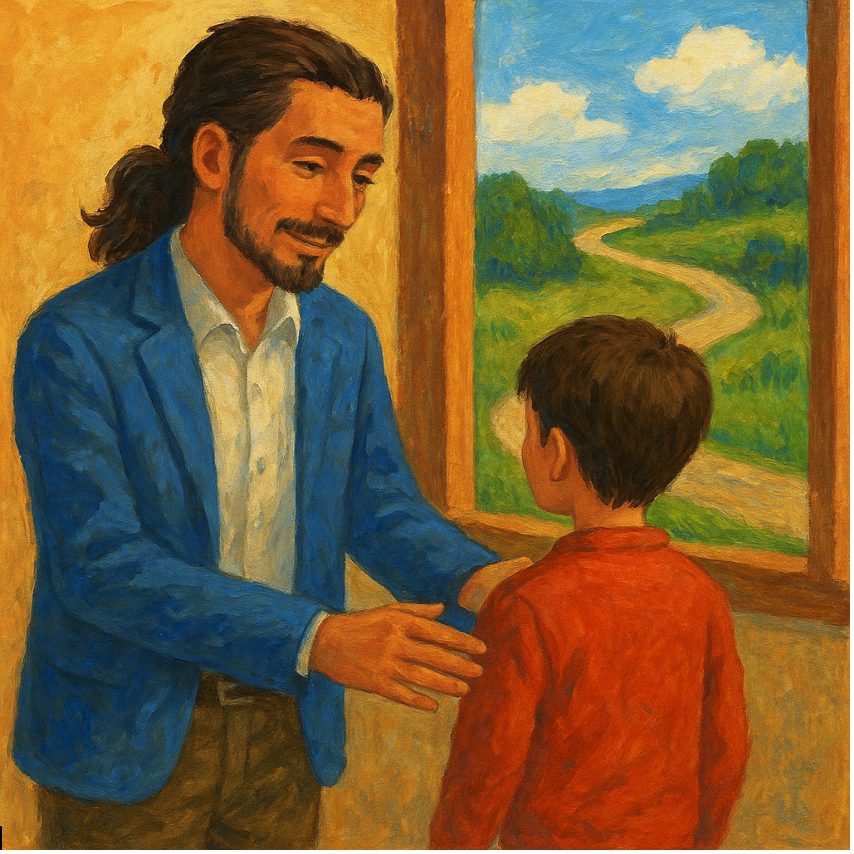
※参考文献・資料
〇『カウンセリングとは何か 変化するということ』 東畑開人 著 講談社現代新書 2025

高田保則先生プロフィール
たかだ・やすのり。1964年北海道紋別市生まれ。オホーツク地域の公立小学校教諭。公認心理師。特別支援教育士。開設された通級指導教室の運営を任され、新たな指導スタイルを模索している。趣味はバンド演奏。

