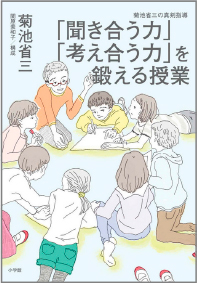<連載> 菊池省三の「コミュニケーション力が育つ年間指導」~3学級での実践レポート~ #23 千葉県船橋市立田喜野井小学校5年1組④<前編>

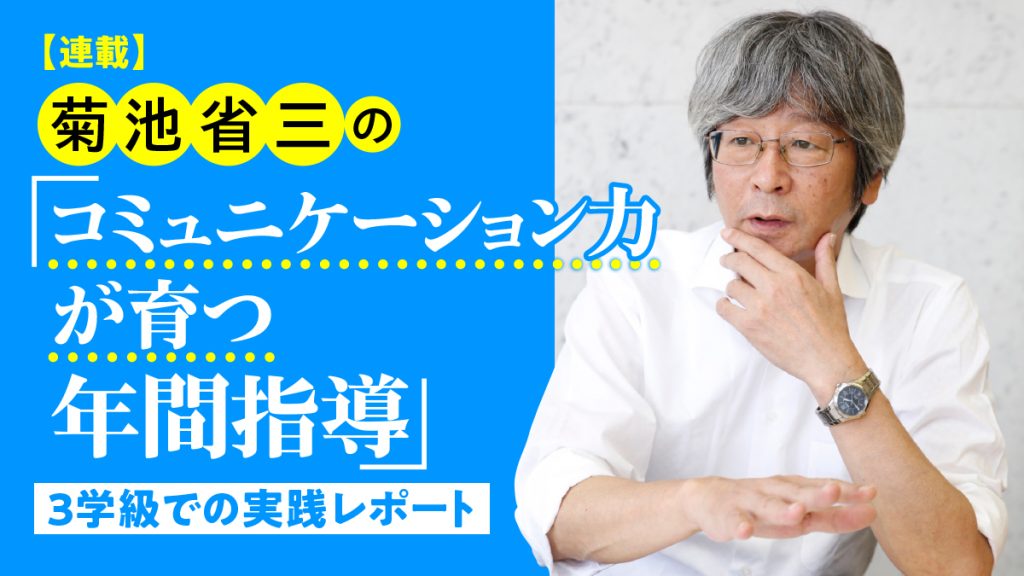
菊池実践を追試している3つの学級の授業と子供たちの成長を、年間を通じてレポートする好評連載。今回は千葉県の植本学級(5年生)における2025年2月の授業レポートの前編です。菊池先生と植本先生による、2時間続きのディベートの合同授業の記録です。

目次
担任・植本京介先生より、学級の現状報告
前回の菊池先生の訪問から、「学習には質がある」ことを、子供たちが感じてきたようです。菊池先生との授業が「メタ認知の強化」でしたが、それまで子供たちの中にはそういう概念がなかったと思います。
一般常識と離れていても、自分が思うことを最優先に考えてきた子たちですが、2学期末あたりから周りのことを気にかけるようになり、学級全体の雰囲気が少しずつ社会化・一般化してきたように感じています。
授業の中でもメタ認知を意識し、子供たち自身で解決する時間を増やしているようにしています。
算数での学び合い・教え合いや社会科でのディベート的な話し合いの準備、6年生を送る会に向けての出し物の企画、帰りの会の子供たちの活動などでは、一歩引いて子供を観察するようにしています。
菊池先生と植本先生の合同授業レポート
「今日のディベートは、前の時間にA君が話した『思いやりをもってバチバチやる』でいきましょう」と植本先生が声をかけると、みんながやる気の表情でいっぱいになった。菊池先生が、
「みんなのことをみんなで話し合ってみんなで決めていく。『自分たちの学校をよりよくしよう』というこの論題は、日本一価値があると思います」と続け、みんなで大きな拍手を送り合った。
論題「田喜野井小学校に新たに代表委員会を設置する」に基づくディベートを始めるにあたって、次のことを前提に考えた。
1 構成員は、4年生以上の学級2名と各委員会委員長とする。
2 代表委員会の開催は年8回、原則各月の委員会活動の翌週に行うものとする。
3 「たきのいタイム」(毎週水曜日の長い昼休み)に行う。
4 3名程度の先生も出席する。
この提案について、賛成派と反対派に分かれてディベートを行った。
ディベート論題「田喜野井小学校に新・代表委員会を設置すべきである」
●ディベートのルール
代表の2チームが立論を発表する。他のチームも賛成・反対に分かれて、質問や反論を行う。
発表、作戦時間はすべて2分間。質問は3分間。ディベートの流れは以下の通り。
①賛成側立論 → 作戦タイム ➡︎ ②反対側質問
③反対側立論 → 作戦タイム ➡︎ ④賛成側質問
⑤反対側反論(第1反駁)
⑥賛成側反論(第1反駁)
第1反駁は、質問した内容に対してだけでなく、立論に対して反論してもいい。
⑦反対側反論2(第2反駁)
⑧賛成側反論2(第2反駁)
判定は、学級全員で話し合う。
早速、ディベートがスタートした。
①賛成側立論
「児童が成長するから」
理由:1つめは、児童が創意工夫できるようになること。現在、各委員会が別々に活動しているが、多くの活動は先生の指導が中心となり、子供自身が責任感を感じて行動することが少ない。新・代表委員会を設置することで、委員会同士で意見を出し合ったり、協力し合ったりして、新しいことを創造するようになる。その結果、活動にやる気が出て、自ら考えて行動するようになる。
2つめは、下の学年の意見を取り入れられること。1~4年生は委員会に入れないため、学校に関する意見を出せる機会がない。新・代表委員会を設置し、議題ポストを設置することで、低学年の意見を聞くことができる。
<反対側質問>
質問)児童が創意工夫するというのは本当ですか。
回答)はい。
質問)例えばどういうところで責任感を持つのですか。
回答)児童が意見を持つことです。
質問)先生の指導が中心となるのは本当ですか。
回答)はい。
質問)なぜそう言えるのですか。
回答)……。
質問)新しいこととはどんなことですか。
回答)……。
質問)創意工夫ができることでやる気が出るというデータはありますか。
回答)はい。
③反対側立論
「トラブルが起きるから」
理由:1つめは、より忙しくなること。現在、毎日活動がある委員会もあり、忙しい。その上、代表委員会が入るとさらに忙しくなる。準備のために、「たきのいタイム」に休み時間を使うことも増えるため、友達と遊ぶ時間が減ってしまう。
2つめは、誹謗中傷が起きること。代表委員会で議論して決まったことをみんなに伝えるたびに、「なぜこうなったのか」と反論し、誹謗中傷が起きる。重い誹謗中傷で自殺することもあり、田喜野井小でも起こりうるのではないか。誹謗中傷のたびに人間関係が悪くなり、よりトラブルが多くなる。
<賛成側質問>
質問)忙しい委員とはどんな委員会ですか。
回答)体育委員や図書委員や給食委員など、毎日活動があります。
質問)誹謗中傷について具体的なデータがありますか。
回答)前回のディベートでも話したとおり、2020年に東京で6年生がインターネットいじめで自殺しました。
質問)委員会の前に何を準備するのですか。
回答)議題箱の回収や会場の準備などです。
質問)「なぜこうなったのか」と言う人がいるのは本当ですか。
回答)……。
質問)田喜野井小でも死んでしまう人が出るというのは、何人ぐらいですか。
回答)1~2人は出るのではないでしょうか。
質問)準備委員会も、「たきのいタイム」を使うのですか。
回答)はい。
質問)「なぜこうなったのか」と言う人が出ると言うが、いやならもう一度意見を出せばいいのではないですか。
回答)はい。
質問)トラブルとはどんなことですか。
回答)ひやかしや悪口などです。
質問)本当にトラブルが増えますか。
回答)はい。
![]()
賛成側が答えに詰まったのは、代表委員会そのものの経験がないことが大きいでしょう。想像を膨らませて、「こんなことをやったら、学校生活がもっとおもしろくなる」といろいろ調べたり、6年生になった自分たちの成長に関連づけて考えたりといったことを、子供たちに意識づけることが大切です。
熱が入った反論
質問を基に、子供たちは反論し合った。
⑤反対側第1反駁
⚫︎主張である「創意工夫」の意味について答えられないのだから、主張自体が認められない
⚫︎「創意工夫できるようになる」「その結果やる気が出る」の2つの根拠について答えられなかった。ということはこの2つができない可能性があり、できない場合、反対側の「不幸な結果」になる可能性がある。
⚫︎「先生の指導が中心になる」について答えられなかった
⚫︎「やる気が出る」根拠について答えられなかった
⑥賛成側第1反駁
⚫︎「いやならもう一度意見を出せばいいのではないか」という質問に「はい」と答えた。意見を出していいのであれば、こうしたトラブルは起きない
⚫︎「友達と遊ぶ時間がない」というが、休み時間以外でも遊べる
⚫︎計画委員は、「たきのいタイム」や休み時間を使うのではなく、委員会のときに準備をすればいい
⚫︎「休み時間に、友達と遊べない」と言うが、放課後など別の時間でも遊べる
⚫︎「なぜこうなったのか」という反論が出ると言うが、放送で伝えてくれるからそういうことは起こらない
⚫︎体育委員は毎日ではない
![]()
「計画委員は委員会のときに準備をすればいい」という反論は、子供たちが計画委員を実際に経験しているので、想像しやすかったのでしょう。そのため、具体的に反論することができました。現状の中で解決できるいい反論でした。
⑦反対側第2反駁
⚫︎「体育委員は毎日はない」➡︎ もともと毎日ではなく、「毎週忙しいのはどんな委員会なのか」という質問に答えたものだからおかしい
⚫︎「友達と遊ぶ時間がなくなってしまうなら、放課後に遊べばいい」➡︎ 休み時間は、みんなで交流を深めることが目的なので、放課後とはちがう
⚫︎「体育委員は毎日はない」➡︎ 毎日ではなくても、忙しいのは変わらない
⚫︎「不幸な結果が出るとは限らない」➡︎ 出る可能性がある
⚫︎出せば出すほど、不満も多く出る
⚫︎「1~2人は出る可能性がある」➡︎ 質問に対して「いいえ」と言ったので、かみ合っていない
⚫︎「計画委員会は委員会で決める」➡︎ 休み時間を絶対使わないとは限らない
⚫︎「死ぬ人がいるとは限らない」➡︎ 傷つく人はいる
⑧賛成側第2反駁
⚫︎「創意工夫の意味が答えられない」➡︎ 答えられなくても賛成側の全員がわかっているし、植本先生も簡単に意味を説明した
⚫︎「創意工夫の意味が答えられない」➡︎ とっさに答えられなかっただけで、立論にはちゃんと書いてある
⚫︎「『先生の指導が中心になる』というデータがない」➡︎ 普段の授業のように、「今日はこれをやります」と先生に言われて動いている
⚫︎「根拠がなくて不幸になる」➡︎ 創意工夫できればみんなで協力できる
⚫︎「責任感を持つとは言えない」➡︎ 創意工夫していけば、自分たちで完成させたいという気持ちが生まれる
![]()
「委員会活動は先生に言われたことをやっていたけれど」という立論や反論が出ました。
“優等生” であれば、疑問も持たずに、言われたことをこなすでしょう。ディベートでこういう発言が出てきたのは、無意識ながらも、論題を通して、自分たちの学校生活を見直そうとしていることの表れです。教師は、地道な話し合いの中で考えさせる場をつくり、議論していることをほめることが大切です。
フローシートを基に、全員で判定
ディベートが終了すると、植本先生が、
「自分のチームが勝ちたい気持ちはあるだろうけれど、今日の判定は、今、記録した自分のフローシートの流れを見て、どちらの方が優勢だったか、その理由を考えて決めてください」と指示した。
子供たちは真剣な表情で、自分のフローシートを見ながら判定。理由を書き込む鉛筆の音が教室に静かに響いた。
結果は……。
賛成側……0人
反対側……29人
各班で理由を話し合い、発表した。
賛成側の子
⚫︎反対側は質問にも答えられているし、賛成側の反論はかみ合っていなかった
⚫︎反対側は質問に答えていたから
⚫︎賛成側は反論もかみ合わず答えられないことも多かった。反対側はちゃんと答えられていた
反対側の子
⚫︎賛成側もよかったが、質問に黙り込んだり、微妙な「はい」があったりした
⚫︎賛成側の答えは、矛盾していた
⚫︎答えていなかったにもかかわらずかみ合っていなかった
⚫︎創意工夫の意味を全員わかっていると言ったが、ちゃんと説明していなかった
![]()
判定の中で「賛成側もよかったが……」と前置きをして発表する子がいました。
勝敗があるディベートでは、相手のことをほめる言葉は基本的に出てきません。しかし、何度か経験するうちに、「いいよ、いいよ」「そうだよね。でも、ちょっと待って」など、不思議とクッション言葉が出てくるようになります。
ディベートでは、真実を追究するために、あえて窮屈なルールの中で話します。けれどもゲームを離れれば、お互いに尊重し合います。だから自然にクッション言葉を使うようになるのでしょう。ディベート終了後の握手も、クッション言葉につながっているのかも知れません。
何度か経験する中で、真剣にぶつかり合ったからこそ、思いやりや認め合いにつながってきたのでしょう。
判定後、植本先生が、
「このゲームは、かなり難しかったと思います。だけど、みんながカバーし合っていることがよくわかりました。質問や反論も、他の人とかぶらないように考えていました。これは、毎日行っているほめ言葉のシャワーの積み重ねと通じているものがあるな、と思います。全員が、言おう言おうとして待ちかまえていて、自分の役割を果たそうという姿勢が伝わってきました」と感想を述べた。
菊池先生から植本先生へのメッセージ
子供の言葉は、教師の日頃の言葉に強く影響されます。このディベートでも、「創意工夫をすれば、自ら考えて行動するようになり、成長する」という立論が出されました。植本先生が、子供たちに「成長」「自ら考えて行動する」という言葉かけをしてきたからこそ、こうした話し合いの場でも、子供たちが使ったのでしょう。
言葉を羅列するだけでは単なる模倣であり、まだその子の血となり肉となっているわけではありません。大切なのは、子供たちがその言葉を使うことではなく、その先を見ていくことです。
ディベートは形式的に、“賛成”“反対”の立場が決まっているので、子供たちは勝つためにいろいろな意見や反論をひねり出します。その中には、普段の授業の模範解答では出てこない発言も出てきます。
役割が明確なので、あまり発言をしない子も発表しなければならない場面がありますし、普段の授業では集中が途切れがちな子が見事に切り返す場面もあります。ディベートでは、普段の授業では見られない子供たちの様子が見られます。一人一人違った多様な意見が出てくることで、よりダイナミックなディベートになっていくのです。
教師が示すキーワードを使った上で、さらに本音の言葉を導き出す。教師は、そこをその子らしさとしてほめることが大切です。言葉が心を育て、人を育てていくのです。

菊池先生の最新刊、今までにない提案性を孕んで発売中!
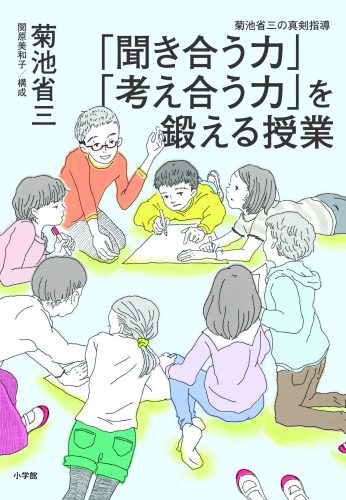
2025年3月22日のリアル対面セミナーの記録動画(有料)を公開中です!
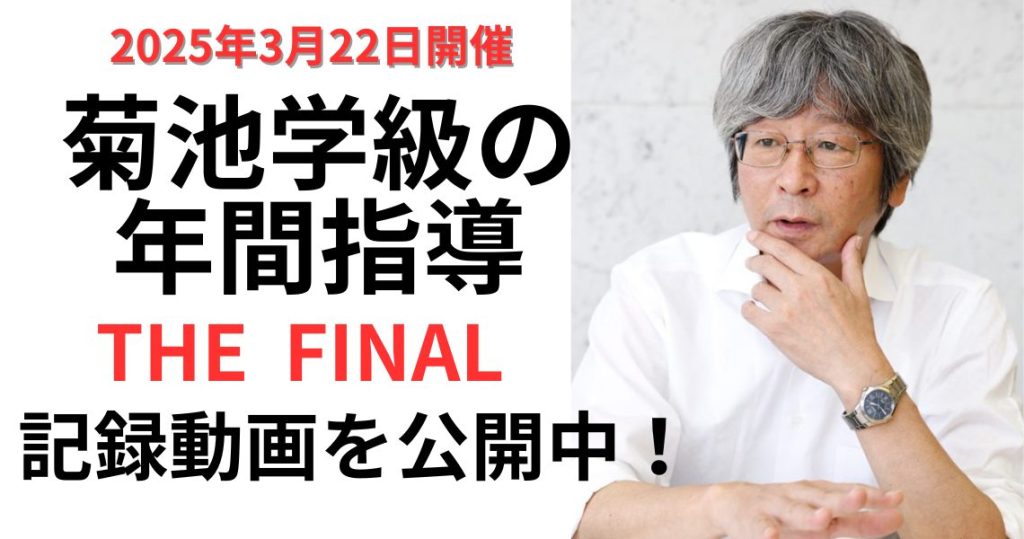
↓2025年3月発売の最新刊
「聞き合う力」「考え合う力」を鍛える授業
好評発売中です!
↓若手が菊池実践を学ぶために最適の単行本
「一人も見捨てない!菊池学級 12か月の言葉かけ」 発売中です!
取材・文/関原美和子

Profile
きくち・しょうぞう。1959年愛媛県生まれ。北九州市の小学校教諭として崩壊した学級を20数年で次々と立て直し、その実践が注目を集める。2012年にはNHK『プロフェッショナル仕事の流儀』に出演、大反響を呼ぶ。教育実践サークル「菊池道場」主宰。『菊池先生の「ことばシャワー」の奇跡 生きる力がつく授業』(講談社)、『一人も見捨てない!菊池学級 12か月の言葉かけ コミュニケーション力を育てる指導ステップ』(小学館)他著書多数。