学び合う集団を育てる授業づくり 指導案作成の6つのステップ|新任教師のための学級経営講座 #9

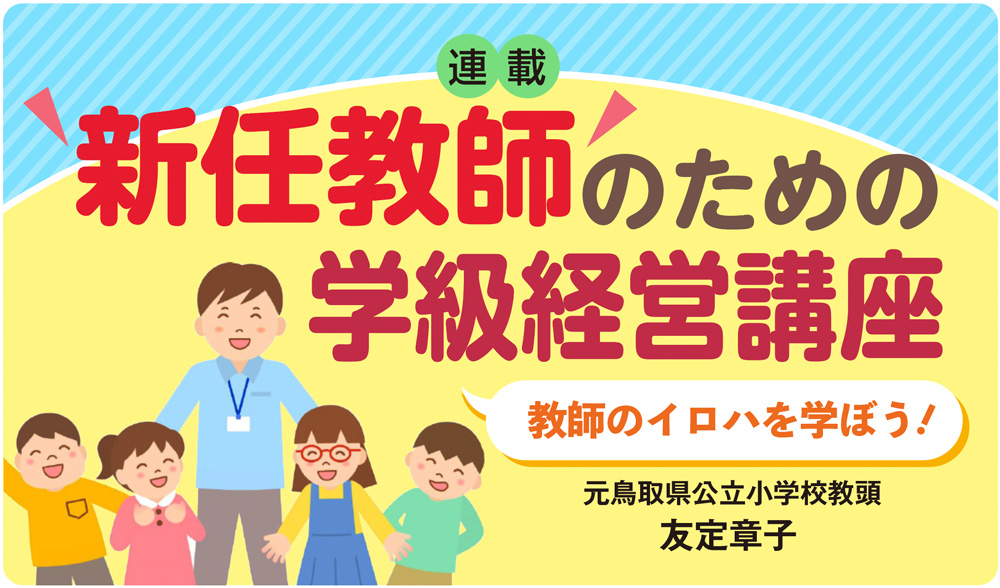
初めて学級担任になった新任教師にとって、「学級経営」は不安なもの。そこで、学級経営の基本が学べる連載をお届けします。毎月の準備や進め方などをその月の学校行事なども絡めながら紹介。鳥取県の公立小学校で、若手教師の育成に尽力してきた友定章子先生が、新任教師でも分かりやすいように解説します。今回は、子供たちが共に学び合える授業づくりの方法について解説します。
執筆/元鳥取県公立小学校教頭・友定章子
目次
はじめに
2学期になると、校内授業研究会や校外でたくさんの授業研究会が行われます。授業研究会は、教師の授業改善、教師の授業力向上を目指した日本独特の文化です。日本ではどの学校種の教師も授業研究会に参加した経験をもっているでしょう。世界でも「Lesson Study」として認められ、教師教育に欠かせない研修スタイルとして研究の対象になっているほどです。
授業研究会では、授業する立場で観てもらうこともありますが、授業を観察する立場で参加することのほうが多いものです。その際、自分の授業のデザインの仕方と比較しながら、授業者がどんな工夫をしているのかに着目して観察すると、自分の授業改善につながると思います。
今回は、子供たちが主体的に学ぶ授業デザインや「学び合う集団」をつくるためのポイントについて、お伝えします。
授業をデザインするために
日々の指導案を作成するには、以下の6つのステップで行うとよいでしょう。
①教材研究は目の前の子供の実態に合わせて考える
「教材研究って何をすること?」と感じたことはありますか? 先生方によっていろいろな考えがあるかもしれませんが、どの教科であっても、まずは教科書や指導書を読んでみることです。この単元でどんな力を付けたいのか、子供たちに何を考えさせればよいのか、単元の学習が終わった時に、どんなことができる子供たちになっていなくてはならないのかということを分析(読み解きます)します。指導書には、板書計画や主な発問なども示されているので、日常の授業ならこれらを参考に授業を進めてもよいでしょう。
ただ、授業研究会の授業者になったら、もう少し深く教材研究をしてみましょう。文部科学省の教科ごとの学習指導要領解説を読んでみたり、他の会社の教科書を読んでみたりすると、子供たちが学習する目的となる背景が見えてくると思います。算数科や理科では、学習の系統性(今までにどんなことを学んでいるのかという既習やこれからどんなことを学ぶのかという未習)を知ると、授業を組み立てる上で、本単元の目標がより明確になると思います。
もう1つの教材研究の方法は、他の先生の指導を参考にすることです。先輩方の指導案を参考にしたりネット上の指導案を参考にしたりすると、少しずつ具体的な授業のイメージがもてると思います。ただ、この時に注意すべきは、その指導案がどんなにすばらしくても、実際の自分の授業でうまくいくとは限らないということです。なぜって、指導案を書いておられる先生との経験知が違いますし、目の前の子供の実態が違うからです。他の先生の指導案を読むのは、あくまで参考にするためです。
②単元計画を立てる
教材について、分析して分かった学習の目標をもとに、単元計画を立てます。教科書にも標準的な指導時数が示されています。ただ、この時数は、あくまでも目安です。その時間数を守りなさいというものではありません。自分の学級の子供たちなら、この1時間扱いでは難しいのではないかとか、2時間扱いになっているけど1時間でできてしまいそうだとか、やっぱり目の前の子供たちのことを想定して単元計画を立てましょう。
私が一番大事にしているのは、単元の第1時です。この単元について、なぜ学ぶ必要があるのか、子供たちが単元のゴールに向かって興味をもち、主体的に学ぼうとするスイッチとなるような学習課題との出合いを工夫したいものです。
③子供たちの好奇心をかき立てる問題(課題)提示
単元計画と同時に、学習目標が明確になるような問題提示や課題提示、1時間ごとの学習のめあてとまとめを考えます。この時、学習目標は、教師の言葉で書き、まとめは、子供の言葉で考えます。そして、その言葉を引き出すためのめあてを考えます。
例えば、4年生の算数科。概数の学習では、概数にする方法を教えたり、概数の計算方法ができるように教えたりすることはもちろん大切ですが、なぜ、概数にしなければならないのか、なぜ、概数で計算する必要性があるのかを考えることもなく授業をしてしまいがちです。
私は、第1時に「近くのスタジアムでサッカーの試合を行う予定がある。あなたが主催者なら、チケットを何枚印刷する? お弁当はどれくらい用意する? ジュースやお茶などの飲み物はどれくらい用意する?」と問いました。身近な場面を想定することで、なんだかおもしろそう、やってみようと考えるきっかけになります。また、推測するためには、多く見積もったり少なく見積もったりするなど、概数で考える必然性が生まれ、自分の考えを根拠として示しながら学び合いが深まりました。
④全ての子供の実態把握と支援を!
授業をする上で事前に発問を考えますが、それだけでなく、発問した後の子供たちの反応を予想します。発問の意図をとらえて的確に答える子供ばかりではなく、きっと答えられない子供や、困って反応ができない子供もいることでしょう。
だからこそ、答えられない子供や困っている子供に対する支援を考えて授業に臨みます。答えを導くためのヒントではなく、その子供が「そうか」と手を動かすための言葉を考えます。既習事項を確認したり、どこに着目すればアイデアが浮かぶのかを声かけしたりすることで、止まっていた手が動き出すような支援だけでなく、できている子供の思考も高まるような支援をしていきましょう。
つまりは、全ての子供たちに支援が必要なのです。「学級のあの子は、こんな反応をするだろうから、こう言おう」「あの子は止まってしまうだろうから、こんな言葉をかけてみよう」と、目の前の学級の子供たちを想像して具体的な支援の言葉を考えておきます。
⑤一人一人を評価できるよう工夫する
1時間の授業の評価は、授業が終わった後、一人一人の子供の思考がどう変化したか、理解できたかどうかを確認するために行います。板書してあることと同じ内容をノートに写しているだけでは、全員が同じノートになるので一人一人を評価することはできません。また、グループで話し合っている内容について全てのグループの話合いを書き留めることや、一人一人の具体物の操作や観察の様子をとらえることはできません。
つまり、一人一人を評価するためには、工夫が必要なのです。私は、まとめの言葉は自分の言葉で書くように伝えたり、気が付いたことをメモしたりするよう促して、後でノートを確認しています。操作したことや観察したことは、必ずメモしておくように伝えます。
⑥授業後のゴールを手書きしてから指導案を作成する

授業をするための指導案はパソコンで作成しますが、私は、まず子供に書いてほしいノートや板書を自分の手で書いてからパソコンに向かいます。算数なら自分で解いてみる。国語なら文字数を考えながら黒板に書いてみる。社会はノートにまとめてみる。授業後の子供のゴールをきちんと書いてみることが大切だと感じています。
いきなりパソコンで指導案を書く前に、大まかな指導の板書計画や子供に書いてほしいノートを自分の手で紙に書いてみましょう。すると、子供の思考を想像したり、書くことへの配慮の必要性などを考えたりすることができます。

