<連載> 菊池省三の「コミュニケーション力が育つ年間指導」~3学級での実践レポート~ #20 徳島県石井町立石井小学校5年3組④<後編>

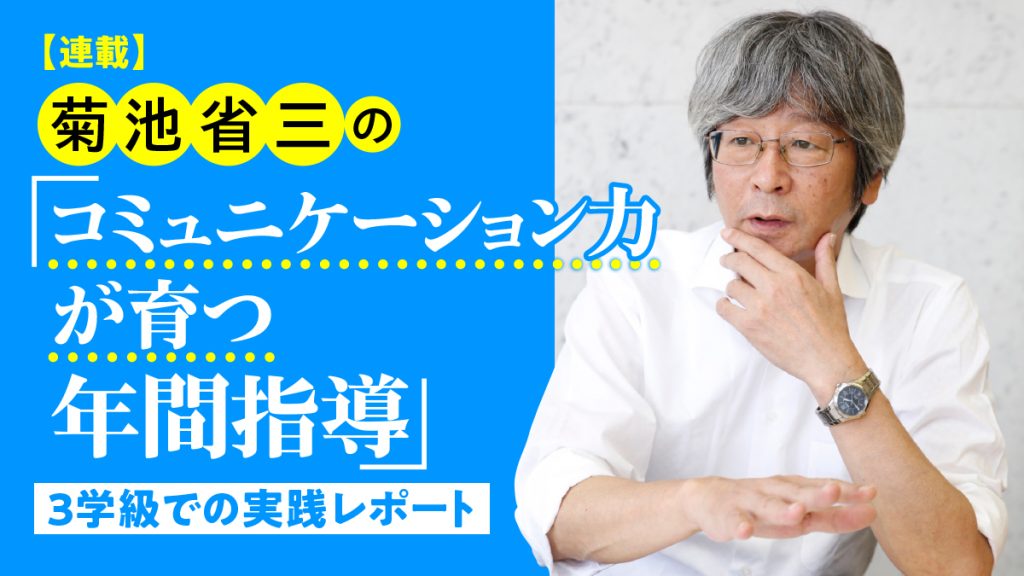
菊池実践を追試している3つの学級の授業と子供たちの成長を、年間を通じてレポートする好評連載。今回は、徳島の堀井学級(5年生)における2025年2月の授業レポートの後編です。菊池先生と堀井先生による、2時間続きの熟議の合同授業の記録です。

目次
熟議におけるファシリテーターの役割
「日本一の教室にするために、残り20日で自分は何をするべきか」のテーマで、班ごとに課題を出し合った。
ある班では、「相手軸に立つ」というキーワードでまとめたカテゴリーが抽象的すぎて、解決策に行き詰まっていた。その様子を見ていた堀井先生が、
「(模造紙に)貼っていることだけで考えずに、みんなで具体的な意見を出し合って、模造紙に書き込んでいってもいいね。
今、みんなが行き詰まっている『話し合うとき、難しい言葉で話してしまう』『難しく考えすぎて、話がまとまらない』ということが、そのまま『相手軸に立つ』のテーマにできるんじゃない? それを解決するために、最近みんなが『ここまでわかりますか?』と確認しながら発表していることとか、言い方をこういう風に気をつけるとか、具体的なアイデアが出てくるのでは?」とアドバイスした。
すると、ファシリテーター役の男子が、
「それなら、『みんながわかりやすくて考えやすい話し合いにする』はどうかな?」と他のみんなに問いかけると、みんながうなずいた。そこで堀井先生がAさんに、
「どう?」と話しかけると、彼女も納得したように大きくうなずいた。
「ちょっといい?」堀井先生がAさんに確認を取ってから、班の子供たちに話しかけた。
「『相手軸に立つ』ことに関連するんだけど、さっき、『自信を持つことが大切』だとみんなが話し合っていたとき、ファシリテーターのB君がAさんに、『Aさんも何かあったら言って』と促していたよね。僕も『Aさんが話し合いに参加できていないのかな?』と思って、何気なく『Aさんはどう思う?』と話を振ったら、Aさんが涙ぐんでしまった。
Aさんの内面とか、それまでの話し合いの流れをよく知らないまま、よかれと思って声をかけてしまったことで、プレッシャーを与えてしまった。相手軸に立っていなかったということです。こういう場面も含めて話し合ってほしい」
堀井先生の話に続けて、菊池先生が、
「相手の状況を知らないと、相手の気持ちや考えとずれたことを言ってしまう場合があります。例えば、『ある人の言葉遣いが悪いこと』を課題に挙げたとき、なぜその人の言葉遣いが悪いのかを知らないと、『直すべきだ』と攻撃して、相手とぶつかるだけだよね」と話すと、みんながうなずいた。
![]()
ファシリテーターの男子は、「番と平等」を目指して班のみんなに声をかけたものの、つい力が入りすぎてしまいました。
内容に追いつけず、話し合いについて行けない子がいるとき、ファシリテーターが無意識のうちに、一つの方向に引っ張っていこうと気負ってしまうことが多々あります。形式的な平等は保とうとするけれど、ゴールありきで進めてしまうのです。
みんな平等に言えるようにする。でも決めつけない――相手の表情や話し合いの内容を読みながら進めていくファシリテーターの役割は重要です。ルール化されているディベートに比べて、話し合いの流れが動く熟議は、難易度が高いのです。
教師自身の失敗をエピソードで語る
課題を出し合った後、「自分はどう向き合っていくか、どうしたいか」を考え、各々がピンクの付箋紙に書き込んでいった。
堀井先生が、再びAさんに確認を取り、先ほどの“失敗談”を今度は学級全員に話した。
「さっき、班を回っているとき、Aさんが発表していない様子を見て、状況をよく知らないまま、『Aさんはどう思う? どうぞ」と話を振ってしまい、Aさんが何も言えずに涙を流す状況を作ってしまいました。彼女にとっては、『自信を持つ』という課題テーマが大きすぎて、どう言えばいいのか悩んでいたそうです。そして、『何も言えない自分が嫌だな』と考え込んでいたんです。そんなタイミングで、僕が尋ねてしまったんだね。
先生はよかれと思って聞いたんだけれど、じつはAさんがどんなことを考え、なぜ発表しないのか考えるところまで至ってなかった。相手のことを考えずに声をかけてしまって、とても反省しました。
今、僕がピンクの付箋に書くなら、『相手の表情や状況、流れを見て声をかける』『相手のことをちゃんと見てコミュニケーションを取る』です」
堀井先生の告白に、みんなが真剣な表情で耳を傾けた。
![]()
熟議の中で、子供たちは「相手軸に立って話を聞く」と何度も発言していますが、実感として捉えているわけではありません。こうした場面では、教師が具体的なエピソードを示して、子供たちに印象付けることが大切です。
堀井先生が、自分がしてしまったばかりの“失敗”を話したことで、より強く子供たちの心に残ったのではないでしょうか。
このように、“失敗”も活かすようにすることが、コミュニケーションの授業の本質です。

