小3理科「磁石の性質」指導アイデア
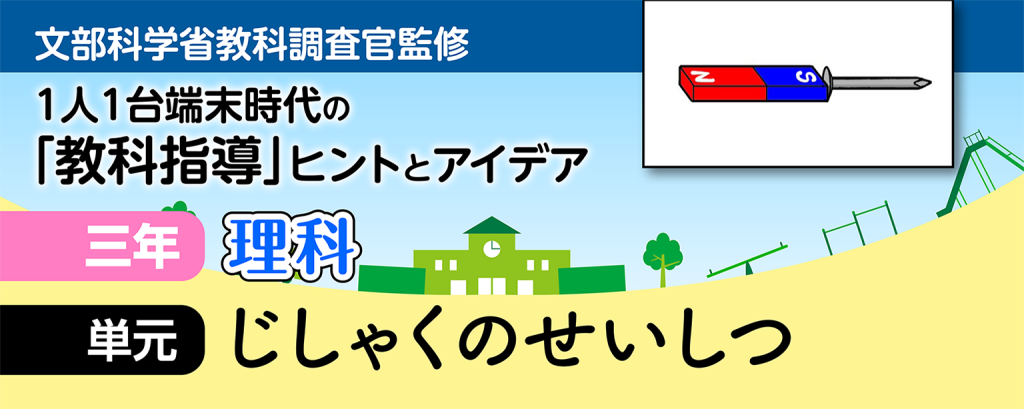
文部科学省教科調査官の監修のもと、小3理科「磁石の性質」の板書例、教師の発問、想定される子どもの発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。
執筆/福岡県北九州市立門司中央小学校教諭・三戸岡洋平
福岡県北九州市立深町小学校指導教諭・鈴木寛人
監修/文部科学省教科調査官・有本淳
福岡県北九州市立湯川小学校校長・齋藤貴志
福岡県北九州市立青山小学校教頭・中富太一朗
目次
単元目標
磁石を身の回りの物に近付けたときの様子に着目して、それらを比較しながら、磁石の性質について調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に差異点や共通点を基に、問題を見いだす力や主体的に問題解決しようとする態度を育成することがねらいである。
評価規準
知識・技能
①磁石に引き付けられる物と引き付けられない物があることを理解している。
②磁石に近付けると、磁石になる物があることを理解している。
③磁石の異極は引き合い、同極は退け合うことを理解している。
④磁石の性質について、器具や機器などを正しく扱いながら調べ、それらの過程や得られた結果をわかりやすく記録している。
思考・判断・表現
①磁石の性質について、差異点や共通点を基に、問題を見いだし、表現するなどして問題解決している。
②磁石の性質について、観察、実験などを行い、得られた結果を基に考察し、表現するなどして問題解決している。
主体的に学習に取り組む態度
①磁石の性質についての事物・現象に進んで関わり、他者と関わりながら問題解決しようとしている。
②磁石の性質について学んだことを学習や生活に生かそうとしている。

