【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第67回】今どき教育事情・腑に落ちないあれこれ(その8) ─「個人」と「国家」・「社会」の関係─

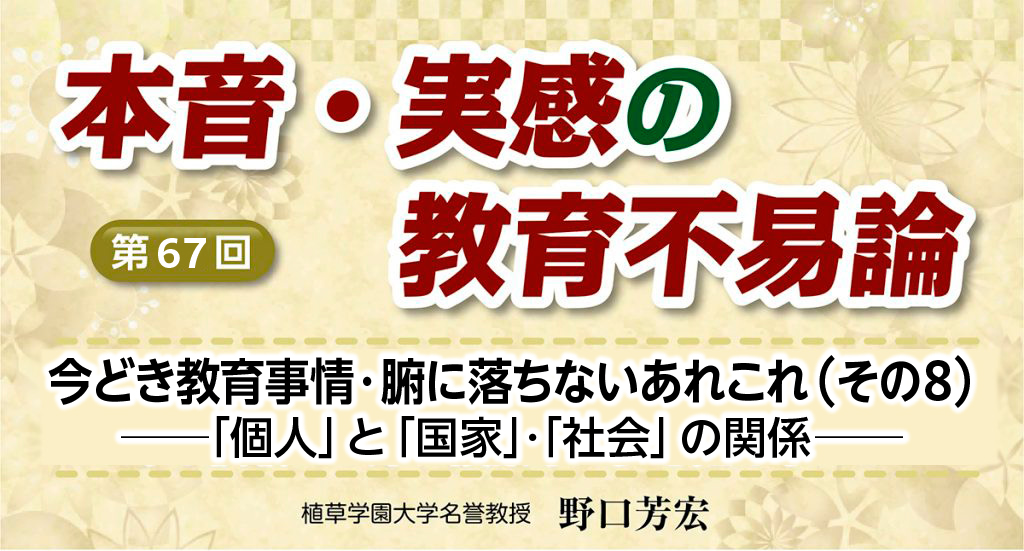
国語の授業名人として著名な野口芳宏先生が、60年以上にわたる実践の蓄積に基づき、不易の教育論を多様なテーマで綴る好評連載。今回のテーマは、【今どき教育事情・腑に落ちないあれこれ(その8)─「個人」と「国家」・「社会」の関係─】です。
執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年以上にわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。

目次
1、国家と個人のどちらが大事か
タイトルのような問いを、一般社会人や教育にかかわっている人に向けてみる。読者諸賢は「国家」とするか、「個人」とするか。自分の立場を決めてから読み進めて貰いたい。自分の選んだのが「正解」と考えるのは当然だが、それは双方に言える。
驚いたことに、どこで問うても圧倒的に「個人」が多い。「驚いたことに」と私は書いたのだが、私のこの書き方、言葉自体が多くの人にとっては「驚いた」ことになるらしい。お互いに、冷静になって考え合いたいことがらである。
私の論理は単純、かつ明快なものだ。「個人」の存在などというものは、国家が危機に陥れば、その途端に風前の灯同様に翻弄され、安否さえもが個人の努力を超えて保障されない。そうなれば、その危難、苦難からは逃げるしかない。各地に見られる難民の姿がその実相を知らせている。ロシアの侵攻を受けることになったウクライナの国民の苦しみは無言の教示になるだろう。
こんな私の思いを、このように自由に書けるという「個人」の存在は、それを許し認める「日本国という国家」が表現の自由を保障し、許し、認めているからだ。これがひとたび崩されて「言論弾圧」でも始まれば、立ち所に私は捕らえられ、口を封じられるだろう。その弾圧が日常化されている国家が、我々、日本の近くに存在している。改めて日本人であることの有り難さや幸せを思わずにはいられない。
さて、先の問いだが、「国家よりも個人が大事だ」と考え、答える人の方が圧倒的に多いというのは大変な「誤認」「誤解」ではないのか。日本という国家が安定を長く保ち、戦禍を遠ざけ、平和を保っているというその得難い恩恵を忘れている。我々の日々が余りに幸せなので、呑気な平和呆けになり、「国家」の存在の有り難さを忘れさせているのではないか。このような私の考え方の方がおかしいのか。
2、教育現場の「個人」観の歪み
親しい教員仲間に用事があって、その職場の事務室に電話をかけたところ、三月末に転出したと言う。そこで転勤先の学校を問うたところ、「個人情報だから教えられない」との返事だった。個人情報ではあるが、同時にそれは公情報でもある。彼は公務員であり、公務に就いている。国家、社会にかかわる仕事をしているのだから、転勤情報は新聞にも掲載して、広く知らせている。「個人情報」の一面のみにこだわって「公的情報」の一面を忘れた不親切だと思うのだが――。
これも親しい間柄の人が入院したというので、病院に「まだ入院しているか」と問うたところ「個人情報は教えられない」とのこと。それが病院の方針だそうだ。
朝の学校に電話が掛かってきた。「子供が、学校に行きたくない、と言っているので今日は休ませます」とのことだったそうだ。
「子供の人権」「子供個人の考え方」を尊重した親の立場からの連絡とも言える。だが、親としては、「教育」は「国民の義務」であり、「親は、子の教育について第一義的責任を有する」存在である。自分の子供が、学校に「行きたくない」と言っているから休ませるのは妥当なのか。余りにも「個人」を尊重しすぎてはいないか。
「子供の主張」の別の一例だ。学年でバスを借りての遠足に行った帰りのことだ。
ある子供が「帰りはバスに乗りたくない」と言い出した。言い出したら引かない子だそうだ。家の人に電話をしたところ「迎えには行けない」とのことだった。そこでやむなく、校長に相談したところ、「タクシーで送るしかないだろう」とのこと。そのようにして自宅まで送り届け、タクシー代は学校持ちだったそうである。「バスに乗って帰りたくない」という「個人」の意志がかなりの手間と出費と心労をもたらしたまれな一例だが、前例となって増えそうにも思われて寒々しい気持ちになった。「個人」が、「公」や「国」よりも大事にされる時代、と言えなくもなさそうだ。
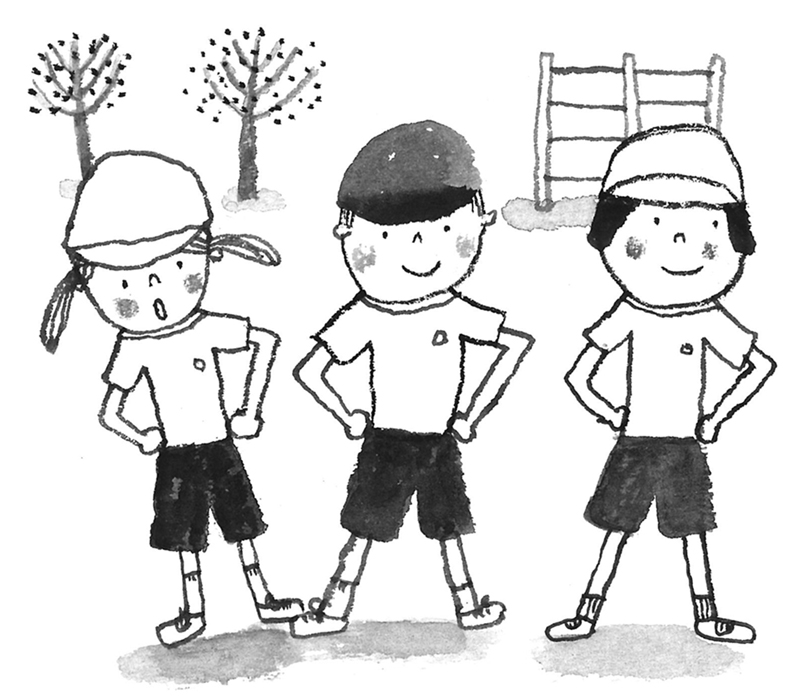
3、個人名と個人の肖像権
近頃個人の作文や発言に個人の名前が書かれなくなっている。KとかTとかいう表記が多い。およそ、イメージが描けない。「個人名は出さないように」と、上司からの指示もあるそうだ。
そう言えば、住所録や電話連絡網も廃止されて久しい気がする。卒業アルバムも作らない学校が増えているとも聞くが本当だろうか。段々、世の中がおかしい方向に動いていくようで、高齢者としては淋しい思いになる。
ある担任が、自分のクラスの授業をビデオに撮影し、翌日サークル仲間でその授業を見合いながら授業の検討会をしたいと企画した。念の為に、と校長に報告したところ「子供にも肖像権があるから、それは公開するな。止めた方がいい」と言われて中止になった、という話を聞いた。
馬鹿馬鹿しい話だと私は考えたので、知人に「どう思うか」と意見を求めると、意外な答えが返ってきた。
「その一場面にある子供の発言がある。その発言が面白かったからとそのワンカットをSNSに流したとなると、その拡散は止めようがなく、あっと言う間に広がってしまう。そういう時代だから、後難を案ずる校長の思惑も分からないではない」とのことだった。
何と不便な時代になったことだろう。子供は、本来学校に行くのが楽しみで、学校を休むなどということは、異常であり、残念であり、淋しいことであった。また、先生との勉強も、もともとは無知、未熟な存在が、人間として必要な様々な知識や情報や技術を教えて貰える有り難い場所であった。少なくともそれは「善い営み」の場であり、公開を拒んで隠すようなことはなかったはずである。
昔の田舎の学校には門扉などは無く、いつでも、誰でも、犬や猫でさえもが、自由に出入りしていた「開かれた場」であったのだが、今は常時門扉が閉ざされ、全ての学校が刺股を備えているようになった。因みに「刺股」とは「江戸時代、罪人を捕らえるのに用いた三つ道具の一つ。木製の長柄の先端に鋭い月形の金具をつけた武器。喉頸にかけて取り押さえる」と広辞苑にある。「学校に刺股」、「世は不信」の時代になってきた。
もう一つ付け加えれば、田舎ではどんなに遠くても子供は自分で歩いて通学したものだ。雨でも雪でも、その子なりに頑張って自分の足で通い続け、それが昔からの当然の通学形態だったのだが、今はボランティアの老人が黄色い旗を持って通学を見守るのが普通の光景、風景になってきた。世の中がそれだけ物騒になってきたのである。文化や文明、学問や技術の進歩、進展とは一体何なのだろうか、とも考えてしまう。
4、「不信感」が「不安」の根源
「昔は良かった」「昔の良き時代」などという言葉は、「老人の口癖」「老化のサイン」などと言われそうだが、そう簡単に言って済むことではない。日本は「世界で一番治安の行き届いた国だ」とずっと言われてきていたように思うのだが、もはやこの言葉も通用しないだろう。
私は、人間が日々生きていく上で、最も大切なことは「安心」ということだと思っている。「心が安らぐ」「安らいだ心でいられる」ということである。「安心」の対義語は「不安」である。これは不幸な状態だ。疑いや妬(ねた)みや嫉(そね)みや怒り。心配や恐れに苛(さいな)まれてもいるのが「不安」である。「昔は良かった」というのは「安心だった」ということだ。無論、戦時下の時代に不安が無かった、とは言えない。だが、不安の質が少し違うと思う。昔の「不安」は共有されていた。不安も、共有されていれば協力して安心を求めようとする。現代の「不安」は、共有されず、協力が生まれない。今の不安には、個別、孤立、孤独が付きまとう。
個々が、我が身だけを大事にすることになり、他者や社会や国家を軽んじ、排除し、関係や繋がりを断つようになった。さらに言うなら、他者への「不信」、自分のことは自分で守るしかないという悲しい諦めと失望の思いが潜在的に密かな肥大を始めているのだ。
そして、それを促しているのが現代の教育界の風潮である。「プライバシーの侵害」という言葉は「不信感」を育てる魔力を持っている。家庭訪問の禁止、電話連絡網の廃止、転勤先も、入退院も教えない。授業の様子も、住所も見せない、知らせない。家族構成も問わないように。友達の家には気軽に行くな、友達を自分の家に気軽に連れてくるな、入れるな。
また、個性重視、そのままでいいんだよ。多様性への寛容。教師側からの押しつけや教えこみや詰め込みは止めよ。叱ってはいけない。子供まんなか。子供は無限の可能性を秘めている。
このようなまことしやかな美しい言葉が受けている。広まっている。広めている。その結果はどうか。苛めは減ったか。不登校は減ったか。ひきこもりは減ったか。子供の自力の学びは伸びたか。子供の読書力は伸びているか。──何一つ良くなってはいない。
そして、慢性的な教員不足の果ては教員志望者の大幅な減少である。減って貰いたいことは減らず、増えて貰いたいことが増えない。──どこかが、根本的におかしいのではないか。
5、さらなる根源は「個」への過信
次の主張についてどう受け止めるか。紙幅の都合上、抄録する。熟議、玩味を望む。
「憲法第13条は『すべて国民は、個人として尊重される』というが、しかし尊重されるべきは、そうした『個人』としてのあり方だけに限られるのだろうか。海上の氷山が実は氷山の一部でしかないように、『個人』も人間のあり方の一部でしかあり得ない。……いつの間にか人間を『個人』としてしか見ない考え方に陥らされているのではないか。……人間には例えば『国家の一員』としてのあり方もあれば、『社会の一員』『家族としての一員』としてのあり方もある。……結婚をするもしないも『個人の自由』、子を持つも持たぬも『個人の自由』(なのか)。……今や、こうした人間観はほとんど教えられることもないのが現実でもある。この風潮を正すにはよほどの覚悟が必要だが、しかしこのままでは国家、社会、家族が滅んでしまう。われわれは力を尽くし、これを説いていくべきなのではないか。」
これは私が愛読している、ある月刊誌の巻頭言の一部分である。常々、私の考えていたことに近い論調なので強い共感を持って読んだ。私の考えが、決して独断ではないのだと、背中を押された思いである。
ついでながら、引用されている法文は、憲法第13条の冒頭の一文である。その書き出しは「すべて国民は、」である。「国民」というのは「共通の文化、社会経験を持つという想定のもとに、政治的な統一組織を作り上げた人間の集団」(広辞苑)とある。肝要なことは、単なる「人間の集団」ではなく、「共通の文化、社会経験を持つという想定のもとに」という限定である。これが「国民」である。「個人として尊重される」のは大前提として「国民」であることが必須要件であることを確認したい。
執筆/野口芳宏 イラスト/すがわらけいこ

