実験方法を子ども自身が考えるための第一歩~「解決の方法を発想する」子どもの見取りと指導~【理科の壺】

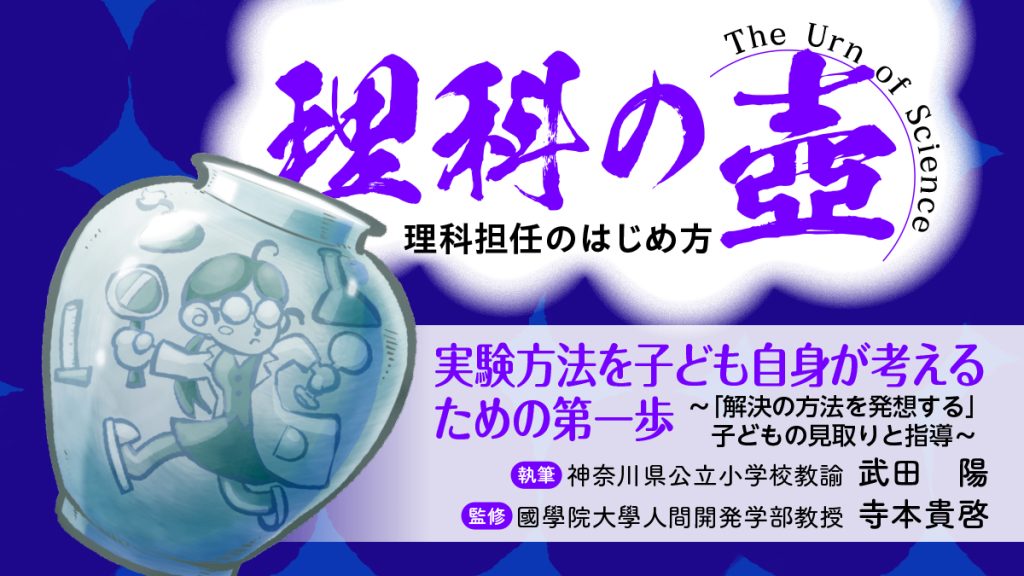
「解決の方法を発想する」というのは、言い換えれば「子ども自身が実験方法を考えられるか」です。子ども一人一人に実験方法を考えさせたいのですが、「実験方法を考えて書いてね」と言っても、すんなり書けない場合が多いです。子どもが自分で書けるようになるには、指導が必要なのです。
そして、何ができていればいいのか、何を指導すればいいのかについては「積み重ね」です。時間をかけて少しずつ指導するわけです。子どもたちの実態をしっかりと見取って、的確な指導をしたいものですね。
優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/神奈川県公立小学校教諭・武田陽
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
はじめに
日々の暮らしの中で、どんな人も、些細なことから大きなことまで様々な問題に直面します。
そのようなとき、小学校理科における問題解決の学びは、大きな役割を担っていると考えます。
「直面する問題に対し、解決する方法を考えて、生活をより良くしていく力」こそ、理科で子どもたちに身に付けてほしい力だからです。
年度初めによく、「初めて理科を教えます」「今年から理科専科になりました」という方々から「解決の方法を発想する力はどのように育成していくの?」という声があがります。
そのような疑問を抱いたら、まずは、めざす資質・能力が育成された子どもの姿を想定します。
その上で「学年集団としてどのような学習経験を積んできたか」「一人一人の到達状況はどうなのか」を見取ります。見取りを基に指導の見通しをもち、「今」目の前にいる子どもにとって必要な指導を考えていくことを大切にしましょう。
1.「解決の方法を発想する」子どもの姿とは?
今回は、目指す子どもの姿として
「子ども自身が、問題に対する予想を解決するための方法を発想することができる」
について考えてみます。解決の方法を発想するというのは、「実験方法を計画する」とも言えます。
ここでは、理科における「解決の方法の発想」を次の2つに分けて考えてみます。
⑴「何を使うか」→実験器具等を考えること。
⑵「どのように使うか」→条件を整理して方法を考えること。
⑴「何を使うか」
教師の心持ちとして、指導をする時点で子どもたちにどこまで委ねることができるかを考えることが大切です。子どもたちに委ねる幅を広げていくことで、資質・能力は育成されていきます。
前提として子どもたちに、実験器具の存在・実験器具の使い方・実験器具の保管場所などの知識があることが必要ですので、以前使ったことがあるものだと子どもたちに委ねやすいと言えます。
「子どもが実験器具等を発想しやすく、安全を確保できる単元」では、「何を使って、どのように調べるか」までを子どもに委ねてみましょう。
⑵「どのように使うか」
子どもの学習経験や到達状況は様々ですし、子どもたちにとっては目新しい単元もあります。
そのため、いつも「何を使って、どのように調べるか」を子どもたち自身に考えさせることができるわけではありません。
はじめて理科を教える先生から、次のような声をよく耳にします。
どんな実験器具を使えばいいか、子どもたちに教えてしまっていいですか?
例えば、子どもが今まで見たこともない器具を使う場合や、教師が子どもたちに対して、意図的に使わせたい器具がある場合は、教師から実験器具の提示をしてもよいでしょう。しかし、これから行う実験での使用方法までを具体的に教える必要はありません。実験器具の名前や基本的な使用方法だけを教え、今回の実験でどのように使えるのかを考えさせるのがお勧めです。
教師から実験器具等提示する場合でも、提示した実験器具を使って、②「どのように使うか」は子どもに委ねることで「解決の方法の発想する力」の育成につながります。

