<連載> 菊池省三の「コミュニケーション力が育つ年間指導」~3学級での実践レポート~ #3 高知大学教育学部附属小学校2年B組①<前編>

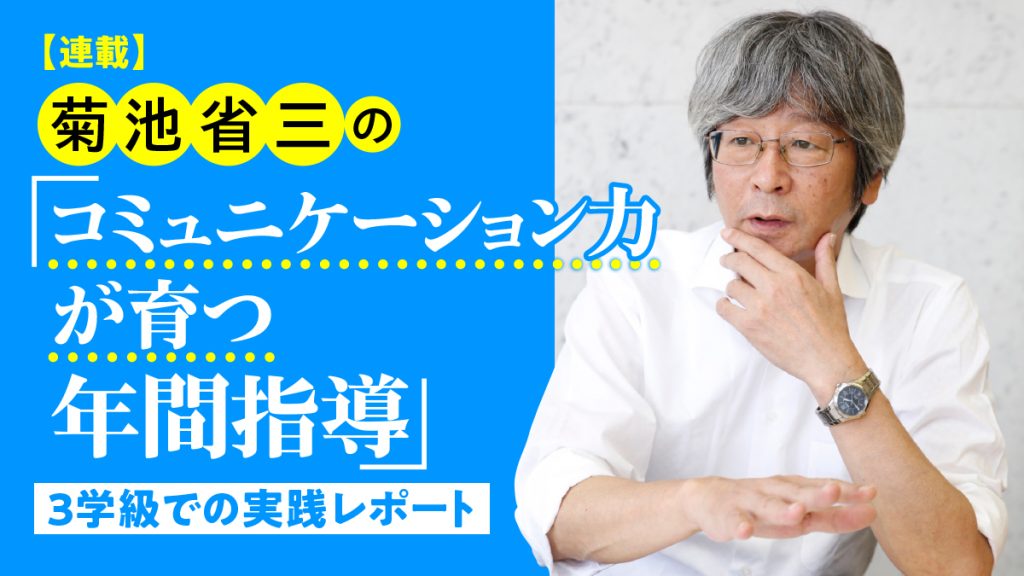
菊池実践を追試している3つの学級の授業と子供たちの成長を、年間を通じてレポートします。3学級の担任は、徳島の堀井悠平先生、高知の小笠原由衣先生、千葉の植本京介先生。それぞれの学級をローテーションでレポートします。 原則的に、菊池先生の授業記録+担任のコメントという構成。今回からは、高知の小笠原学級(2年生)における、6月上旬の授業レポートです。

目次
担任・小笠原由衣先生より、学級の実態について
子供たちに出会ってすぐ、発表する子が多く、「元気いっぱいの学級だな」と感じました。どの子も絵や字が丁寧で、学力が高い子が多いという印象を受けました。
一方で、強い言葉で友達を責めたり、自分の思いが通らないと「どうせおれが悪いんやろ」とすねたりする子がマイナスの空気をつくり出し、ほかの子供たちは彼らの言葉に遠慮し、あまり発言できないように見えました。
「先生、〇〇していいですか?」と頻繁に尋ね、顔色をうかがう子もいました。
そこで私は、1年後のゴールイメージとして、温かい言葉で関係性をつくっていけるクラスを目指すことにしました。
まず、新年度が始まってすぐに、<教室にあふれさせたい言葉><教室からなくしたい言葉>の授業をしました。言葉への意識を高めたいと思ったからです。
授業中でも学級活動でも価値語を使うように意識し、子供たちがイメージしやすいよう、イラストで価値語の意味を紹介するポスターを作りました。
週に一度ですが、成長ノートも始めました。授業では発言できなくても、成長ノートに価値語について書いてくる子がいます。「自分は成長していない」と否定的なことを書いてくる子には、「こんなところがあなたのいいところだよ」とプラスのコメントを入れて私の思いを伝えるようにしました。
「ほめ言葉のシャワー」にも取り組み始めました。4月から、朝の会や帰りの会で、私が何人かの子供のいいところを紹介していきました。
するとある日、「○○さんのいいところ、他にもあるよ」と言い出した子がいたので、「じゃあみんなも見つけられる?」と始めました。元々は2学期から始めようと考えていましたが、せっかくのこの流れをすぐに活用しなければ、と感じたからです。
「姿勢がいいです」「声が大きいです」など、まだありきたりのほめ言葉ばかりですが、全員が意気込んでいますし、「4時間目の図工で、○○さんは人に合わせるんじゃなくて、自分で考えて~~していました」のように、具体的に言える子たちが出てきました。その子たちをほめ、少しずつ全体に広げていきたいと思っています。
「○○しなきゃ!」と構えてしまうと、子供たちに対してつい硬い表情になってしまうことも多々あります。自分自身、もっと柔らかい表情や姿勢を意識していきたいと思います。
菊池先生による飛び込み授業
「ちょっと音を消してもらっていい?」
菊池先生が話しかけると、3時間目の授業が始まっても中休み気分が抜けずざわざわしていた教室が静かになった。
「今、先生の声が聞こえますか?」
菊池先生が少しだけ小さい声で声をかけると、子供たちがうなずいた。2列目に座っていた男子のところに行きながら、
「今日は、先生が好きなアニメを使って勉強したいと思います。楽しくやりたいので、彼のような姿勢を見せてください」
と話すと、子供たちの姿勢がピシッとなった。
「先生の好きなアニメです。わかったら、今よりもいい姿勢をしてね」
と菊池先生がアニメの主人公のシルエットが描かれた絵を見せた。
「あっ!」「はいっ!!」
子供たちが元気よく手を挙げ、1人が「アンパンマン」と答えた。
菊池先生が2枚目の絵を見せながら、
「みんなが生まれるずっと前、最初にアンパンマンが生まれたときの絵です。今と違うところがわかりますか?」と尋ねると、
「進化してるー」
と思わずつぶやく子も。
「そう。どんどん増えて進化しているんだ。毎年、200ぐらいキャラクターが増えるんだそうです」
と、昔と今のアンパンマンの絵を見せ、
「どこが違うか、隣の人と話し合って5個以上見つけましょう」と声をかけた。
子供たちは、2枚の絵をじっくり見比べながら違いを見つけ、隣の子と意見交換。
「先生がすごいスピードで当てるから、みんなは、パッパッと手を挙げるんだぞ。じゃあ、1個でも見つけた人?」
菊池先生が尋ねると、みんなが勢いよく手を挙げ、菊池先生が次々に指名していった。
●マント
●顔の形
●手
●色
●キャラクター感がある
座ったままで話そうとする子には、菊池先生が、
「立って言いましょう」と声をかけた。
●顔がでかい
指名された次の子が席を立とうとした時、何人かが待ちきれずに勝手に発言しようとした。菊池先生はその子たちに向かい、
「今は聞くとき。誰かが発表しているとき、他の人はしゃべりません。先生の声が聞こえるんだから、『聞こえません』とは言いません。これがベースです。じゃあ、みんなに聞こえる声でどうぞ」
と話すと、立った男子が、
「手」と答えた。
「それ、さっき出た!」 他の子が指摘すると、菊池先生が笑いながら、
「(他の子の発表を)聞いていないとだめだなあ」
と男子に話しかけた。
![]()
この男子は、自分が発した“雑音”のせいで発表者の声が聞こえないにもかかわらず、「聞こえません」と言い、我先に自分の意見を発表しようとしていたので、あえて後に指名しました。
この子は、自分と同じ意見を他の人に先に言われると、「同じだから、もう発表しない!」と不機嫌になる。そこで、「人の意見をきちんと聞きなさい」ではなく、「発表をしっかり聞いていないと、他の人の意見と重なってしまうよ」と伝えました。
「では、今手を挙げている人は全員立ちましょう。先生が順番に当てていくから、黙って聞く。相当速いスピードだぞ」
と、菊池先生が次々と指名していった。
●胸のマーク
●前のほうが痩せている
●目が昔は点々。今は丸い
●足の長さ
●昔は顔が小さい
●ベルトの色が、昔は黄色と赤。今は黄色と白
●マントの裾がギザギザ、今は緩やか
●頬全体の色
●むかしの絵は、色鉛筆で塗り絵ができそう。今はクレヨンで書いたみたい
●今のほうが背が小さい
発表の途中で2人が席を立った。
「最初は、手を挙げている人を立たせたけれど、あとから立った人がいました。2人はまだ言いたいことがあるから立ったんですね。自分が発表したいから自分から立って言う。これが2時間目で学んだ自由起立発表です。じゃあ、どうぞ」
●今のポーズは足が開いているけど、昔は閉じている
男子が前に出てきて、黒板の絵を見上げながら指さして発表すると、それまで授業に参加せず、ずっと折り紙を折っていた女子が急に立ち上がり、長い棒を探し出してきた。
菊池先生がその女子の隣に立ち、
「2時間目も今も、彼女が頑張っているところをほめたり、『もっとこうしてね』と注意してくれる人がいました。さっき彼女が急に席を立ったのは、前の男子がアンパンマンの絵を指すことができる棒を探しに行ったのかもしれませんね。友達のため、自分のために一生懸命頑張っているんですね」
とほめ、
「じゃあ、どうぞ」
とその子に対して発表を促した。
●こっち(昔の絵の下に書いてある『1976』)は数字だけど、これ(絵の下に書いてある『現在』)は漢字
その女子はニコニコしながら発表。席に戻ると、再び折り紙に没頭した。
![]()
ずっと折り紙に没頭していた女子は、この時、興味を引かれるテーマだったので、発表に参加しました。落ち着かず、授業中でも自分のやりたいことに夢中になる子がいる場合、この時期ならば好きな作業を認め、授業に乗ってきたときに受け入れる指導でもかまいません。
本人が聞いて考えていることをほめ、他の子供たちにも伝えましょう。
こうした子供は、自分が興味を持つテーマには食いついてきます。おもしろいテーマを示しながら、その子を巻き込むようにしていきます。そして、落ち着かずにフラフラする子が悪目立ちすることがないよう、自由な立ち歩きの話し合いなど、動きを伴う活動を取り入れていきましょう。

