小4社会「ごみの処理と再利用」指導アイデア
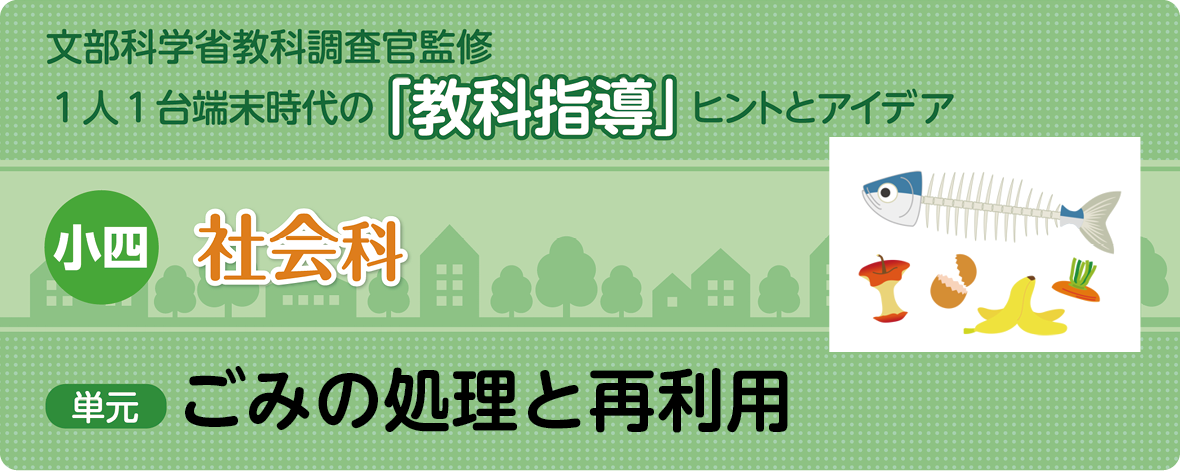
執筆/杉並区立天沼小学校指導教諭・新宅直人
編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登
国士舘大学教授・秋田博昭
目次
年間指導計画
・都道府県の様子
・水はどこから
・ガスはどこから
・ごみの処理と再利用
・自然災害から人々を守る活動
・伝統文化を今に伝える福島県
・郷土の発展に尽くす
・伝統的な技術を生かす新宿区
・伝統文化を守り生かす台東区
・豊かな自然環境を生かす小笠原
・国際交流に取り組む大田区
目標
廃棄物を処理する事業について、処理の仕組みや再利用、県内外の人々の協力などに着目して、見学・調査したり地図などの資料で調べたりしてまとめ、廃棄物の処理のための事業の様子を捉え、その事業の果たす役割を考え、表現することを通して、廃棄物を処理する事業は、衛生的な処理や資源の有効活用ができるよう進められていることや、地域の人々の生活環境の維持と向上に役立っていることを理解できるようにするとともに、主体的に学習問題を追究・解決し、学習したことを基に、ごみの減量など自分たちが協力できることを考えようとする態度を養う。
評価規準
知識・技能
①処理の仕組みや再利用の様子、県内外の人々の協力などについて、見学・調査したり地図などの資料で調べたりして、必要な情報を集め、読み取り、廃棄物の処理のための事業の様子を理解している。
②調べたことを白地図や図表、文などにまとめ、廃棄物を処理する事業は、衛生的な処理や資源の有効活用ができるよう進められていることや、生活環境の維持と向上を支えていることを理解している。
思考・判断・表現
①処理の仕組みや再利用の様子、県内外の人々の協力などに着目して問いを見いだし、廃棄物の処理のための事業の様子について考え、表現している。
②廃棄物を処理の仕組みや人々の協力関係と地域の良好な生活環境を関連付け、事業の果たす役割を考える。また、学習したことを基に廃棄物を減らすために、自分たちが協力できることを考えたり選択・判断したりして表現している。
主体的に学習に取り組む態度
①廃棄物を処理する事業について、予想や学習計画を立て、学習を振り返ったり見直したりして、学習問題を追究し、解決しようとしている。
②学習したことを基に、廃棄物を減らすために、自分たちが協力できることを考えようとしている。
学習の流れ(10時間扱い)
問題をつくる 3時間
- 家で出しているごみの種類について、調べてきたことを話し合う。
- 学校で出されるごみの種類を調べる。
- ごみの収集についての疑問を話し合い、学習問題と学習計画を立てる。
(学習問題)
毎日、こんなに多くのごみが出されているのに、どうやって処理しているのだろう。
追究する 5時間
- ごみはいつ、何の種類が収集されているのか調べる。
- 可燃ごみの処理の仕方や、清掃工場の仕組みについて調べる。
- 可燃ごみ以外のごみの処理について調べる。
- 埋め立て処分場と資源ごみの再利用について調べる。
- 東京都のごみ処理の歴史を調べる。
まとめる 2時間
- ごみ処理の仕組みや工夫について調べてわかったことを関係図にまとめ、学習問題に対する自分の考えをまとめる。
- これまでの学習を振り返り、ごみの減量に向けて自分たちにできることを話し合う。
問題をつくる
家や学校でどのようなごみをどれくらい出しているのかを調べ、ごみの収集や処理等について疑問に思ったことを基に学習問題を設定する。(1、2、3/10時間)
導入のくふう
家や学校で出しているごみの種類や量を調査することで、私たちの生活の中では大量のごみが出ていることに気付くことができるようにする。
1時間目
家で出しているごみの種類について、調べてきたことを話し合う。
家では、どのようなごみがどれくらい出されていましたか?
※事前に、家で出しているごみの種類を調べてくるように伝えておくとよい。
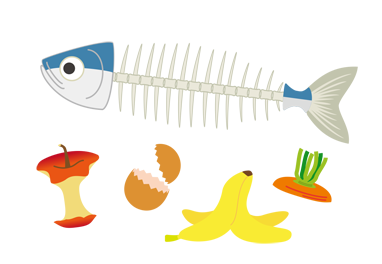

チラシとかティッシュ・ペーパーとか、紙のごみが多かったです。
生ごみは、毎日出ていました。タブレット型端末で写真を撮ってきたよ。
ビンや缶のごみもありました。ごみ収集所には、ごみを出す曜日が貼ってあったので、写真を撮ってきましたよ。
2時間目
学校で出されるごみの種類を調べる。
ごみを出すのは家だけではないですよね。学校はどうだろう?

教室で出たごみを持っていく場所があるので、そこを調べたり、主事さんに聞いたりしてみるといいと思います。
家だけじゃなくて、ぼくたちの学校生活でも多くのごみが出ているね。
学校でも、いくつかの種類に分けてごみを捨てているみたいだね。
3時間目
ごみの収集についての疑問を話し合い、学習問題と学習計画を立てる。
家や学校で出されているごみの種類を調べて、気付いたことや疑問に思ったことを話し合いましょう。
集めたごみはどうしているのかな。すべて燃やすのかな。
ごみは何種類くらいあるのかな。どうしてごみの種類に分けて、集めているのかな。
ごみ収集所はいくつあるのかな。それから、ごみ収集車は何台くらいあるのかな。
たくさんのごみが出ていたけれど、1日にどれぐらいの量のごみが出ているのかな。何トンとかになるのかな。
東京都民は、1人が1日に約800グラムのごみを出している計算になるんですよ。
ええっ! 東京都には1000万人以上の人がいるから、1日で8000トン以上のごみが出ているのですね。毎日、こんなに大量のごみが出ているのに、町にごみが溢れていないのはどうしてだろう?

毎日、こんなに多くのごみが出されているのに、どうやって処理しているのだろう。
【学習計画(調べること)】
・ごみの集め方
・ごみの種類
・だれがやっているのか
・収集車の数
・しょりの仕方
・収集所の数
・最後にはどうなるのか
≪問いを見いだすポイント≫
「問題をつくる」段階では、家や学校から出ているごみの種類や量を調べました。調べる際には、タブレット型端末を使ってごみの種類やごみの出し方などを撮影しておくと、授業での話合いに活用することができます。3時間目では、調べてわかったことを基に気付いたことや疑問を出し合うことで、「こんなに多くのごみをどうやって処理しているのだろう」という問いにつなげて学習問題を設定するとともに、その予想から、学習計画を立てていくようにしました。
追究する
学習計画を基に、大量に出されたごみがどのように処理されているのかや、人々はどのような協力をしているのかを調べる。(4、5、6、7、8/10時間)
話合い活動のくふう
各児童の家では、何曜日にどの種類のごみを出しているかを調べ、集めるごみの種類と曜日は、地区ごとに違っていることを捉えることで、なぜそのような仕組みになっているのかを話し合うことができるようにする。
4時間⽬
ごみはいつ、何の種類が収集されているのか調べる。
イラスト/(資)イラストメーカーズ

