小6理科「人の体のつくりとはたらき」指導アイデア
文部科学省教科調査官の監修のもと、小6理科「人の体のつくりとはたらき」の板書例、教師の発問、想定される子どもの発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。
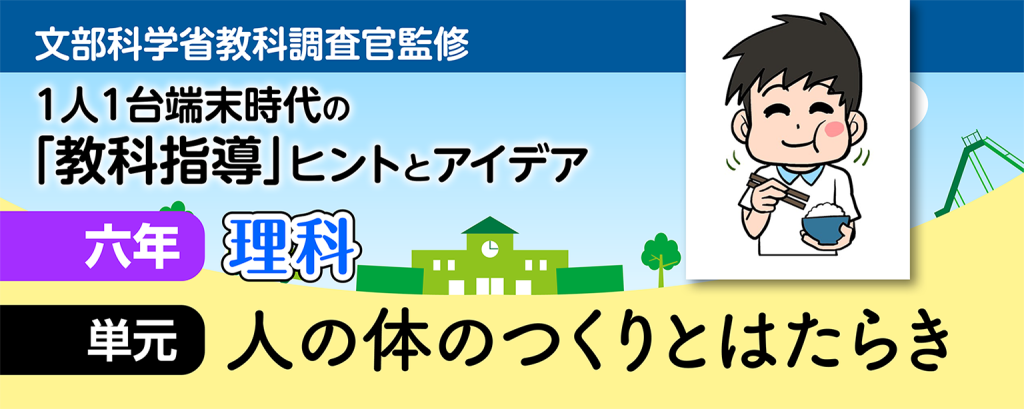
執筆/福岡県福岡市立東吉塚小学校教諭・岩田謙人
監修/文部科学省教科調査官・有本淳
福岡県福岡市立東吉塚小学校校長・杉原賢太郎
福岡県福岡市立南片江小学校校長・酒井美佐緒
目次
単元目標
体のつくりと呼吸、消化、排出および循環のはたらきに着目して、生命を維持するはたらきを多面的に調べる活動を通して、人や他の動物の体のつくりとはたらきについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主により妥当な考えをつくりだす力や生命を尊重する態度、主体的に問題解決しようとする態度を育成することがねらいである。
評価規準
知識・技能
①体内に酸素が取り入れられ、体外に二酸化炭素などが出されていることを理解している。
②食べ物は、口、胃、腸などを通る間に消化、吸収され、吸収されなかった物は排出されることを理解している。
③血液は、心臓のはたらきで体内を巡り、養分、酸素及び二酸化炭素などを運んでいることを理解している。
④体内には、生命活動を維持するための様々な臓器があることを理解している。
⑤人や動物の体のつくりとはたらきについて観察、実験などの目的に応じて、器具や機器などを選択して、正しく扱いながら調べ、それらの過程や得られた結果を適切に記録している。
思考・判断・表現
①人や他の動物の体のつくりとはたらきについて、差異点や共通点などを基に問題を見いだし、予想や仮説を基に、解決の方法を発想し、表現するなどして問題解決している。
②人や他の動物の体のつくりとはたらきについて、観察、実験などを行い、体のつくりと吸収、消化、排出および循環のはたらきについて、より妥当な考えをつくりだし、表現するなどして問題解決している。
主体的に学習に取り組む態度
①人や他の動物の体のつくりとはたらきについての事物・現象に進んで関わり、粘り強く他者と関わりながら問題解決しようとしている。
②人や他の動物の体のつくりとはたらきについて学んだことを学習や生活に生かそうとしている。

