算数の授業デザインとは【教科担任制 最前線!! 算数専科を楽しもう】③
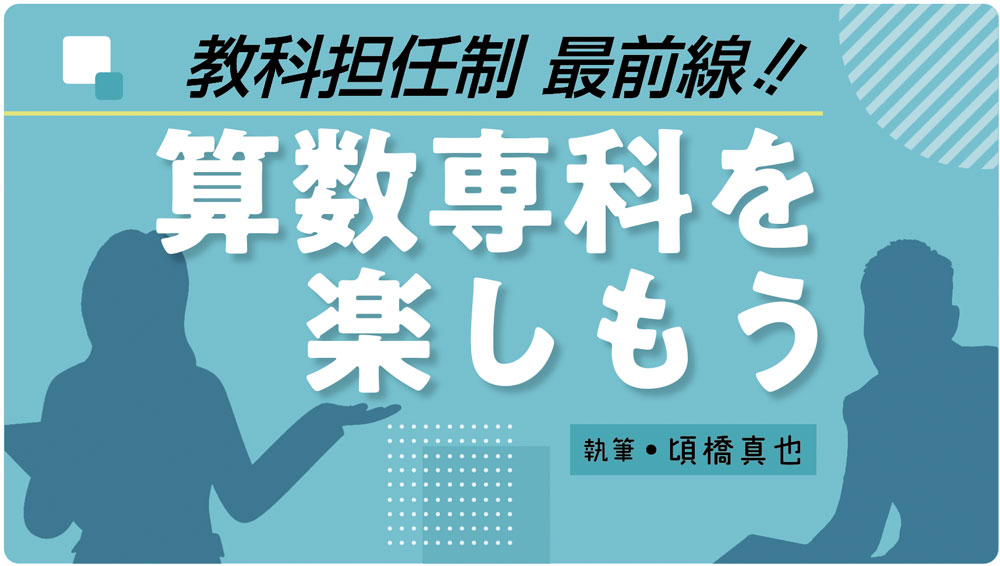
今回は、算数の授業デザインを考えていきます。頃橋先生の初任から10年までの授業づくりと現在14年目で志している授業づくりを紹介しながら、先生方の授業づくりに役立つようなマインドをお届けします。
執筆/奈良県公立小学校教諭・頃橋真也
目次
THE 一斉授業からの卒業
主体的で対話的な深い学び。この言葉を耳にするようになり、授業の在り方を見直した先生は大勢いると思います。自分のこれまでの考え方や指導法を変えるのは、ものすごく勇気がいることです。
特に、一斉授業のスタイルで、数多くの実践を積まれて、成果を感じてこられた先生はなおさらです。しかし、私たち教師は、日々自分の授業をリフレクションしてアップデートしていくことが必要です。
私は現在、算数専科として3~6年生の算数の授業(全20コマ)を担当しています。初任から10年目までは、一斉授業を主体として、ペア学習やグループ学習を一部取り入れるという方法を取ってきました。このスタイルの授業を行っているときは、学力でいうと下位層~中流層の子どもに焦点を当て、これらの子どもが分かるような授業を志していました。
そのような考え方で授業をしていたときに見られた子どもの姿は、次のようなものでした。
- チャイムが鳴る前に片づけ始める児童(上位層・下位層)
- 対話があまりない授業(1人で問題を解く)
- 問題を解こうとしない、やる気が起きない児童(下位層、一部上位層)
- 45分座りっぱなしの授業
しかし、新学習指導要領が提示され、「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善」を行う必要性を改めて感じました。そこで、私が注目したのは、佐藤学先生(東京大学名誉教授)が提唱する「学びの共同体」の学び合いについての考えと、西川純先生(上越教育大学教授)が提唱する『学び合い(二重括弧の学び合い)』の考え方です。コロナ禍では(10年目~13年目)は、ペアやグループでの対話にも制限がかかり、大変苦労しました。しかし、この間に、Afterコロナにどのような授業をデザインしていきたいか徹底的に整理することができました。
「学び合い」と『学び合い』
ではここで、学びの共同体が提唱している学び合いについて説明します。
佐藤学先生は著書『学びの共同体の創造』(小学館)で、
学びの共同体の改革は、授業や学びや教師の研修や学校経営の「改善」ではなく「革命」であり、改革の処方箋ではなく「ヴィジョン」と「哲学」と「活動システム」のトータルな理論的・思想的実践である。
『学びの共同体の創造』(小学館)より
と述べられています。
また佐藤学先生は同著書で、
学びの共同体では授業の前半を教科書レベルの〈共有の学び〉、授業の後半を教科書レベル以上の〈ジャンプの学び〉で組織している。―聴き合う関係を基礎として、「探求と協同の学び」がどの授業においても実現し、子どもたち1人残らず授業の最初から最後まで「学びの主人公」として夢中になって学び合っていること。
『学びの共同体の創造』(小学館)より
と述べられています。
次に、『学び合い(二重括弧の学び合い)』について説明します。西川純先生は著書、「『学び合い』で「気になる子」のいるクラスがうまくいく!」(学陽書房)にて、
『学び合い』は、1人も見捨てられない社会・教育を実現するために生まれました。―第1に「学校は、他の人と折り合いをつけたり、助け合って課題を達成したりすることを通して、他者との社会的なかかわりを学ぶ場である」という「学校観」。第2に、「子どもたちは有能である」という「子ども観」。この2つの考えから、「教師は、目標の設定、評価、環境の整備を行い、学ぶことは子どもたち自身に任せるほうが、子どもが主体的に学ぶことができ、子ども同士の関係も育つ」という「授業観」が導かれます。
『学び合い』で「気になる子」のいるクラスがうまくいく!」(学陽書房)より
と述べられています。
これから、私が紹介する実践は、この2つの学びの在り方から着想を得て、導いた授業のデザインです。

「みんなの教育技術」でも、「ウィズコロナ時代にあるべき学校教育像とは―『学びの共同体の創造~探究と協同へ~』著者インタビュー」で紹介されていますので、ぜひご参照ください。

