おさえておこう! 理科授業の「1人1台端末」活用の基本とは? 【理科の壺】

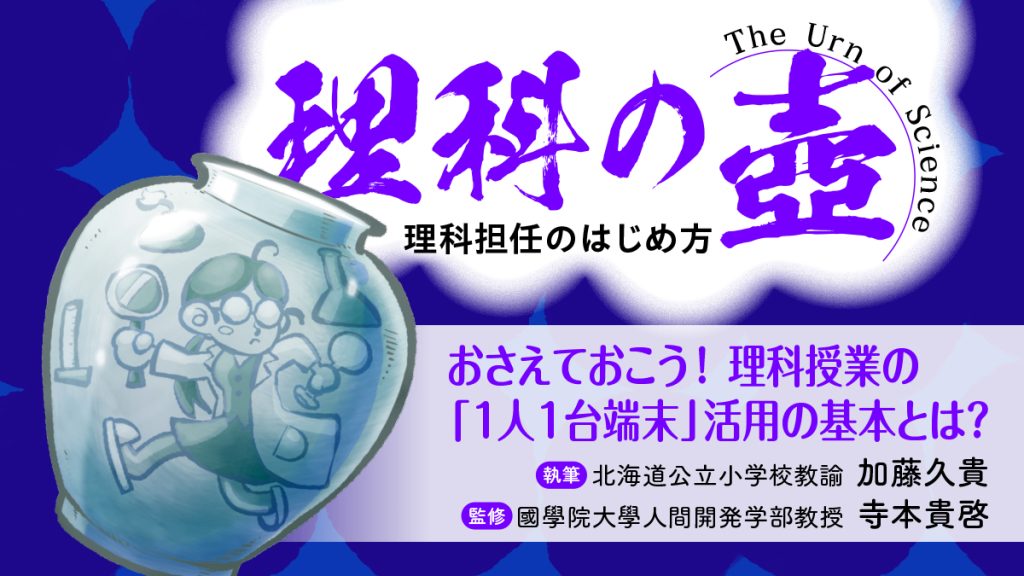
年度末を迎え、そろそろ次年度に向けて動き出す時期となりました。理科の授業でも1人1台端末の活用は日常的なものとなっています。このページをご覧になっている方の中には、来年度初めて理科を担当することになり、不安に思われている方もいらっしゃるのでは、と思います。理科では、1人1台端末をどのような場面でどのように活用していくことが望ましいのでしょう。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/北海道公立小学校教諭・加藤久貴
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
理科と「1人1台端末」の組み合わせ
理科の授業と「1人1台端末」は非常に相性が良いものと考えます。理科は、自然事象との出合いの中で問題解決を行いますので、一人一人の問題意識は、実に多岐にわたります。一人一人が自分の考えに合わせて端末を活用し、情報収集や記録が容易にできるようなったことは、大きなメリットであるといえるでしょう。ここで、活用の基本的なポイントを押さえておきたいと思います。
1.活動の記録を効果的に撮影しましょう
理科の学習においてはたくさんの場面で画像や動画を撮影します。春になると植物の種子や発芽の様子、生き物の様子などさまざまな画像を撮影することができます。子どもは、とにかく撮影することが大好きなので、たくさんの画像を端末に収めていくことでしょう。私は、基本的に「どんどんとっていいよ」といいます。ただし、いくつか気を付けることがあります。
⑴ 撮影の目的を自覚していること
例えば、同じ昆虫についての学習でも、昆虫の体のつくりに着目する学習では、昆虫の体のつくりがわかるように様々な角度から撮影する必要があります。また、昆虫のすみかを調べる活動では、昆虫とその周りの様子を含めた画像を撮影します。このように、学習の目的によって撮影のポイントが違います。大切なことは「何のために撮影するのか」を子どもが自覚しているかどうかです。撮影の目的を自覚できるような指導を心掛けることで、着目する視点が明確になり、学習のねらいに迫ることができます。そうすると、やみくもに撮影することもなくなりますので、自然と撮影される枚数は限られてくるでしょう。
⑵ 積極的にメモを残しておくこと
撮影した画像は、そのままにせずに、自分が着目したポイントを残しておくことが大切です。例えば、葉の形に着目する時間では、撮影した画像をチャートを活用して分類したり、気づいたことや発見したことなどを書き加えたりすることで、葉の特徴をくわしくまとめることができます。そのようにして記録した画像は残しておき、必要のない画像は適宜削除していくことを日常化できるようにしましょう。


