小1生活「もうすぐ2年生」指導アイデア
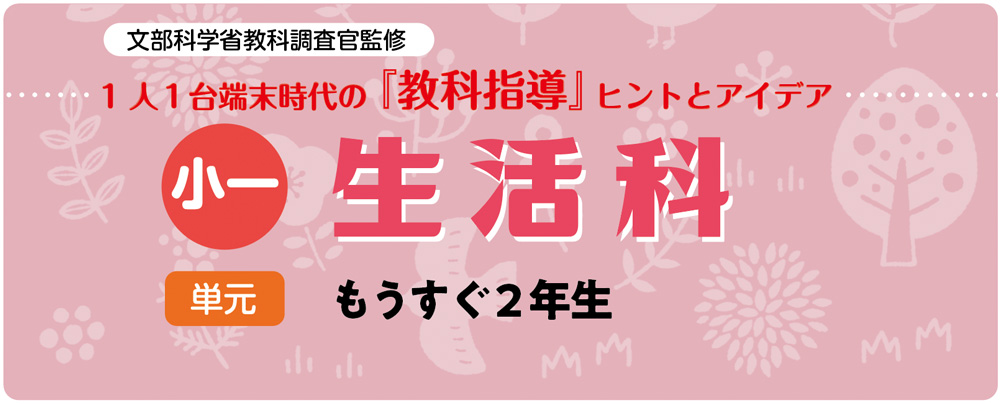
文部科学省教科調査官の監修による、小1生活科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「もうすぐ2年生」の単元を扱います。
執筆/高知大学教育学部附属小学校教諭・廣瀬 愛
編集委員/文部科学省教科調査官・齋藤博伸
高知県公立小学校校長・尾中映里
目次
年間指導計画
年間指導計画(クリックすると表示します)
| 4月 | どきどき わくわく 1ねんせい(スタートカリキュラム) |
| 5月 | がっこう だいすき |
| 6月 | きれいに さいてね |
| 7月 | なつが やって きた |
| 8月 | いきものと なかよし |
| 9月 | あきを さがそう |
| 10月 | あきの おもちゃを つくろう |
| 11月 | あきまつりを しよう |
| 12月 | じぶんで できるよ |
| 1月 | ふゆを たのしもう |
| 2月 | しん1ねんせいに がっこうのことを つたえよう |
| 3月 | もうすぐ2ねんせい |
単元目標
自分自身の生活や成長を調べたり伝え合ったりする活動を通して、自分のことや支えてくれた人々について考えることができ、自分が大きくなったこと、自分でできるようになったことなどが分かるとともに、これまでの生活や成長を支えてくれた人々の存在に気付き、これからの生活や成長への願いをもって、意欲的に生活しようとする。

