第4学年「電流のはたらき」のコツ 【理科の壺】

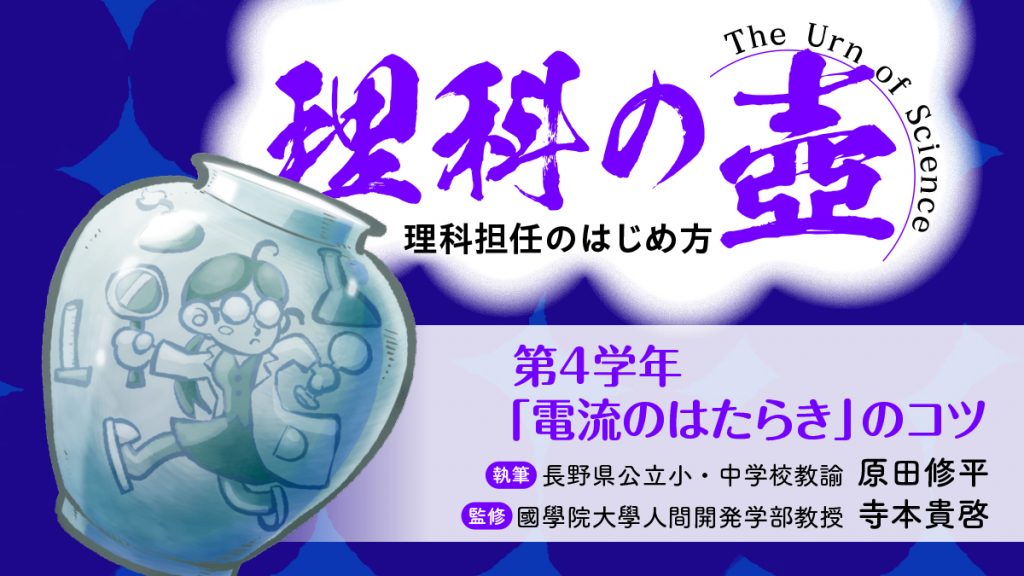
4年生では、2個の電池をつないで直列回路、並列回路の学習を学びます。電流の流れ方や電池のつなぎ方を学習する際、様々な回路ができてしまって、どのように収拾をつけるか困ったことのある先生も多い単元です。また電池や導線、モーターの実物を使うと、回路図で見るのとは異なり、つなぎ方の違いがわからず、違うつなぎ方や逆向きのつなぎ方をしてしまうことも多いです。このように、先生にとっても、子どもたちにとっても難しい電気の単元ですが、考え方の流れさえ先生自身が理解していれば、比較的簡単に授業が進められると思います。今回は1つの授業の流れや押さえるポイントを整理した回となります。実際に電池と導線、モーターを用意して、試しながら読んではいかがでしょう。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/長野県公立小・中学校教諭・原田修平
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1.第4学年「電流のはたらき」を学ぶ前の児童たちの実態は?
3年「電気の通り道」の学習では、(電池ボックスに入れた)乾電池1つ、ソケットや豆電球、スイッチ、導線などを1つの輪のようにつなぎ、回路にすると電気が通って、豆電球に明かりがつく学習をしています。また、電気を通すものと通さないものがあり、電気を通すものは金属でできていることを学びます。
ここでは、乾電池のプラス極、マイナス極につなぐことは学びますし、「金ぞくは電気を通す」という表現はしますが、電気の流れを「電流」ということは扱っていません。ましてや電流に向きがあると思っていない児童や、プラス極からもマイナス極からも電気が出て伝わって、豆電球でぶつかって光ると思っている児童が意外に多いのが実態です。
さらにつまずきやすい内容としては、「鉄」という言葉を「金属」と同じ意味で使ってしまうことです。「アルミニウムは鉄ですか」と問われて、「はい、そうです。」と答える児童はだいたい勘違いしています。
単元の導入で「金属は種類が多く、鉄はそのうちの1つであること。ほかにも銅やアルミニウムなど、様々な金属があること」を確認・指導しましょう。

