国語の教材分析④ ~分析の観点「冒頭」~

Instagramでは1万人超えのフォロワーに支持され、多くの女性教師のロールモデルにもなっている樋口綾香先生による人気連載! 国語の教材分析シリーズ第4回は、「冒頭」を切り口に教材を読み深めていくポイントについてお伝えします。
執筆/大阪府公立小学校教諭・樋口綾香
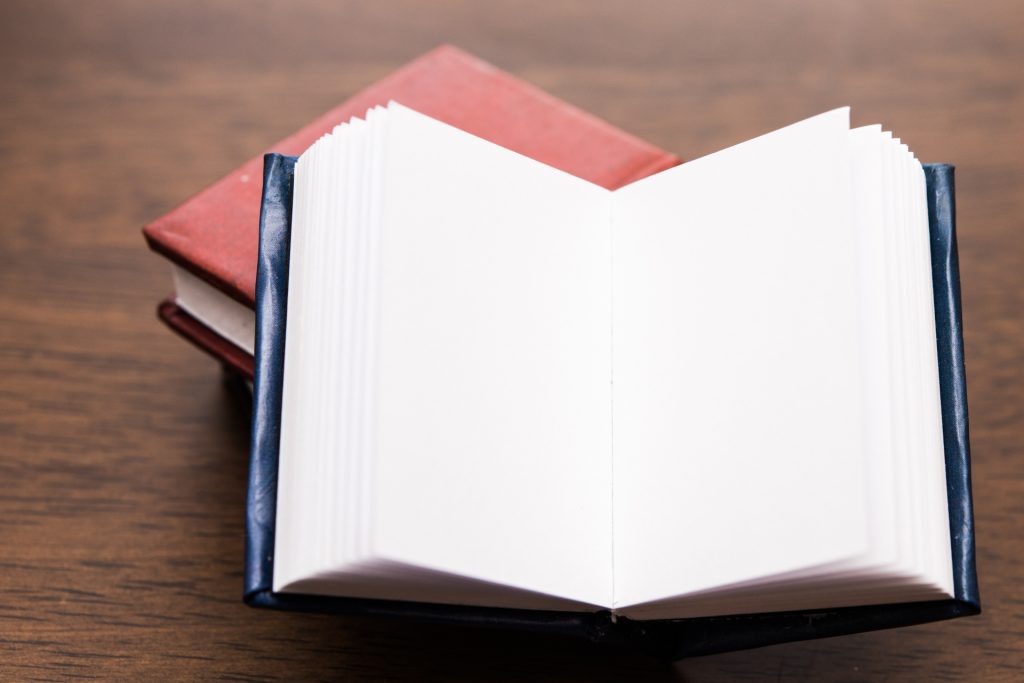
【関連記事】
国語の教材分析① ~教材分析で大切にしたいこと~
国語の教材分析② ~分析の観点「題名」~
国語の教材分析③ ~教師と教材との出合い~
目次
①昔話の冒頭と比較する
前回、物語の冒頭には、お話の設定である「時・場所・人物」が書いてあることが多いとお伝えしました。
この「時・場所・人物」の中で、「どれが最も多く説明されているか」や、「お話の設定以外の文は、何について詳しく書かれているか」と考えることがポイントです。
たとえば、『三年とうげ』の冒頭では、「時・場所・人物」の中で、「場所」である三年とうげのことが18行に渡って語られています。人物の紹介が書かれるのは19行目からです。
昔話のよくある冒頭である「むかしむかし、あるところに、おじいさんとおばあさんが住んでいました。」と比べると、場所の説明が特に多いことが分かります。
このことから、このお話では、三年とうげという場所が大変重要(場所の言い伝えが変容する)であり、作者は、三年とうげがどんなところなのかを読者に印象付けたいのだと読み取ることができます。
児童と学習をするときには、冒頭を読み取る際、三年とうげがどのような場所であるか、それが事件や結末とどう結びつくかを考えていくとよいでしょう。
このように、昔話のよくある冒頭と比べることで、そのお話の何に着目して読めばよいかが分かります。
【関連記事】
子供たちに伝わる板書の書き方を徹底解説している特集。様々な事例がたくさん!→ 樋口綾香&樋口万太郎夫妻が解説! 国語・算数 伝わる板書のルール

