国語における教師の行為の中で、教員の腕の見せ所は「説明」【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #53】
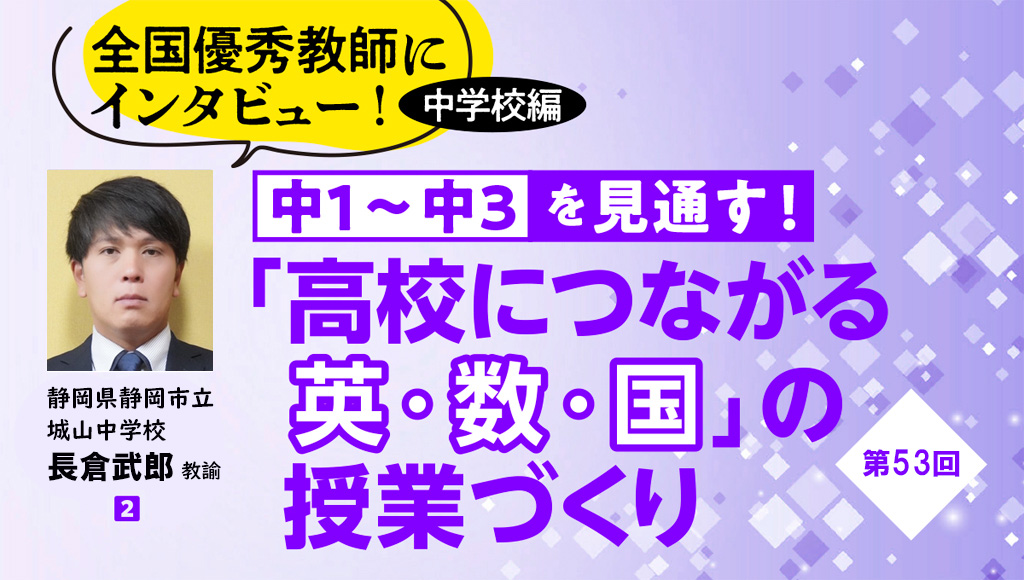
前回は、静岡県静岡市立城山中学校の長倉武郎教諭が、2年生の説明的文章を読む単元と授業の実践事例を紹介しました。今回は、そのような単元・授業づくりの背景となる、授業づくりの考え方や、それを通してどんな人を育てたいかという教育観について伺っていきます。

長倉武郎 教諭
目次
教員になったら、楽しいと思える国語の授業をしたい
子供が主体的に読んだり対話したりしながら、その学習活動を楽しいと思えるような単元づくりをしたいと話す長倉教諭。その思いの基になった中学校時代の体験から話を聞いていきました。
「私は、大学時代は近世の文学を学んでおり、当初はそれほど強く国語の教員になろうと思っていたわけではありませんでした。それは私自身が中学校時代に受けた国語の授業があまり楽しいものではなかったことによります。『教科書を教える時代だった』のかなと思うのですが、『登場人物の気持ちを考える』とか、『説明文の内容を要約する』ということが中心で、国語が楽しいとは思えなかったのです。
ただ、父親が教員で、教員という仕事は身近でしたし、『大学に行ったら教員免許は取っておけよ』とも言われていました。やがて、いざ卒業、就職が近付いてきたときに考えてみると、やはり教員はよい仕事かなと思いましたし、『教職は大変だ』『ブラックだ』などと言われてもいましたが、子供のためだったら時間を使える人間でありたいと思い、教師になろうと考えました。そして、教員になったら自分が体験したのとは異なる、楽しいと思える国語の授業をしたいと考えたのです。
とは言え、いざ教員になった当初は、1時間ごとの授業をつくるのが精一杯でした。まず教科書教材に当たって、『この教材は、こういうねらいでこういう構成になっていて……』と、その解釈を子供たちに伝えるような授業になってしまっていた時期もあったと思います」
そこから研究会などを通して学びを重ねながら、まず学習指導要領に当たって授業をつくるようになり、次第に授業も変わっていったと長倉教諭は話します。
「例えば、単元の最初には、『この単元を通してみんなに身に付けてほしいことはこういうことだよ』と説明をします。そのとき、例えば次回紹介をする図表などを活用した説明文の単元であれば、『これから読む文章は図表などと照らし合わせながら読むことが必要な文章で、それを読む力は君たちが将来働くとき、資料などを読むためには必要なんだよ』と話をします。
それに対して、内容知優先の教科である数学はよいなと思うこともあります。数学であれば、内容が明確で『これが分かった』『できた』と子供たちも実感しやすいし、正の数、負の数を学んだら、それを実生活で生かす場面が比較的分かりやすいと思うのです。
しかし、方法知優先の教科である国語は、そのつながりが見えにくいので、そこをしっかり伝えて単元に入っていきたいと思っています」
自分たちで読みたくなるような仕組みのある単元づくりをしたい

そのように、学ぶ必要性を感じられるようにすることと同時に、中学時代の体験とは逆に、学ぶ楽しさも感じられる単元・授業づくりを心がけているという長倉教諭。どのような点を大事にしながら単元・授業づくりを行っているのでしょうか。
「必要感や楽しさを感じられる授業をつくるには、やはり言語活動をどう設定するかが肝になってくると思います。
例えば、中学1年生を対象に物語文の学習をしたときに、学習指導要領の言語活動例にはないのですが、単元の最後にディベートをするような構成にしたこともあります。ある物語文の中で対立的な立場にある登場人物AとBの立場に分かれて、それぞれが討論を行ったのですが、子供たちは『この部分を見てください』と、物語文の叙述に根拠を求めながら自身の論を展開していきました。
そのようにうまく言語活動が工夫できれば、他者を説得するため主体的に教科書の叙述を精読しながら分析し、根拠を探して対話していこうと思えるし、学ぶことが面白くなるのだと思います。これをもし、『まずここを読みましょう』『次、ここを読んで』と指示に従っていたのでは、子供たちの中に面白さは生まれないでしょう。
そうではなく、先のように自分たちで読みたくなるような仕組みのある単元づくりを可能な限りたくさんしたいとは思います。しかし、すべての単元がそうできるわけではないので、1年を見通して、どこでそういう仕掛けをするか、その活動の評価も含めてしっかり考えてつくりたいと思っています」

