小4算数「およその数(計算の見積もり)」指導アイデア《目的に応じた積や商の見積もり》
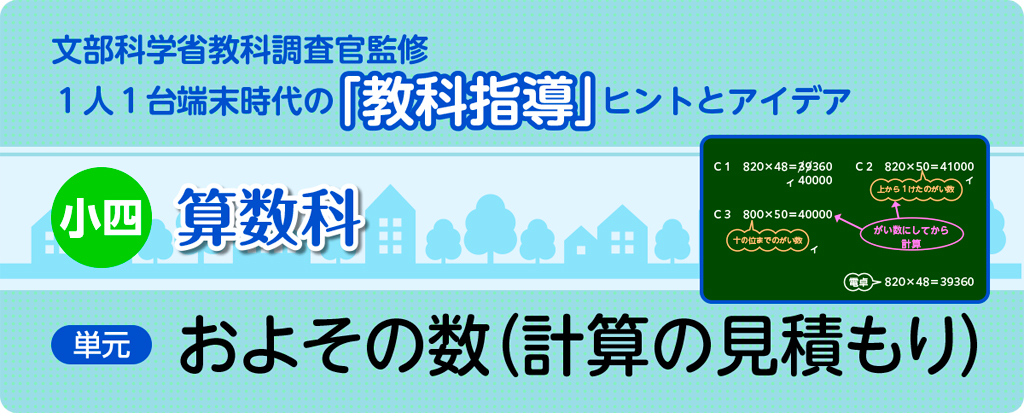
執筆/東京都練馬区立大泉東小学校主任教諭・大橋直
監修/東京都国立教育政策研究所教育課程調査官・加固希支男、東京都板橋区立上板橋小学校副校長・内藤信義
目次
年間指導計画
・大きい数
・折れ線グラフ
・角とその大きさ
・わり算1桁
・小数のしくみ
・垂直・平行と四角形
・わり算2桁
・およその数、計算の見積もり
・そろばん
・倍の見方
・資料の整理
・式と計算
・変わり方
・面積
・分数
・小数のかけ算とわり算
・直方体と立方体
単元の展開(各時の主な学習活動内容)
第1時 がい数について理解し、がい数で表すよさについて考える。
第2時 四捨五入の方法と、その意味について理解する。
第3時 四捨五入して、□の位までのがい数にするときの表現や四捨五入の仕方を理解する。
第4時 四捨五入して、上から○桁のがい数にするときの表現や四捨五入の仕方を理解する。
第5時 「以上」「以下」について知り、四捨五入してがい数にする場合の範囲について考える。
第6時 人口を棒グラフに表すなど、大きな数をがい数で表すことについて考え、「未満」について理解する。
第7時 目的に応じた和や差の見積もりについて考える。
第8時(本時)目的に応じた積や商の見積もりについて考える。
第9時 学習内容の定着を確認し、理解を確実にする。
本時のねらい
がい数を用いて積や商の見積もりができる。
評価規準
前時でのがい数を用いて計算する方法に着目し、がい数を適切に用いて積や商を見積もることができる。
本時の教材のポイント
本時は、四則演算の積や商について、目的に応じた見積もりの方法を考える学習です。前時では和や差の見積もりを扱い、目的に応じて四捨五入・切り上げ・切り捨てを使い分けることについて学習しました。本時ではその学びを積や商に適用し、目的に応じた見積もりの仕方を意識した指導を行います。本時の問題では、目的に応じた見積もりをするために、どのようながい数で表せばよいか自ら判断できるようにすることが大切になります。
最初はおよその金額を求めるということと、人数のみ示します。また、答えの見通しをもつために答えの選択肢を示しました。問題を解決するために必要な情報について考えさせることで、「1人分の金額が分かればかけ算で求められる」と式の見通しをもてたり、選択肢を示すことで、およその金額のイメージをもつことができたりすることをねらっています。また、解決の見通しをもてない子供に「3つの内の1つが答え」である安心感を与えて見通しをもちやすくさせたり、全員に学び合いの場でどの答えになったか立場を主張させたりすることもできます。
学び合いの場では、それぞれの考え方を比較し、より簡単に見積もりができる考え方のよさを全員で共有していきます。考え方を比較する際には、「計算しやすい」「簡単」など、子供が使う言葉を取り上げ、その考え方の価値を認め、積の見積もりをする際には、簡単に計算できるがい数にすることが大切であるということを共有します。
そして、積の見積もりの後に、商の見積もりの問題を扱います。ここでは、積の見積もりの際の考え方を生かし、簡単に計算できるがい数にすることを意識させたいところです。子供から「さっきの問題と同じように計算しやすいがい数にする」といった発言があればよいですが、もしなければ「積の見積もりのときと同じように考えられるかな?」といった問いかけをしていきます。そして、積と商を見積もるときの共通点に着目させて、まとめていきます。
本時の展開
前の時間まで、どのようなことを学習してきましたか。
昨日は、和や差の結果をがい数を使って見積もりました。
見積もりをするときにどのような工夫をしましたか。
がい数にしてから計算しました。
がい数にして計算することのよさは何ですか。
がい数にしてから計算すると簡単に見積もることができます。
暗算で求められました。
そうでしたね。それでは、今日の問題です。

4年生48人で遠足に行く計画を立てています。電車で行くなら全員分のおよその代金は次のうちどれでしょう。
ア 35000円 イ 40000円 ウ 50000円
このままでは分かりません。
どんなことが知りたいですか。
電車で行く場合の1人あたりの代金が知りたいです。
電車で行く場合の1人あたりの代金は820円です。
かけ算になりそう。
820×48の答えの見積もりです。
かけ算の答えのことをどういう言葉で表していたか覚えていますか。
積です。

積の見積もりをしましょう。
見通し〈問題①〉
かけ算を使えばできそう。筆算で計算できるかな。
がい数にして計算すれば見積もりが楽になるかな。
どの位までのがい数にして計算すれば簡単に見積もりができるかな。
自力解決の様子〈問題①〉
A
・積を求めてから、がい数にする。
820×48=39360
40000
約40000円
B
・十の位までのがい数にしてから、積を求める。
820×50=41000
約41000円
C
・上から1桁のがい数にしてから、積を求める。
800×50=40000
約40000円
全体発表とそれぞれの考えの関連付け〈問題①〉
まずどのようにして電車で行く場合の問題を考えたのか教えてください。
構成/桧貝卓哉 イラスト/横井智美 図版作成/永井俊彦

