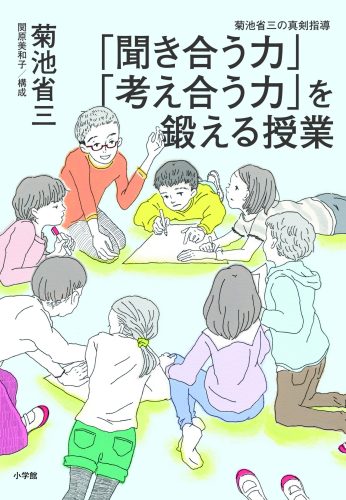菊池省三インタビュー「AI時代の今、紙の辞書を使った学びでしか身に付かない力とは?」
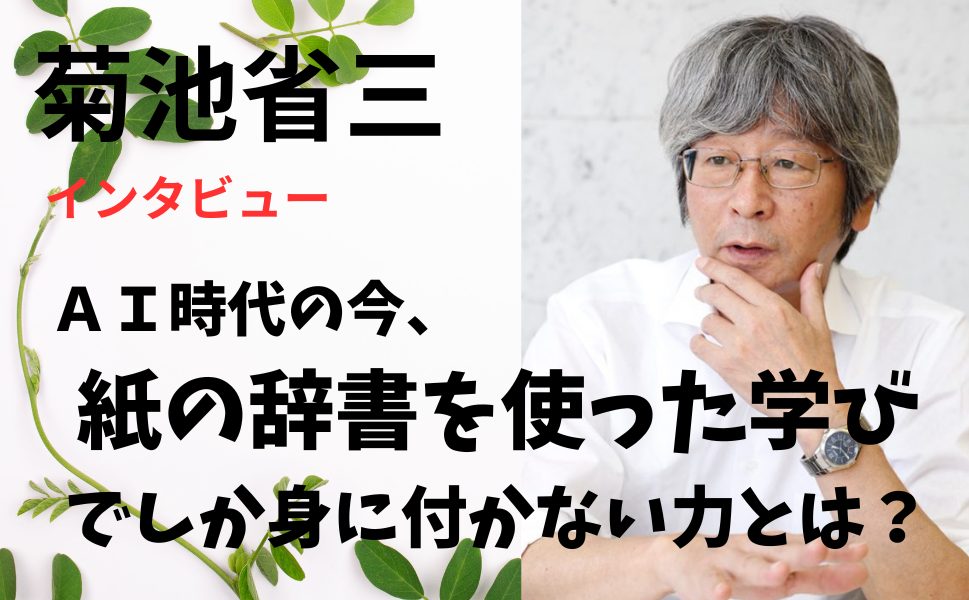
学級崩壊立て直し請負人と呼ばれる凄腕実践者にして、教育実践研究サークル「菊池道場」を主宰する菊池省三先生。その現役小学校教諭時代、担任する学級の子どもたちが日常的に使いこなしていた紙の辞書は、言葉を大切に育てる菊池実践の核とも言えるツールでした。シェアナンバーワンを誇る「例解学習辞典シリーズ」の新装・改訂版の刊行を記念して、菊池先生に「なぜ今、紙の辞書で学ぶことが大切なのか?」について聞きました。
取材・文/「みんなの教育技術」編集部
目次
広大な言葉の世界へのパスポート
保育所や幼稚園・こども園の中には、卒園記念に辞書をプレゼントする園がありますよね。
小学1年生からでも使えるようにと丁寧に作られ、用紙や色使い等に細やかな心配りが行き届いた紙の辞書が、一人一人に配られます。
多くの子どもたちはその時、人生で初めて辞書を手にします。まだ幼い男の子や女の子たちが、その時初めて、広大な言葉の世界の入り口に立つのです。
私が現役の小学校教師だった頃は、1年生から6年生まで、担任したどの学級でも、子どもたちの机の上には必ず辞書を置かせていました。教科を問わず、1日中子どもたちが自ら自由に活用できるようにしていました。国語辞典、漢字辞典、四字熟語辞典、慣用句辞典、等々……様々な種類の辞書が机の上に何冊も積み重なり、タワーのように高くなる時もありました。
それらの辞書を日常的に使いこなしているうちに、子どもたちは、「言葉の力」の大きさと、語彙を増やしていくことの大切さについて、自然に理解し始めます。辞書が積み重なっていると、掃除の時などに机を移動させるのが大変なのですが、子どもたちから「重い」とか「邪魔だ」とか、そういう文句は不思議に出ませんでした。
私の授業では例えぱ、「犬」という言葉を引かせて、「昔からよく飼われている動物。ペットのほか、警察犬や介助犬などがある。」などと書かれている文を、第2、第3の意味も含めて、3回音読させていました。辞書を引き終えた子から順に立ち上がって、3回声に出して読むわけです。
子どもたちは3回読むうちに、「そうか、うちのポチは、こういう生き物なのか」と納得していきます。つまり、「うちのポチ」よりも抽象度が高い「犬」という上位語の意味と、実際に飼っているポチという具体とが繋がってきます。辞書にはさらに、その言葉を使った例文や類似語も示されています。私のクラスでは、そうした学びを日常的に積み重ねていました。
果てしない言葉の世界を「俯瞰」できるツール
辞書の長所について考えるため、まずは紙の新聞を例にとってみましょう。
新聞にはいろいろな記事が掲載されています。政治経済面、スポーツ面、文化面に社会面……それらが見出しとリード文で大まかにざっと概観、俯瞰できるわけです。多様な情報を多様な角度から取りあげた記事を、一望のもとに見渡すことができます。
それに比べ、スマホを使ってインターネットで検索した場合、画面にはピンポイントでヒットした情報しか表示されず、複数の情報を俯瞰して見ることはできません。こうした新聞の長所は、紙の辞書の長所と共通しています。
情報の「俯瞰性」。小学1年生の段階から広大な言葉の世界を俯瞰し、それらを自分の中に落とし込んでいけることーーそれが紙の辞書の大きな長所だと考えています。
辞書を使ったグループワークの可能性
辞書を使った学びの例を他にもご紹介しましょう。
私の授業ではある言葉を課題として出し、4人グループで一斉に引いて速さを競う活動や、子どもたちが知らない言葉の意味を3択クイズとして出題し、一斉に辞書を引いて調べ、競って解答する活動も行っていました。授業中にこうした活動で楽しく盛り上がることで、子ども同士に、「辞書を中心にした関わり」が生まれます。
基本的に個人で端末に向き合って検索するインターネットと違い、紙の辞書なら、それを使いながら友達と繋がって学び合う、「協働的な学び」の多様な可能性が広がるのです。
辞書で、公に通用する「人間」を育てよう
私は「学級崩壊立て直し請負人」と呼ばれることもありますが、厳しい状況にある学級の子どもたちに対し、「書きましょう」と指示しても、多くが驚くほど書けません。「話しましょう」と指示した際にも、それぞれが粗暴で下品な言葉しか使うことができず、当然ながら話し合いも成立しません。
そういう子どもたちは、「公の言葉」を知らないのです。公の場でみんなに伝えるために必要な、「公の言葉」を獲得できていないのです。彼らは「公の言葉」を獲得し、公にふさわしい行動・態度を学ばない限り、広い社会へと出て行くことはできません。
私は子どもたちによく、「敬語を使うのは面倒くさいかもしれないけど、それを身に付けていれば、社会の中の様々な人と繋がることができる。敬語は自分の世界を広げるためのパスポートなんだよ」と話していました。
そうした敬語を含め、「公の言葉」を調べて獲得できる辞書は、社会と繋がり、自分の世界をどんどん広げていくためのパスポートでもあります。辞書は、社会に通用する「人間」を育てるための重要なツールだと言ってもよいでしょう。
私事になりますが、私の亡父は中学校の社会科の教師でした。
生前には英字新聞を定期購読して、毎日英和辞典を引きながらそれを読んでいました。その辞書は長年使い込まれてボロボロで、父がその辞書を引いている時には、どの単語がどの辺りにあるか、その位置を指が覚えているように見えました。
その辞書の厚み、「だいたいこの辺やな」とか言いながら引いている姿、そして引く時に指で触れる箇所の汚れ……。それら全てに畏敬と憧れの気持ちを抱きながら、毎日見ていたことを懐かしく思い出します。
今、目の前にある子ども用の辞書(例解学習国語辞典・小学館)を手に取ってみると、持ち運びやすいサイズと重さですし、ページの紙もふっくらと柔らかくてめくりやすく、それでいて丈夫で破れにくいな、と感じます。辞書ご担当の方にお聞きすると、数十年のノウハウを生かして、辞書のためだけに特別に開発された用紙を使っているのだそうです。
このように子ども向けに丁寧に作られた辞書を手渡し、語彙を獲得する環境を意図的に整えてあげることは、教師のみならず保護者にとっても、子どもに対する「責任」の一つだと思います。
自分が知りたい言葉を辞書の中に探して、「あった!」という喜び。スマホでは感じられないであろう「自分の力で意味を見つけた!」という喜び…。そういう喜びを、ぜひ子どもたちにたくさん感じさせてあげてください。
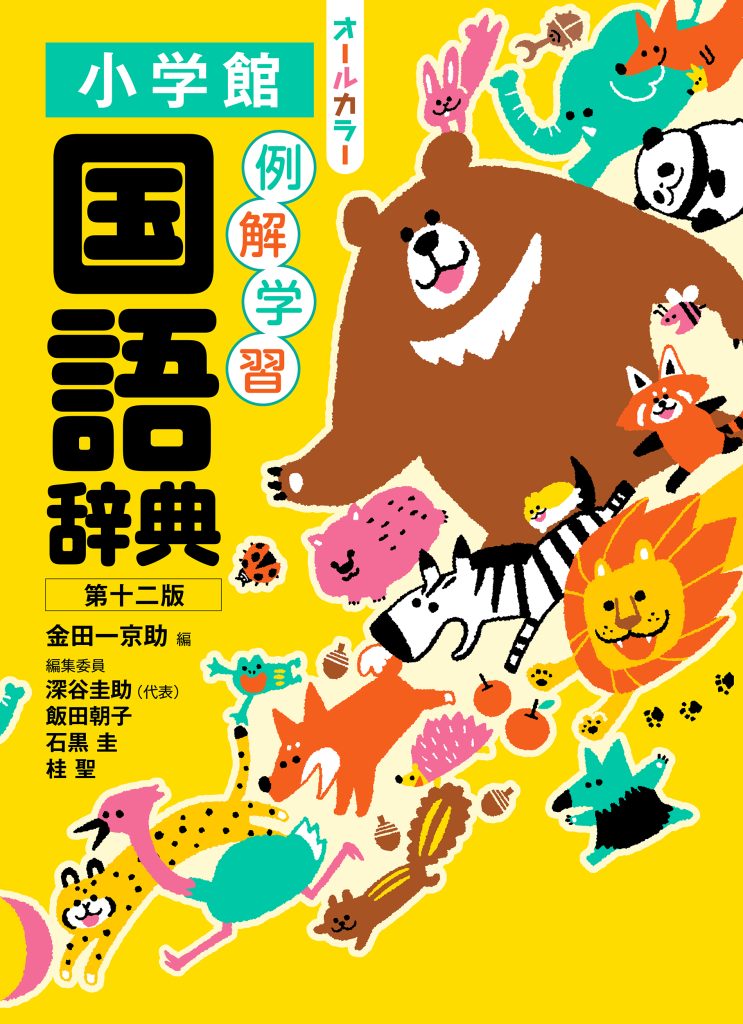
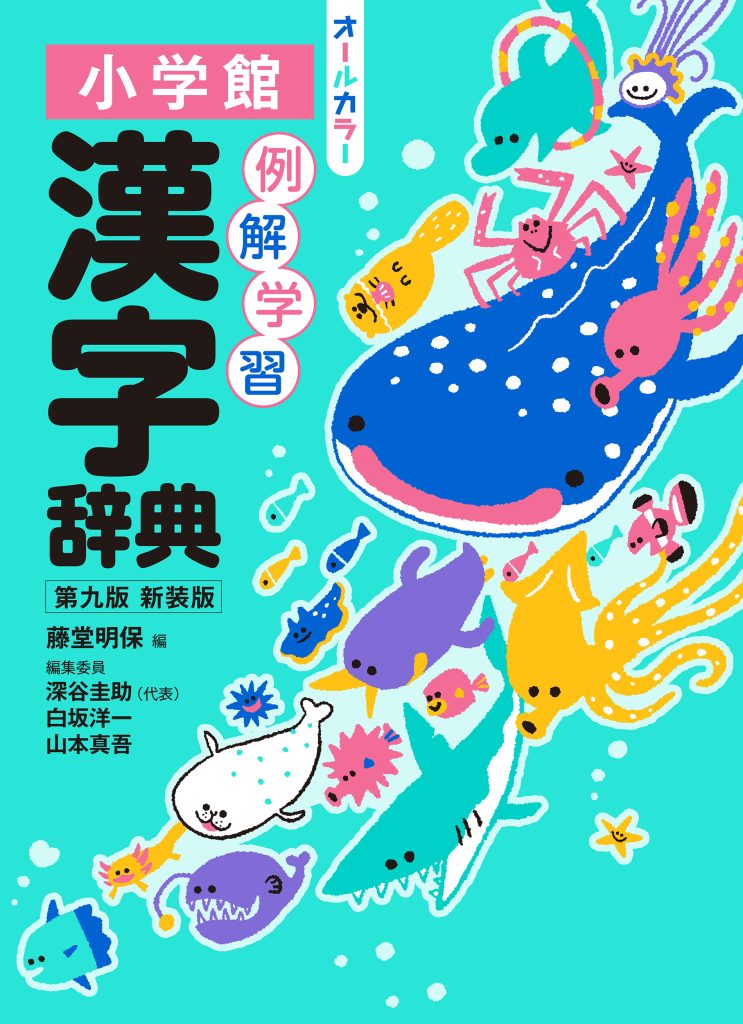
なぜ「紙の辞書」で学ぶべきなのか
子どもたちにそうした喜びを感じさせるため、先生方や親御さんたちにお勧めしたいのは、身体の部位に関する言葉、日本の伝統行事や、四季折々の自然や季節の情感を表す言葉について調べるよう促し、丁寧に教えてあげることです。
身体の部位に関する語彙(肘、脛、膝、うなじ、こめかみ等)は、子どもたちにとって獲得しやすく、獲得すれば結果として自分自身の身体を大切にすることにつながります。
また、現代の都市部では実感しにくくなってきた季節感を表す語彙(春雨、薫風、夕立、鰯雲、木枯らし等)は、今後の子どもたちの人生を、より豊かなものにしてくれるでしょう。
目の前の子どもたちに対し、「今日は時雨が降っていたよね。時雨という言葉を、ちょっと辞書で引いてみようか?」といった言葉かけができる大人は素敵ですよね。
今の時代、知らない言葉の意味だけなら、インターネットで検索すればすぐに出てくるでしょう。
でも、その情報は基本的に大人向けのものです。そもそも「幼い子どもが受け取る情報」だという配慮はなされていません。アプリやサイトによっては、そもそも情報の信頼性が低い場合もあるでしょう。
そうしたことを踏まえると、これから「公」の社会へと旅立って行く子どもたちに最初に手渡してあげたいのはやはり紙の辞書だと考えています。
それは、これから先どんな時代になったとしても、ずっと変わらないはずです。
(2023年11月・高知市内のカフェにて)
辞書と一緒にプレゼントしたい! 特製「辞書カバー」を限定発売中です
菊池省三先生がそのクオリティの高さを認め、強くご推薦いただいた「例解学習国語辞典」や「例解学習漢字辞典」(B6判・小学館)が収納でき、持ち運びに便利な「辞書カバー」が、小学館パブリッシング・サービスから発売中です(ご購入はこちら)。
B6判であれば、どの出版社の辞書でも収納可能です。子どもたちの辞書の活用率をグンとアップさせ、たしかな国語力を手に入れてほしいという願いを込めた新商品です。
好きな写真や絵などを入れて自分流にデコれる正面のクリアポケットや、付箋等を入れられる小さな内ポケットも付いていて、学校や塾で「かわいい~!」と注目が集まること間違いなし!


価格:1,980円(税抜1,800円)
B6判(幅・約35㎝×高さ・約20㎝)
素材:ポリエステル・塩化ビニル樹脂 中国製
この特製「辞書カバー」は、以下の書店でお買い求めいただけます。
↓【取り扱い書店】
■有隣堂 横浜駅西口店(神奈川県)
■有隣堂 たまプラーザテラス店(神奈川県)
■有隣堂 テラスモール湘南店(神奈川県)
■有隣堂 アトレ目黒店(東京都)
■有隣堂 ららぽーと豊洲店(東京都)
■有隣堂 ニッケコルトンプラザ店(千葉県)
■ブックファースト 中野店(東京都)
■ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店(兵庫県)
↓【オンライン・ショップ】
※数に限りがあるため、最新の在庫状況は各書店にお問い合わせください。
この魅力的な商品、売り切れる前に、ぜひお買い求めくださいね。
Profile
きくち・しょうぞう。1959年愛媛県生まれ。北九州市の小学校教諭として崩壊した学級を20数年で次々と立て直し、その実践が注目を集める。2012年にはNHK『プロフェッショナル仕事の流儀』に出演、大反響を呼ぶ。教育実践サークル「菊池道場」主宰。『菊池先生の「ことばシャワー」の奇跡 生きる力がつく授業』(講談社)、『一人も見捨てない!菊池学級 12か月の言葉かけ コミュニケーション力を育てる指導ステップ』『「聞き合う力」「考え合う力」を鍛える授業』(小学館)ほか著書多数。
菊池省三先生の最新刊も、新たな提案性を孕んで好評発売中です。