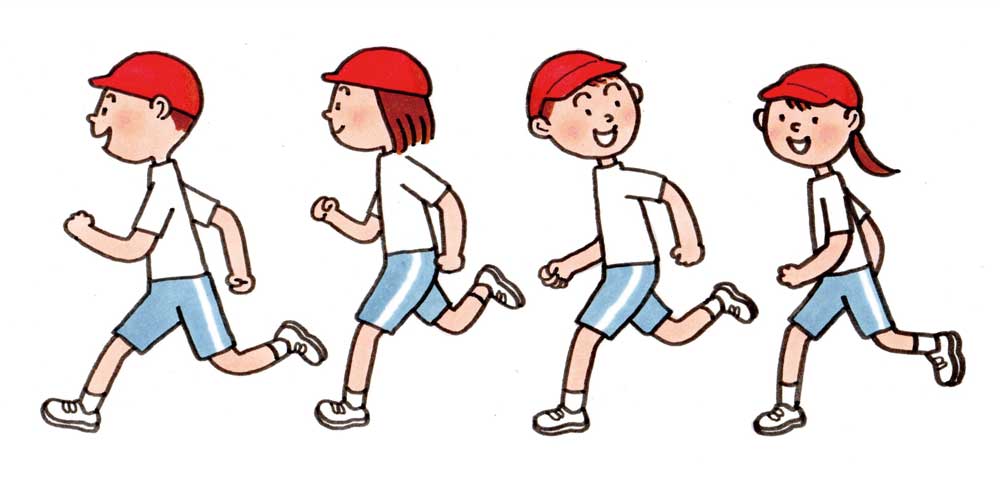子供が自ら意欲的に取り組む持久走(マラソン)指導〔Part1〕ダウンロードプリント付

子供たちに「次の体育は持久走(マラソン)です」と伝えると、「うぇー」「やだぁー」など、大体どの学級からも同じ反応が返ってきます。子供たちにとって持久走は、「つらい」「つかれる」「つまらない」の「3TU(つ)」のようです。長年、体育科、陸上競技の指導を行ってきた栃木県公立小学校校長・平塚昭仁先生に持久走の指導について、基本編・準備編の〔Part1〕、実践編の〔Part2〕に分けて教えていただきます。今回の〔Part1〕では、持久走の位置付けや持久走嫌いの要因、持久走の準備などを伝えます。
どのような授業を仕組んでいけば子供たちの持久走嫌いをなくせるのか、そして、子供たちが自ら意欲的に取り組める持久走とは何かを考えていきましょう。ダウンロードプリントもご活用ください。
執筆/栃木県公立小学校校長・平塚昭仁

目次
知っておきたい基本編
学習指導要領における持久走の位置付け
現行の学習指導要領(平成29年告示)では次のように位置付けられています。
低学年
A「体つくりの運動遊び」 (1)イ多様な動きを作る運動遊び (イ)体を移動する運動遊び
一定の速さでのかけ足・無理のない速さでかけ足を2~3分程度続けること
中学年
A「体つくり運動」 (1)イ多様な動きを作る運動 (イ)体を移動する運動
一定の速さでのかけ足・無理のない速さでかけ足を3~4分程度続けること
高学年
A「体つくり運動」 (1)イ体の動きを高める運動 (エ)動きを持続する能力を高めるための運動
時間やコースを決めて行う全身運動・無理のない速さで5~6分程度の持久走をすること
これまで、学習指導要領における持久走の位置付けは、時代によって大きく変わってきました。
昭和の時代は、持久走が自己記録の短縮や距離の伸び、競走の楽しさを味わうことがねらいとされている「陸上運動領域」に位置付けられていました。
昭和の終わりから平成のはじめにかけては、低学年「基本の運動」、中学年「陸上運動」、高学年「体操領域」に位置付けられ、これまでの陸上運動系だった内容が、競走にこだわらない持久走に変化してきました。
平成20年から現在にかけては、低学年「体つくりの運動遊び」、中高学年「体つくり運動」に位置付けられました。生涯スポーツの観点から無理のない速さでの持久走は継承されました。また、体力の必要性や体力を高めるための運動の行い方を理解し、自己の体力に応じて体力づくりが実践できることをねらいとしています。さらに、走り終わった後、「疲れたけれどすっきりする」「心臓がバクバクする」「友達と走って楽しかった」など、心と体の一体化、リフレッシュ、仲間との交流に関わることを気付きとして言語化し、子供たちにフィードバックすると、学習指導要領のねらいに近付きます。
子供が持久走を嫌いな理由
持久走は、好き嫌いがはっきり分かれる種目です。
好きな子供のなかには、「休み時間も走っていいですか」と聞きにくる子供がいるくらいです。
しかし、アンケートを見ると、体育で嫌い・苦手な種目の上位に持久走がランクインします。
これは、昔に比べ体力が低下していると言われている現代の子供たちにとって、長い距離を続けて走ること自体、体力的、精神的に苦痛と感じるのではないかと推測します。また、走りたくないのに距離を決められ、競いたくないのに順位を付けられることも持久走を嫌う要因の1つかもしれません。
逆に教師側は、そんな子供たちに持久走を通して体力を付けさせたい、精神力を鍛えたいという思いが強く、記録の短縮や競走をメインとした授業で子供を過度に追い込むことがあります。指導にも熱が入り、疲れて歩き出した子供に対して「歩くんじゃない」と叱咤激励することもあります。この時、子供の「やらされ感」はMAXに達し「持久走なんて大嫌い」となります。しかし、直接その思いを教師にぶつけられないので、保護者に教師の愚痴を言ったり風邪をひいたと次の体育を休んだりします。あの子が休むなら私もと体育の見学者が増えていくこともあります。
こうした教師と子供の意識の差が、子供たちの持久走嫌いを加速させている要因とも考えられます。
また、持久走は「早い・遅い」が誰から見てもはっきり分かってしまいます。体育はどの種目もこの傾向がありますが、なかでも、持久走は一番その傾向が強いのではないかと思います。例えば、短距離走は一瞬で終わってしまいますが、持久走は何分間かずっと走り続けなくてはなりません。苦手な子供にとっては遅い順位のままずっと走り続けることになります。しかも、最後にゴールした子供はみんなから拍手をもらうことがあります。その拍手を素直にうれしいと思う子供もいれば、いやだと感じる子供もいます。
持久走大会の移り変わり
昭和の時代は、持久走大会が学校行事に位置付けられていた学校が多くありました。
大会が近付くと、当日走る距離を安全に走れるよう練習の段階から競走させたり、自分の最高記録が出るよう何度も挑戦させたりしました。なかには、「体力づくり」と称して、長い休み時間に全校児童で持久走の練習を強制的にしていた学校もありました。これは、当時の学習指導要領で持久走が自己記録の短縮や距離の伸び、競走の楽しさを味わうことがねらいとされていた背景があったからです。
持久走大会は、得意な子供にとってはまたとない活躍の機会です。持久走大会の入賞者には賞状が出され、みんなの前で表彰されればなおさら嬉しいでしょう。保護者も応援に熱が入ります。
しかし、持久走の好き嫌いの2極化を生み出すことにつながっていったこともあり、現行の学習指導要領では「無理のない速さで5~6分程度の持久走をすること(高学年)」と内容が示されています。そう考えると、競走を伴う持久走大会は現行の学習指導要領にはそぐわないことになります。また、持久走大会またはその練習中において、命に関わる事故の発生が全国でいくつか報告されました。
そのような流れもあり、持久走大会を行わなくなった学校が多くなってきました。
それでも今なお、持久走大会を続けている学校が少なくないと聞きます。
続けている理由は、子供の体力を高めるため、活躍できる子供がいるから、伝統的に続いてきたからやめようとしたが保護者や地域の反対にあったなど様々です。
個人的には、現行の学習指導要領の目標に掲げられている「生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を培う」という観点から、一時の記録の短縮や体力の高まりを過度に目指すあまり、持久走嫌いな子を増やすことは小学生段階では避けるべきであると考えます。
大人になると人気のスポーツに変わる持久走
子供たちには人気のない持久走ですが、日本のランニング人口は1000万人に近いとも言われ、大人にとっては人気のスポーツとなっています。この逆転現象はなぜ起こるのかを考えていくと、小学生段階における持久走嫌いをなくしていくきっかけになるかもしれません。
なぜ、ランニングは大人に人気のスポーツなのでしょうか。
理由の1つに、健康のためということが挙げられます。ランニングは、つらいし疲れるけれども健康によいということが分かっているので続けられるのです。また、つらければつらいほど、走り終えたときの達成感は大きくなります。これが走る喜びにつながっているのだと考えます。
そのほか、道具がいらず自分1人でできることも大きな魅力の1つです。また、時間や場所を選ばず、自分にあった距離やペースで誰に気兼ねすることなく走ることができます。そうしたなか、自分の記録が高まったり走れる距離が伸びたりすることで、さらにやる気は高まっていきます。まったく運動に縁のなかった高齢者が、フルマラソンに挑戦するまでになったという話を聞いたこともあります。生涯スポーツとしてうってつけの種目と言えます。
このように、持久走には素晴らしいメリットがたくさんあるにもかかわらず小学生に人気がないのは、そのメリットを子供たちが理解していない、走る距離や練習方法が決まっていてやらされ感が大きい、個人差に対応していないなどの理由が考えられます。体育のなかでこうしたことを解消できるような実践が必要になってきます。