小四後半期突入!ここで見直す、算数の授業づくり

二学期になりました。今年度もいよいよ後半のスタートです。年度はじめに描いた算数の「授業づくり」について、このタイミングでしっかり見直して、子供たちを積み残しなく高学年へと進級させるようにしましょう。ノート指導、単元指導の見直しについて解説します。
監修/大阪府公立小学校教諭・岡本美穂
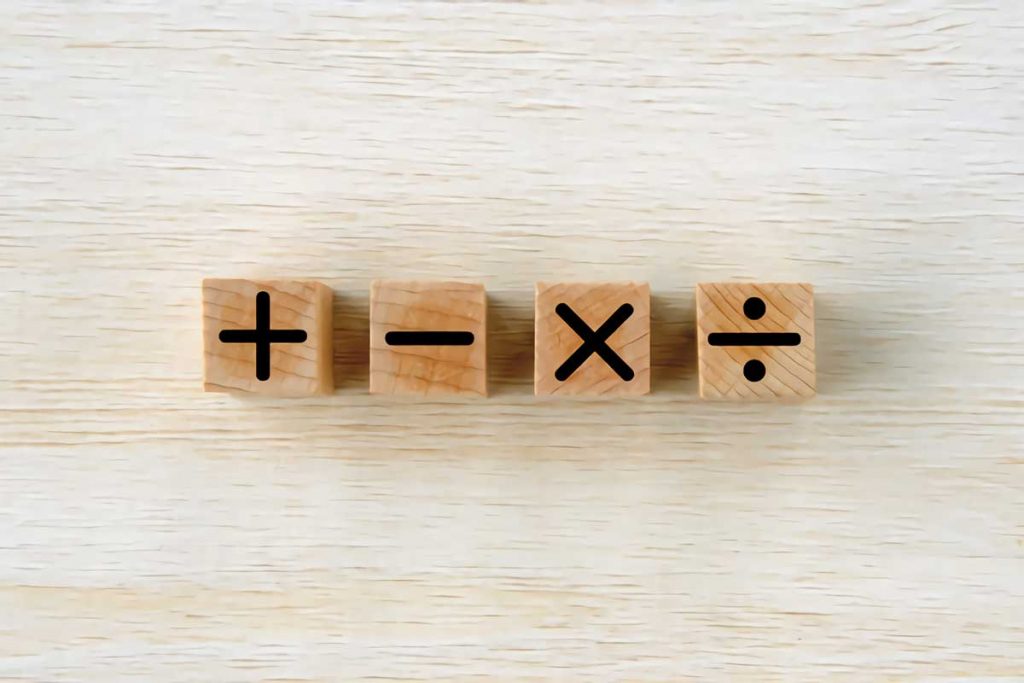
目次
授業計画の見直しポイント
算数ができない子とできる子の差とは何でしょうか。できない子と普通の子の差は、理解度の差です。できない子は、そもそもの知識が少なかったり、解法を理解していなかったりもします。
しかし、できる子と普通の子の差は、定着度です。理解度はあまり変わりません。知識もあまり変わりません。
できる子は、しつこく解いていますし、こまめに解いています。安定して9割以上の点数が取れるような子は、しつこく同じ問題を解きます。ケアレスミス・計算ミスにも厳しいのです。つまり理解度ではなく、定着度で差が付くということです。
この定着度は、学級の友達と一緒に取り組むなかで得られるものではないでしょうか。「自分の脳は自分で鍛える・みんなで鍛える」ということを二学期の算数の授業では目指しましょう。
子供は、みんなで仲間の成長を喜ぶことができます。また、子供は認めてあげるとやる気を出すことができるのです。
ノート指導の見直しポイント
めあて、ふり返りを書くことばかりに縛られないことが大事です。もちろんこの2つは土台となります。しかし、めあてあっての中身なし、めあてはあるが授業は何をしたのかわからない、ということもよくあります。
そこで、二学期には自分でめあてをノートに書くということもチャレンジしてみましょう。そして、少しずつオリジナルのノートづくりができることを目指しましょう。
それだけでなく、計算ドリルの間違い直しなどもノート指導に生かしましょう。計算ドリルが終わって答え合わせをした後、
「過去に戻って計算ドリルを行う自分に、その問題を間違えないようにアドバイスを書いてあげましょう」
と言うこともおすすめです。


