第58回 2022年度 「実践! わたしの教育記録」審査員選評
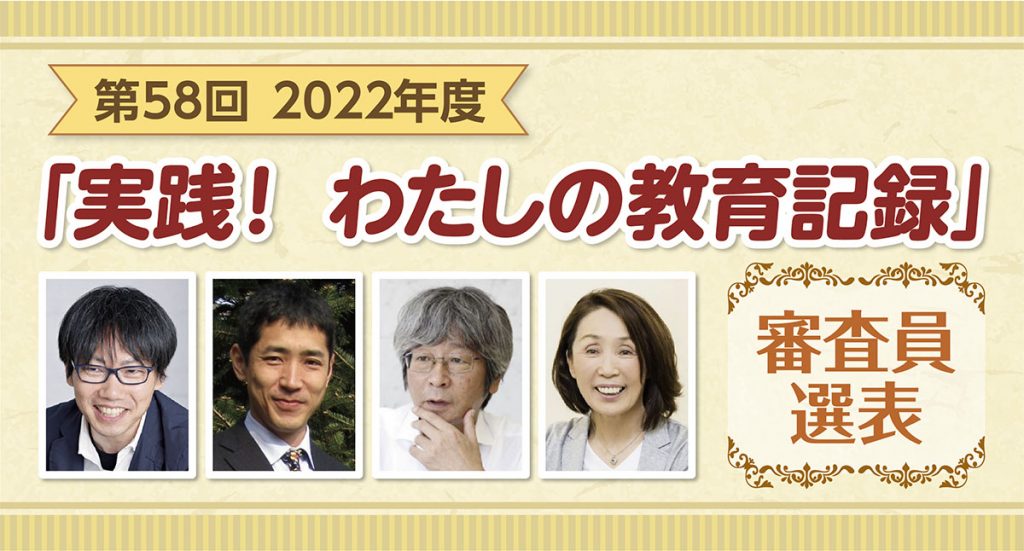

第58回「実践! わたしの教育記録」入選者が発表されました。4人の審査員の方々から、入選作品についての選評を伺いました。
目次
これからの教育界をアップデートさせる可能性を感じる取り組みの数々に感銘を受けた

上越教育大学教職大学院教授・赤坂真二さん
まず、特選の北島幸三氏の実践であるが、PTA役員からの提案を生徒との思い出を創るだけでなく、教育の機会にしようとした氏の着想に敬意を表したい。保護者の思いに賛同する形で活動を立ち上げ、生徒を巻きこみ、学校、地域を巻きこんでいったプロセスが無駄なく端的に記録されていてドラマを見ているようだった。生徒の主体性を引き出しながら、生徒や保護者の協働を組織していく一連の流れは、魅力的な学校づくりのヒントが満載だった。
特別賞の久冨哲朗氏の記録は、「発信・共有」をベースとした社会科授業の改善という問いがシャープで、協働学習、個別進度学習、そしてICTの活用というバラエティー豊かな取り組みが、ばらけることなく一貫性をもって子どもの変容を伝えていた。
入選の授業・学級づくり部門の一編、水流卓哉氏は、現在の学級活動における話合い活動の問題点を鋭く突き、それを改善するための手立て、また、話合い活動のプロセスにおいて明記することが避けられがちなルール面も正面から取り上げ、再現性の高い実践報告となっていた。同部門入賞の友田真氏の実践は、今注目されるUDL実践の具体的な記録として価値がある。可能な限り無駄な情報を省いて、授業で起こった事実を忠実に述べたことでより説得力を感じた。
入選の授業・学校づくり部門の宮森正人氏の実践は、生徒の主体性を高めるためのしかけの一つひとつが素晴らしく、教師としての覚悟を感じさせるものだった。特に生徒の手によるクラス替えの実践は圧巻であった。同部門入選の窪田悠氏の実践は、現在の学校組織において足枷になっていると言われるPTA活動の在り方に斬り込んだ。近未来的であるようでいて、すぐに実現可能な取り組みとして希望を感じさせる実践であった。
新採・新人賞の中原修平氏の実践は、一まとまりの動きをつくるまでの即興表現の経験値を上げる、話合いによって動きを高め合うなど、打つ手の一つひとつがとても効果的。それをプログラミング的思考の枠組みでまとめたことが斬新だった。
優れた実践ばかりで、優劣を付けることがとても難しかった。これからの教育界をアップデートさせる可能性を感じさせる、新規性のある取り組みが多々あり、感銘を受けた。
新しい教育の担い手=新採・新人賞部門の読み応えのある実践記録の数々に頼もしさを感じた

学校法人 軽井沢風越学園校長、軽井沢風越幼稚園園長・岩瀬直樹さん
コロナ禍も3年目となった。現場での状況はしんどさを増し、大人の働き方にも、子どもたちの育ちにも大きな影響が見えてきている。このような状況の中、情熱的な実践記録をたくさん読ませていただき、このような現場での子どもたちとの試行錯誤が学校教育を支えているのだと熱い気持ちになった。
特選の北島幸三さん。生徒はもちろん、北島さん自身の生徒への熱い想いが伝わってくる記録である。コロナ禍の制限のマイナスにフォーカスするのではなく、その中で培われた強みに焦点を当てた実践。「何をするか」の前提として「何のためにやるか」という目的を深掘りしているところに、プロジェクトベースとしての価値がある。生徒の幸せそうな顔が浮かんだ。つくづく学校とは「幸せな子ども時代」を過ごす場なのだ。
特別賞の久冨哲朗さん。バズワード化している自由進度学習であるが、教材研究と綿密な授業デザインが支えることを実践で示した好例である。評価の透明性も提案性が高い。この学びを経験した学習者の声・成長など個の変容まで記録されると、さらに実践記録としての価値が高まるだろう。
入選の水流卓哉さん。丁寧にプロトコルを記述し、実践の具体が伝わってくる。先行実践を調査することでさらに豊かな実践になるだろう。友田真さん。UDLの視点を活かしつつ、一人ひとりの問いから出発する探究的な学び。教師の関わりについて熱く記述してほしかった。宮森正人さん。一つひとつの実践は興味深く、その価値が伝わってくる。総花的でTIPS集のようになってしまったので、具体の記述を読みたい。窪田悠さん。PTAの新しい形として興味深い内容。このような実践記録が増えていくと面白い。
新採・新人賞の中原修平さん。表現とプログラミング思考を掛け合わせたユニークな実践。個の変容を読みたかった。新採・新人賞部門は読み応えのある実践記録が多く、頼もしい限りであった。この世代が新しい教育をつくっていくのだろう。だからこそ謙虚にたくさん学び、たくさん実践記録を世に問うてほしい。

