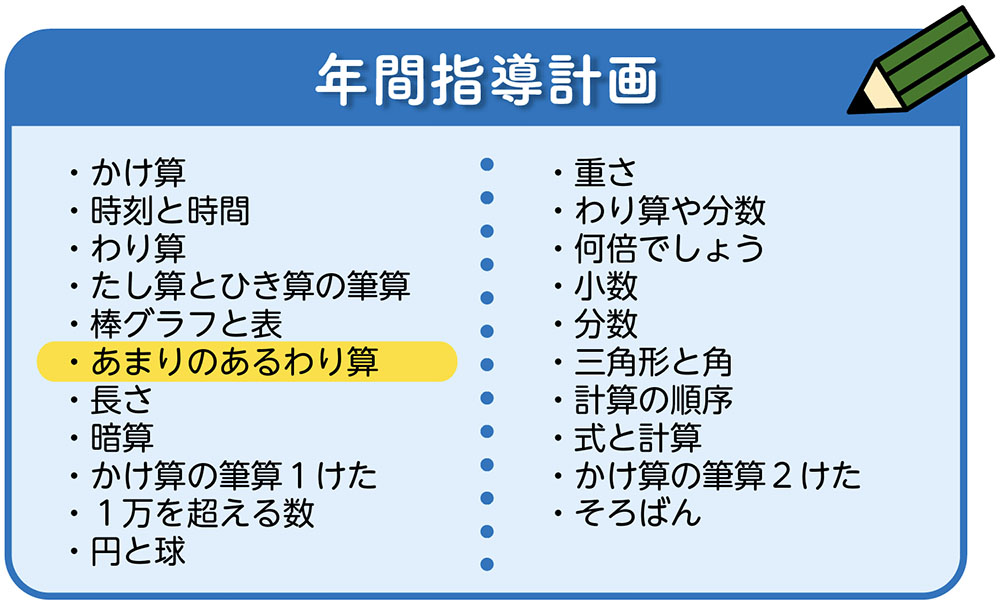小3算数「あまりのあるわり算」指導アイデア《問題に応じた商の処理のしかた》
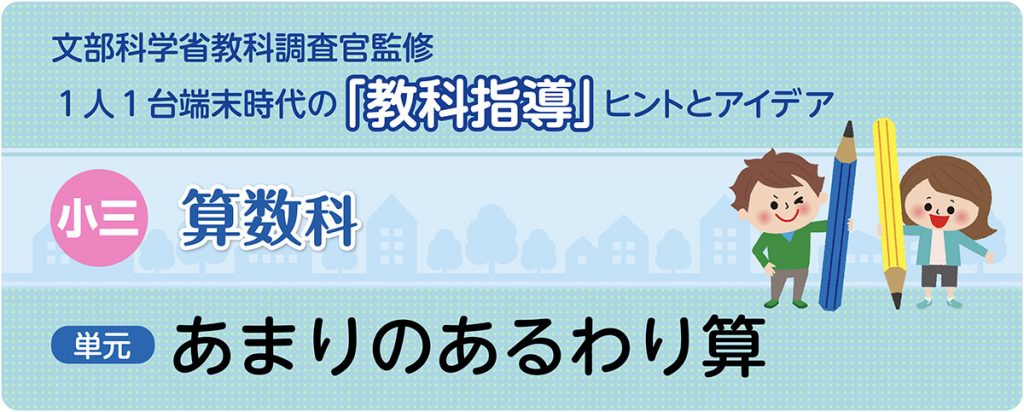
執筆/神奈川県横浜市立大綱小学校教諭・小畠政博
監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、島根県立大学教授・齊藤一弥
目次
単元の展開
第1・2時 わり切れない場合の計算のしかた(包含除)14÷3
▼
第3時 わり切れない場合の計算のしかた(等分除)16÷3
▼
第4時 わり切れない場合の除法の答えの確かめ方
▼
第5時(本時)問題に応じた商の処理のしかた(あまりを考える問題)
▼
第6時 まとめ
本時のねらい
商やあまりの意味に着目して、問題に応じた商の処理のしかたを考え、説明することができる。
評価規準
商やあまりの意味に着目して、日常生活の場面に照らし合わせながら、問題に応じた商の処理のしかたについて考え、説明している。

35人の子どもがすわれるように、4人がけの長いすを用意します。
どのような場面か、説明できますか。
35人の子供が、4人がけの椅子に座っていく場面です。
同じ数ずつ座っていくので、いくつ分かを求めるわり算の場面です。
何を求めているのか分からないので、計算ができません。
いくつ分かを求めるわり算の場面と考えると、「長椅子はなん台用意すればよいですか」になると思います。
では、問題をこのようにします。式を書き、答えを求めましょう。

35人の子どもがすわれるように、4人がけの長いすを用意します。長いすは、なん台用意すればよいですか。
「35÷4=8あまり3」なので、長椅子は8台用意すればいいと思います。
計算の答えの確かめも大丈夫だったので、いいと思います。
でも、おかしな問題だね。かわいそうだよ。
それは、どういうことですか。
だって、3人座れない人がいたらかわいそうです。
わり算で計算したら、「8あまり3」だから、8台になると思うよ。
あまりが3だけど、本当に長椅子は8台でいいのかな。35人の子供が座れるようにと書いているから……。
では、もう一度、長椅子がなん台必要か、考えてみましょう。

「35÷4=8あまり3」の商とあまりの意味に着目し、問題場面に応じた商の処理のしかたについて考え、説明することができる。
見通し
○を使った図を用いて、答えの8と3が何を表しているのか考えればいいよ。[方法の見通し]
答えは8あまり3だけど、あまりを出さない場面だから、状況によって答えが変わるよ。[方法の見通し]
答えの8あまり3は、4人ずつ8台に座ると3人余るということなので、3人が座るために、もう1台必要になるよ。[結果の見通し]
自力解決の様子
A つまずいている子
あまりの処理のしかたが分からず、困っている。
B 素朴に解いている子
○を使った図を活用し、あまりの3個をひとまとまりにして考えている。
C ねらい通り解いている子
商とあまりの意味に着目し、場面に応じた処理のしかたに気付いている。
学び合いの計画
除法で解決した結果をそのまま答えとすることを本時のゴールにしていません。除法での処理の結果である商とあまりを、もう一度問題場面に照らし合わせて妥当であるかどうか判断し、結論を得ることが大切です。
イラスト/横井智美